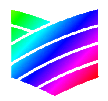
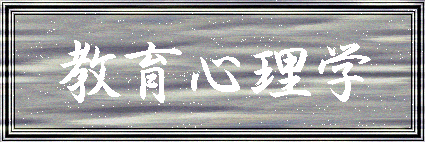
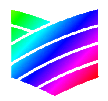
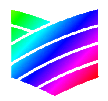
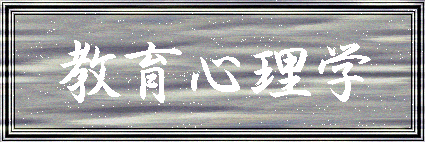
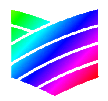
46期 荒井良一(西川ゼミ)
| 問題と目的 心理学の古典的研究の一つに、「欲求不満・攻撃仮説」が存在する。この説は、欲求不満によって、攻撃が生じるという、イェール大学人間科学研究所のダラード(1939)等の説である近年は、バーコビッツ(1989)が、不快情動説という、より洗練された理論を展開している。 攻撃について研究したパストーレ(1952)やコーヘン(1955)は、不合理な欲求不満(目標達成行動を妨害する障壁・干渉に根拠がない、あるいは悪意に満ちた不合理なもの)と合理的欲求不満(目標達成行動を妨害する障壁・干渉に根拠がある、あるいは不可避的であると見なされるもの)では、前者のほうが攻撃的に反応すると述べた。そして、欲求不満の不合理性は最近になって、原因帰属の視点から新たに取り上げられた。 ルール、ディック、ネスデール(1978)やドッジ(1980)の研究では被害の大きさが等しい状況下で、欲求不満の原因に関する情報(起因情報)を操作するlことによって、被害者の攻撃反応に変化が観察された。その理由は、起因情報が欲求不満の不合理の知覚に影響を与えるためと考えられた。 起因情報として、従来の研究では主として、意図の有無(加害は故意か否か)や意図の社会性(動機が利己的か利他的か)が取り上げられてきたが、大淵(1981)は、これらを整理して、欲求不満の不合理性判断に影響する起因情報を次のように分類した、(表1参照)
|
| また、加害者と被害者との関係も、無視できない要因の一つである。大淵(1986)の研究では、家族・恋人といった親しい人には、怒りを抑制せず、思った通りの攻撃行動を実行したが、よく知らない人・親しくない人に対しては攻撃を強く抑制した。バロン(1979)は憎んでいる人に対しては、攻撃反応は促進されると主張した。 そこで本研究では、対人条件(親しくない人・親しい人・嫌いな人の3条件)と欲求不満条件(過去・過失の2条件)を組み合わせて、調査を実施した。攻撃反応は対人条件と欲求不満条件のどちらに強く喚起されるか、それを比較検討するのが、本研究の目的である。 |
| 仮説 (1)各々の条件において、怒り尺度と攻撃尺度には、正の相関がある。 ※なぜならば、Averill(1979)が開発した質問紙「怒りの日常的経験」を使った大淵・小倉(1984)の研究によると、怒りを感じた人の94%が何らかの攻撃行動に動機づけられ、そのうち70%の者が攻撃行動を実行した。つまり、怒りと攻撃行動の間には、正の相関があるといえよう。 (2)各々のの対人条件において、合理的欲求不満と不合理な欲求不満では、不合理な欲求不満の方が強くなる。 ※大淵(1982)の「欲求不満の原因帰属と攻撃反応」では、怒りについても、攻撃と同様に、合理的欲求不満と不合理な欲求不満では、不合理な欲求不満の方が強く出た。これと同様の結果が出るであろう。考察で詳しく触れるが、反応抑制説ではなく、動因低減説を支持するであろうと思われる。 (3)各々の欲求不満条件において、親しくない人、親しい人、嫌いな人の順に怒り・攻撃反応が強くなる。 ★なお、対人条件と欲求不満条件では、どちらがより強く攻撃を喚起するか、予測をたてる材料に乏しいので、この問題について、仮説を立てることはできなかった。 |
| 方法 ◆欲求不満物語と実験条件 大淵(1982)が作成した欲求不満物語を元に、対人条件(親しくない人、親しい人、嫌いな人の三つの条件)を組み合わせて、新たに作り直した。欲求不満物語の内容は次の通りである。 「あなたは、Xさんとドライブに行く約束をしました。寒い街角で、あなたは、Xさんを待ちましたが、一時間過ぎてもXさんは来ません。」 ※Xさんは、親しい人・親しくない人・嫌いな人を示唆しています。 物語の骨子は変えず、Xさんの欲求阻止行動の原因に関する情報を操作することによって、2種類のバリエーションを作った。一つは「過失」・・・「後日、Xさんに会い、理由を聞くと、『忘れてた。』とあっさりいわれてしまいました。」もう一つは「事故」・・・「あとでXさんに理由を聞くと、『車が故障していけなかったんだよ。連絡できなくてごめん』といわれました」 ◆従属変数 「過失」・「事故」の2つの問題状況について2つの質問が行われた。被検者は各質問において、五段階評定が求められた。 質問1(怒り測度)「あなたは怒りますか」 質問2(攻撃測度)「あなたはXさんを責めますか」 どちらの測度においても、高得点であるほど当該反応や態度が、強く推測されたことを表す。 ◆手続きと被検者 実験は、三重大学の大学生を対象に、講義時間を利用して行われた。被検者の人数は合計275名。実験に要した時間は訳10分であった。 |
| 結果及び考察・・・Table.1,2参照 1:仮説1について 怒りと攻撃の間には、正の相関が見られた(p<0.001)。怒りが強ければ強いほど、攻撃的に反応することがわかった。 |
| 2:仮説2について 各々の対人条件において、不合理な欲求不満における怒り・攻撃反応と、両者について、対応のある2群の母平均値の差の検定を行った。それぞれについて有意な差が見られ(p<.001)、前者の方が、怒り・攻撃得点は高くなった。 合理的欲求不満に攻撃反応が起こらない仕組みについて、Worchelらは反応抑制説を主張した。それによると、被害者は内面では、欲求不満(合理・不合理にかかわらず)によって怒り(攻撃動因)が喚起されるが合理的事態では攻撃行動を抑制する(Burnstein&Worchel,1962;Rothaus&Worchel;1960)。 しかし、本実験結果では、怒り測度にも欲求不満条件の効果が見られ、被害者は合理的欲求不満に対しては、不合理な欲求不満ほどには怒りは感じていないと評定された。怒りなどの情緒体験自体も欲求不満条件によって影響を受けることは、他の研究領域からも指摘されているので(Schachter&Singer,1962; Zillman,1978)、内的情緒の水準において既に、欲求不満の不合理性に対応する差異が生じても不思議ではない。 以上のことから、本研究は反応抑制説ではなく,Rule(1978)らの動因低減説を支持する。この結果は、この研究の元になった大淵の「欲求不満の原因帰属と攻撃反応」(1982)と同様のものである。 |
| 3:仮説3について 不合理な欲求不満において、「親しい人・嫌いな人」、「親しくない人・嫌いな人」のそれぞれの組み合わせで、対応のある2群の母平均値の差の検定を行った。 それぞれの組み合わせについて有意な差が見られ(p<.001)、親しくない人・親しい人・嫌いな人の順に反応が強くなり、仮説は支持された。 合理的欲求不満についても同様の組み合わせで、対応のある2群の母平均値の差の検定を行った。怒り測度では、親しい人・親しくない人の両者で、有意な差が見られた(p<.05)。 攻撃測度では、親しい人・親しくない人の両者で、有意な差が見られなかったが(p=0.281>0.10)、それ以外の組み合わせでは、有意な差が見られた(p<.001)。親しくない人・親しい人・嫌いな人の順に反応が強くならず、仮説は支持されなかったが、この3条件において、嫌いな人に対しての攻撃反応が、もっとも強くなるということは分かった。 |
| 4:攻撃反応は対人条件と欲求不満条件のどちらにより強く喚起されるか 嫌いな人が与えた合理的欲求不満における怒り・攻撃反応と、親しくない人が与えた不合理な欲求不満における怒り・攻撃反応の両者で、対応のある2群の母平均値の差の検定を行った。それぞれについて有意な差が見られ(p<.001)、後者の方が怒り・攻撃得点は高くなり、攻撃反応は対人条件より欲求不満条件に、強く喚起されるという結論に達した。 |
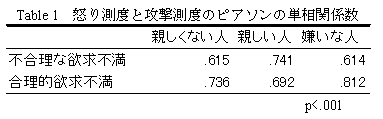 |
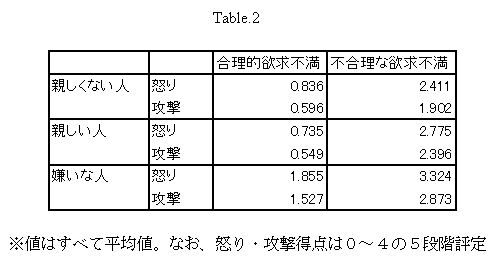 |