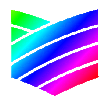

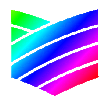
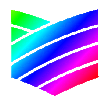

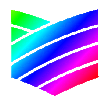
46期 145番 水谷慶子
| Ⅰ.問題および目的
他方、子どもを受容し許容的な態度の母親は、子どもの独りでの探索や行動を支持してくれる.このような親の下での子どもは、自律的独立的行動を多く示すようになり、自信を持って外界とかかわる.こうした経験によって、こどもは新しいことでも「自信を持って遂行することに動機づけられる.このような自信、外界への興味や積極的な働きかけは、学校生活や家庭での学習意欲にもつながるものと考えられる. 親の学習行動へのしつけのテクニックが子どもの達成目捷の形成に影響するとした研究が多くなされてきたがその一つに、速水(1991)が小学校6年生を対象として調べている.
一方、親が子どもの学習過程を大切にし長期的視点にたって励ましていくといった「間接的励まし」のしつけテクニックを用いるとき子どもは学習すること自体が目標となるラーニング・ゴール(LG)の目標を形成し、それによって動機づけられることを示した. |
| しかし、この速水の研究も含めて、今までの研究において親の養育態度を親自身がどのように認知しているか親に対して尋ねる研究が多くなされてきたが親の養育態度を誰が評定するのかは重要な問題である.親の養育態度の評定については 1)親の自己認知にもとづくもの 2)子どもの認知にもとづくもの が考えられる. |
| しかし本研究では、親自身の認知だけでなく子ども自身の子どもの側からの認知も検討していく.なぜなら、親の態度によって影響を受けるのは子ども自身でありその子どもが親の態度をどのように感じ、対処するのかということに意味があると考えられるからである. またそこで生ずる親の子どもに対する養育態度の認知と、子ども自身の親に対する養育態度の認知の差も検討していく.また、両親の養育態度として父親・母親と分けた研究報告は少ない.両親の養育態度は必ずしも一致しておらず、むしろ考えかたや態度が一致していない場合のほうが多いのではないか. したがって、本研究では父親・母親それぞれについて調査し子どもの学習意欲への影響について検討する. |
| Ⅱ.方法
1.被験者 調査は三重県下の2つの小学校5年生4クラス全員(147名)とその父親・母親それぞれを対象に調査が実廃され、親子の資料がそろっている124組が研究の対象とされた.
|
| ①学習動機傾向の測定(5段階測定 21項目) 速水が小学校6年生を対象とした学習動機の調査を参考に項目を作成した・因子構造は現実志向動機、理解志向動機、確認志向動機の3因子が明らかとなっている.
|
| Ⅲ.結果 1)子どもが認知する両親の養育態度と学習動機との関係 子どもが認知する両親の養育態度と学習動機の相関を男女別に見たものが表1-1,1-2である。
男子・女子に共通して父親の間接的励ましが理解志向動機(わかること自体が楽しくおもしろいために勉強する、すなわち好奇心や向上心が中核となる)の形成に影響している.
また数値を見てみると、男子においては父親よりも母親の間接的励まし型が理解志向動機と高い相関をもつのに対して女子ではその逆で母親よりも父親の間接的励まし型と高い相関をもった. つまり、異性の親の影響を強く受けていることがわかる。同じように現実志向動機や承認志向動機についても同じことがいえる.またこれらの結果は親自身に尋ねた養育態度よりも子どもが認知する両親の養育態度との間に高い相関が見られたことから学習動機に影響するのは子どもが親の態度をどのように認知しているのかが学習動横を左右する大きな要因であるといえよう. |
| (2)学習動機について
一方、理解志向動機と承認志向動機との問にはほとんど相関が見られなかったことから、理解志向動機と承認志向動機は独立のものであることがわかる.
|
| 3)子どもの認知する親の養育態度の性差について また、性別における子どもの認知する親の養育態度の平均値の差を見たものが表3である。女子の父親よりも男子の父親の方が直接的統制の態度が強く、その傾向は親自身の認知よりも子どもが認知する親の養育態度の方にみられた。 また、親自身の認知する養育態度においては性別においてほとんど差が見られなかった。
|
| Ⅳ 考察
また、直接的統制の態度は子どもにとって、支配的、強制的な親として受け取られているようである。自ら目標をもって、勉強を楽しんでやるというよりは、両親に承認されることや拒否されることを避けることを目標にするようになると考えられる. |
| また、平均値からみる限り、小学校5年生に対しては直接的統制よりも間接的励ましの方が多くなされているようであるが学習結果だけを重視する近視眼的な姿勢は子どもから学習を楽しむ態度を奪い、目の前の大人からの承認を得、拒否を避けるために学習するといった目標を設定させやすいと考えられる.逆に学習過程の努力に対して励ましてやることが学習目標の設定に寄与すると考えられる. ところでよい学校に進学することを目的とする現実志向動機と親の働きかけとの関係は複雑である。なぜなら、間接的励ましの直接的統制との間にも正の相関が見られたからである。現実志向動機の形成には一方で子どもの学習過程を重視し、他方では学習結果も重視するといったような一見矛盾するような働きかけが作用すると思われる。 |
| Ⅴ.今後の課題 本研究では3つの学習動機を別々のものとして扱ってきたが個人個人のなかではそれらが様々な形で組み合わされている,それらの組合せなり動機の型や学習成績との関係を検討することは今後に残された興味深い課題の一つである。 たとえば現実志向動機が強ければ承認志向動機も強く学業成績の動機づけへと作用するかもしれない.また、本研究では両親の養育態度の組合せによる影響まで検討していないので今後の課題としたい。 |
| そして、本研究では5年生の1学年だけの調査としたが、学年が上がるにつれてまた、中学生や、高校生とは学習動機が異なるかもしれない。 受験を控えた生徒はよい成績をとることが目標とされ、深く理解しないまま、記憶するというようなことがなされているかもしれない.したがって、学年差についての研究も今後の課題として研究したい. |