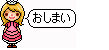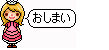
Ⅵ 考察
1)笑顔表出の主効果について
活動性についての印象評定では、笑顔を表出しない場合よりも初期または終期に笑顔を表出した場合の方がポジティブな印象を抱かれたことから、先行研究(横矢,2002)通り笑顔を表出しない場合よりも笑顔を表出した場合の方がポジティブな印象を抱かれたことは示されたが、初期笑顔表出群と終期笑顔表出群の間に有意な差が見られなかったため、初頭効果と新近効果のどちらがより有効であるか、ということは示されなかった。
個人的好ましさについての印象評定では、笑顔を表出しない場合よりも終期に笑顔を表出した場合の方が、また、初期に笑顔を表出した場合よりも終期に笑顔を表出した場合の方がポジティブな印象を抱かれた。よって、初頭効果よりも新近効果の方がより強く現れたと考えられる。また、今回の研究においては、笑顔を表出しない場合と初期に笑顔を表出した場合とでは印象評定に有意な差が見られなかったことから、個人的好ましさについては、表出時期によっては必ずしも笑顔を表出しない場合よりも笑顔を表出した場合の方がポジティブな印象をもたれるとは言えないことが示された。
協同・交遊についての好意度の評定では、笑顔表出×被験者の性に交互作用が見られたが、笑顔の主効果を見ると、笑顔を表出しない場合よりも終期に笑顔を表出した場合の方が好意度が高くなり、また、笑顔を表出しない場合よりも初期に笑顔を表出した場合の方が好意度が高くなる傾向にあった。初期笑顔表出群と終期笑顔表出群の間に有意な差は見られなかったが、統制群と初期笑顔表出群、または終期笑顔表出群とのそれぞれの差の有意確率の大きさを考慮すると、初頭効果よりも新近効果の方がより強く現れる傾向にあったと考えられる。
親密・承認についての好意度の評定では、笑顔を表出しない場合よりも終期に笑顔を表出した場合の方が、また、初期に笑顔を表出した場合よりも終期に笑顔を表出した場合の方が好意度が高くなった。よって、初頭効果よりも新近効果の方が強く現れたと考えられる。また、個人的好ましさについての印象評定と同様に、笑顔を表出しない場合と初期に笑顔を表出した場合とでは好意度の評定に有意な差が見られなかったことから、親密・承認については、必ずしも笑顔を表出しない場合よりも笑顔を表出した場合の方が高い好意度が得られるとは言えないことが示された。
印象形成において新近効果よりも初頭効果の方が強く現れる、という結果は全く得られなかったばかりか、活動性次元における印象形成以外の印象形成及び好意形成については、初頭効果よりも新近効果が強く現れていた。総合的に考えると、被験者の性や認知的熟慮性-衝動性によって様相は異なるが、初対面の女性が友人をつくることを目的として自己紹介をするとき、終期に笑顔を表出した場合の方が、初期に笑顔を表出した場合よりも相手によりポジティブな印象を抱かれ、また、より強い好意を抱かれる、と言える。これは、予想に反する結果であった。
初頭効果が強く現れなかった理由として、次のことが考えられる。本実験における刺激のVTRは、30秒程度と比較的短時間のものであったが、被験者がVTRのはじめの情報を多少忘却してしまっていた可能性がある。そこで、全体の印象を形成するときに、記憶に新しかったVTRの最後の情報が強く影響を与えたことが考えられる。これは、笑顔表出の時間をより長く設定することで検討しなおす必要がある。また、印象評定の活動性次元においては初頭効果と新近効果の現れ方に差が見られなかった。印象評定の個人的好ましさ次元や好意度の評定が他者に対して自分はどのように感じているか、という自分の個人的な感情をまきこむ主観的な印象であるのに対して、印象評定の活動性次元は個人的な感情の影響がほとんど現れない、他者に対する客観的な印象と考えることができる。このことより、客観的な印象の形成には初頭効果と新近効果の現れやすさに差が見られないが、主観的な印象の形成には初頭効果よりも新近効果の方が現れやすいのではないか、と考えられる。また、終期に笑顔を表出した場合の方が、初期に笑顔を表出した場合よりも相手によりポジティブな印象を抱かれ、また、より強い好意を抱かれたことについては、次のようにも考えられる。終期に笑顔を表出した場合については、はじめは笑顔の表出がなく、最後に笑顔の表出があったのは、刺激人物が自己紹介場面を撮影されることに最初は緊張していたが、徐々に緊張がほぐれて笑顔表出ができるようになったためだ、と被験者が考え、刺激人物は、いつもは笑顔表出の多い人物なのだと肯定的に捉えたと推測できる。一方、初期に笑顔を表出した場合には、はじめから笑顔を表出できていた(緊張していない様子)のに、徐々に笑顔表出がなくなっていったことから、刺激人物は、いつも笑顔表出のある人物なのかどうか疑わしいと捉えられたのではないだろうか。この場合、刺激人物が終期に笑顔を表出した場合は被験者は刺激人物に共感し、比較的好ましく思うだろうが、初期に笑顔を表出した場合には刺激人物に対して疑問が残り、前者に比べて刺激人物を好ましく思うとは考え難い。この個人的感情が、活動性次元以外の印象または好意の形成に影響を及ぼした、ということも考えられる。
2)被験者の性について
活動性についての印象評定では、被験者が刺激人物と同性であるか、異性であるかにかかわらず、笑顔を表出しない場合よりも笑顔を表出した場合の方がポジティブな印象を抱かれることが示された。
また、被験者の性の主効果が見られ、同性条件よりも異性条件の方が刺激人物に対してポジティブな印象を抱いた。これは、特に初期笑顔表出群と終期笑顔表出群で有意に認められた。笑顔統制群では被験者の性の単純効果が見られなかったことから、活動性についての印象評定においては、同性条件よりも異性条件の方が笑顔表出の有無による影響を受けやすいと考えられる。しかし、刺激人物と同性であっても異性であっても初期笑顔表出群と終期笑顔表出群の間に差が見られず、初頭効果と新近効果の現れ方に差が見られなかった。
個人的好ましさについての印象評定では、同性条件においては笑顔統制群よりも終期笑顔表出群の方がポジティブな影響を抱かれたことが有意に示されたが、その他の効果については有意差が見られなかった。また、異性条件においても笑顔統制群よりも終期笑顔表出群の方がポジティブな影響を抱かれる傾向にあった。このことから、被験者が刺激人物と同性であるか、異性であるかにかかわらず、終期に笑顔を表出した場合に限り、笑顔を表出しない場合よりもポジティブな印象を抱かれることが示された。
また、個人的好ましさについての印象評定においては、同性も異性も初頭効果よりも新近効果の影響を受けやすい傾向にあるが、異性よりも同性の方がその傾向が強いと考えられる。これは、同性は初頭効果と新近効果の現れ方に差がない、という予想に反する結果であった。
協同・交遊についての好意度の評定では、笑顔表出×被験者の性に交互作用が見られ、異性条件でのみ笑顔を表出しない場合よりも初期に笑顔を表出した場合の方が、また、笑顔を表出しない場合よりも終期に笑顔を表出した場合の方がそれぞれ好意度が高くなっていた。一方、同性条件では笑顔表出の条件間に有意な差は見られなかった。このことより、協同・交遊についての好意においては、同性では笑顔表出の有無による影響を受けにくいが、異性では笑顔を表出しない場合よりも表出した場合の方が好意度が高くなると考えられる。これは、横矢(2002)の研究結果と異なるものであった。本研究において見出された協同・交遊という好意の対人認知次元が、横矢の研究で好意度を測るのに用いられた対人認知次元と異なるものであったことや、横矢の研究で設定された笑顔表出は、本研究とは異なり、終始笑顔を表出するものであったこと、また、横矢の実験が実際の会話場面を用いて行われたのに対し、本研究では被験者がVTRを一方的に見ることによる実験であったことなどが理由として考えられる。
また、笑顔統制条件と初期笑顔表出条件の笑顔表出2条件×被験者の性2条件で交互作用が見られた。笑顔統制条件では被験者の性の単純主効果は見られなかったが、初期笑顔表出条件では同性よりも異性の方が強い好意を抱いていた。終期笑顔表出条件では被験者の性の単純主効果は見られなかったことも考慮すると、協同・交遊についての好意度の評定については、同性条件よりも異性条件の方が初頭効果が強く現れると言える。
親密・承認についての好意度の評定では、被験者が刺激人物と同性であるか、異性であるかにかかわらず、終期に笑顔を表出した場合に限り、笑顔を表出しない場合よりも好意度が高くなることが示された。
このことから、親密・承認についての好意度の評定においては、同性、異性とも初頭効果よりも新近効果が強く現れた、と言える。
また、協同・交遊次元の好意度の評定結果については、次のことが考えられる。協同・交遊次元の好意は、印象や親密・承認次元の好意と比較してその後の他者への接近により直接的に影響を及ぼすものと考えられる。刺激VTRは友人を作成する目的での自己紹介場面であった。女性の刺激人物と同性である認知者は、異性の認知者よりも相手の内面をより重視し、相手の本質を知った上で友人になりたい、と考える傾向が強いと思われ、初期印象がどうであれまずは話をしてみて相手をよく知った上で共に行動したいかどうかを判断する傾向にあるのではないだろうか。一方、異性の認知者は、相手の内面を知った上でなくても、相手の外見的な情報からポジティブな印象を抱いた場合には、共に行動したいと考える傾向が強いのではないだろうか。異性の場合、他者への接近性は同性よりも初期印象に影響されやすく、初期印象がポジティブであるほど、その他者と行動を共にしたいと考えるようになる傾向が強いと考えられる。これらのことを検討するために、対人魅力尺度の項目のうち、「会って話をしたい。」と共に行動したいかどうかを尋ねる項目の代表として「一緒に遊びたい。」について分析を行なった。「会って話をしたい。」については、笑顔表出、被験者の性を独立変数、項目の得点の平均を従属変数とした二要因分散分析において、交互作用も主効果も得られなかった。被験者の性の単純効果についても得られなかったことから、笑顔表出の全ての条件で、同性と異性は同程度「会って話をしたい。」と思っていたことがわかる。また、一要因分散分析の結果、同性条件では笑顔表出条件による差が見られなかったが、異性条件では差が見られ(F(2,59)=3.25,
p<0.05)、統制群<初期笑顔表出群に有意傾向が見られた(p<0.10)。一方、「一緒に遊びたい。」については、二要因分散分析の結果、笑顔表出×被験者の性の交互作用が見られた(F(5,132)=4.98,
p<0.05)。笑顔統制条件と終期笑顔表出条件では同性、異性間で差はなかったが、初期笑顔表出条件では同性<異性の単純効果が見られた(p<0.05)。よって、初期笑顔表出条件では、同性よりも異性の方が刺激人物と共に遊びたいと思っていたことがわかる。また、一要因分散分析の結果、同性条件においては笑顔表出条件による差が見られなかったが、異性条件では統制群<初期笑顔表出群に有意差が見られた(p<0.05)。これらのことから、会って話をしたいという気持ちはどの笑顔表出群においても同性と異性では差はなかったが、一緒に遊びたいかどうかとなると、初期笑顔表出群で男性の方がその気持ちは強くなった。また、同性では両項目とも笑顔表出条件によって差はなかったが、異性では「会って話をしたい。」では統制群よりも初期笑顔表出群の方が強い好意を抱かれる傾向にあり、「一緒に遊びたい。」でも同様の有意差が見られた。これは、上の考察を支持する結果だと言えるだろう。
3)被験者の認知的熟慮性-衝動性について
活動性についての印象評定では、初期笑顔表出条件と終期笑顔表出条件の笑顔表出2条件×認知的熟慮性-衝動性2条件で交互作用が見られた。初期笑顔表出群において認知的熟慮群よりも衝動群の方がポジティブな印象を抱いており、終期笑顔表出群においては衝動群よりも熟慮群の方がポジティブな印象を抱く傾向にあった。笑顔統制条件において認知的熟慮性-衝動性の単純主効果が見られなかったことを考慮すると、相対的に熟慮群よりも衝動群の方が初頭効果が強く現れやすく、衝動群よりも熟慮群の方が新近効果が強く現れやすいと言える。これは、予想通りの結果であった。また、両群ともに笑顔表出のない場合よりもある場合の方がポジティブな印象を抱き、さらに熟慮群では初期笑顔表出群よりも終期笑顔表出群によりポジティブな印象を抱く傾向にあった。これらのことから、熟慮群は初頭効果よりも新近効果の方が強く現れる傾向にあると考えられる。一方、衝動群は初頭・新近効果の影響の受けやすさに有意な差が見られなかった。
個人的好ましさについての印象評定では、熟慮群のみにおいて笑顔の表出がない場合よりも終期に笑顔を表出した場合の方が、また、初期に笑顔を表出した場合よりも終期に笑顔を表出した場合の方がポジティブな印象を抱いた。衝動群では、笑顔表出条件による有意差は見られなかった。このことより、個人的好ましさについての印象評定については、熟慮群は、初頭効果よりも新近効果の影響を強く受けたと考えられる。これに対して衝動群は、笑顔表出の有無自体による影響を受けにくいと言える。
協同・交遊についての好意度の評定では、熟慮群においてのみ笑顔表出のない場合よりも終期に笑顔を表出した場合の方が高い好意度を得られた。その他には有意な効果は見られなかった。初期に笑顔を表出した場合と終期に笑顔を表出した場合では有意差が見られなかったが、笑顔表出のない場合と初期に笑顔を表出した場合においても有意差が見られなかったことから、熟慮群は、初頭効果よりも新近効果が強く現れやすい傾向にあると考えられる。一方、衝動群は笑顔表出の有無自体による影響を受けにくいと言える。
個人的好ましさについての印象評定と協同・交遊についての好意度の評定において、衝動群は、1つ目に見た笑顔統制条件のVTRの影響を受けている可能性がある。1つ目の笑顔統制条件のVTRによって形成された刺激人物に対する印象が初頭効果となって2つ目のVTRの印象形成に影響を及ぼしたため、2つ目のVTRで笑顔表出をしてもしなくても印象形成に影響がなかったということが考えられる。
親密・承認についての好意度の評定では、熟慮群、衝動群ともに笑顔を表出しない場合よりも終期に笑顔を表出した場合の方が好意度が高かった。さらに、熟慮群では、初期に笑顔を表出した場合よりも終期に笑顔を表出した場合の方が好意度が高くなる傾向にあった。衝動群では、笑顔を表出しない場合よりも初期または終期に笑顔を表出した場合の方が好意度が高かった。これらのことより、熟慮群は初頭効果よりも新近効果が強く現れる傾向にあり、衝動群は初頭効果、新近効果の現れ方に有意な差が見られなかった。
これらのことから、活動性における印象形成においては相対的に熟慮群よりも衝動群の方が初頭効果が現れやすく、衝動群よりも熟慮群の方が新近効果が現れやすいことが示されたが、他次元での印象形成、また、好意形成については相手の認知的熟慮性-衝動性の違いによる初頭効果と新近効果の相対的現れやすさを弁別することができなかった。また、認知者の認知的熟慮性が高い場合においては、初頭効果よりも新近効果の方が印象形成及び好意形成に強く現れたが、認知者の認知的衝動性が高い場合には、初頭効果と新近効果の現れやすさに差が見られなかった、という予想外の結果が得られた。認知的衝動性が高い認知者についての結果は、最初と最後に与えられた情報を同程度利用したと考えると滝聞(1991)の研究結果と一致していたが、認知的熟慮性の高い認知者についての結果は滝聞の結果とは異なるものであった。認知的熟慮性の高い人は、速さよりも正確さを重視し、より多くの情報を利用して慎重に結論を下すという認知特性をもっている。そのため、先に笑顔表出の時期についての考察の中で述べたように、刺激VTRを作成する際の刺激人物の様子や感情といった、VTRの背景を推測しながら印象を形成した可能性がある。また、滝聞の研究が特性語を用いた印象形成研究であったのに対し、本研究がVTRを用いた印象形成であり、印象形成の手がかりの要因が複雑である、ということも理由として挙げられるだろう。認知的衝動性については、新しい解釈を試みるような研究が必要であるかもしれない。今後、様々な場面設定のもとで認知的熟慮性-衝動性と順序効果の関係を検討していく必要があると考える。
日常場面として初対面の女性が友人をつくることを目的として自己紹介をするとき、相手の認知的熟慮性が高い場合においては、終期に笑顔を表出した場合の方が、初期に笑顔を表出した場合よりも相手によりポジティブな印象を抱かれ、また、より強い好意を抱かれる、と言える。一方、相手の認知的衝動性が高い場合には、初期に笑顔を表出した場合と終期に笑顔を表出した場合とで、印象についても好意についても有意な差はないことが示された。
4)問題点及び今後の課題
本研究は、女性に対する印象形成に限定したものであったが、男性に対する印象形成では異なる結果が得られるかもしれない。よって、今後男性に対する同様な研究を行い、結果を検討することが望ましい。
また、方法として講義時間中に実験を行った被験者と講義時間外において実験を行った被験者の両者が存在する。講義時間中に行った実験でのVTRの聴衆は講義時間外に行った実験でのVTRの聴衆に比べて圧倒的に人数が多かった。このことは、条件の統制という点で問題であったと考える。可能であれば、すべて講義時間中または講義時間外で実験を行うべきであった。
今回、刺激人物と被験者が直接対面する状況ではなく、VTRを通して間接的に刺激を提示するものであった。このことにより、実際に人と人が直接対面した場合に生ずる交互作用や緊張感などが欠落してしまい、印象形成過程に影響を及ぼした可能性がある。条件統制が可能であるならば、刺激人物と被験者が直接対面する場面を設定することが望ましい。
VTRの提示方法について、同じ人物のVTRを2度提示した。被験者は、1度目のVTRと2度目のVTRでは何らかの違いがあり、印象は何らかの変化をしていることが望ましいのだろう、と実験者の意図を推測している可能性がある。被験者がこのように推測していた場合、特に笑顔統制条件を2度見た被験者において2回目のVTRに対する印象評定に影響を及ぼした可能性がある。また、認知的熟慮性-衝動性についての考察の中でも述べたが、被験者が2つ目のVTRについての印象形成を行なう過程で、1つ目のVTRについて形成された印象が初頭効果となって影響を及ぼしている可能性もあるだろう。
また、最終的に1人の刺激人物に対する実験データのみを用いて行ったため、印象形成の対象となる人物の個人差を検討することができなかった。刺激人物の個人差によって結果が異なることも十分考えられるので、今後検討する必要がある。
尚、本研究は、女性に対する初期印象の形成過程において笑顔の順序が実際にどのような影響を及ぼしているのかを検討したものであり、そこにどのようなメカニズムが作用しているのか、といったことについて検討するまでには至っていない。このような問題は今後の課題となるだろう。