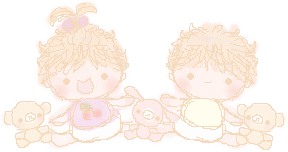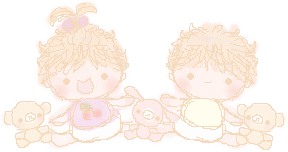本研究において明らかとなったことは、次の3点である
移行対象の発現には男女差があること、
落ち着かせ、慰めるもの(sooner)として移行対象の機能について多くの母親が、
漠然としてではあるが、理解していること、
我が子がが移行対象を所有していない母親よりも所有している母親の方が、
移行対象をポジティブに捉えているということである。
移行対象の発現には男女差があることに関しては、日本特異な社会文化的状況、例えば、女児の方が愛着物を与えられやすい、女児と男児に与えられるおもちゃに違いある、といったことなどに留意して、さらに詳しく検討していく必要があるだろう。
また、慰めるもの(sooner)としての機能について多くの母親が理解しているが、子どもが移行対象を所有していない母親は、移行対象の発達的意味に関して偏見的な見方をしていることが示唆され、移行対象に関しての知識を広めることの重要性が見出されたことに関しては、特に子どもが移行対象を所有していない母親に対し、移行対象についての知識を持ってもらうことが必要であると考えられる。
その際、どのように移行対象に関しての知識を広めるのかを今後検討していかなければならない。
さらには、移行対象を所有する子どもはコミュニケーション能力に欠けるという点以外で、移行対象所有に対する認知にどのような偏りがあるのかを検討する必要があるだろう。
なお、本研究では近親者の移行対象に対する認知が母親の移行対象所有に対するイメージにどのように影響するのか、誰の影響が強いのかといったことに関して、はっきりとした結果を導き出すことができなかった。
しかし、影響がないとは言い難く、さらなる検討が必要となる。
| |