|
1 4下位尺度得点によるクラスタ分析
Gabbardの指摘によれは、自己愛人格はその多くが、先に挙げた2種類の自己愛人格を両極とした軸のどこかに位置づけられると考えられる。本研究で見出された「評価過敏」「誇大性」を自己愛人格の2下位分類に関連すると考えると、これらの得点の組み合わせによって自己愛人格は大きく2つのグループに分けられると考えられる。また、すべての人が自己愛的であるわけではないので、どの下位尺度についても低い得点をつける被験者群の存在や、自己愛的な誇大性・過敏性をもたないが、対人恐怖傾向の強い、真の不安群とも言える被験者群の存在も予測される。そこで、ここでは被験者を得点パターンによって分類することを目的として、研究1で見出された4下位尺度の項目平均値(z得点化したもの)を投入変数としたクラスタ分析を行った。
分析対象者が901人と多数であったため、非階層的クラスタ分析を行った。非階層的クラスタ分析とは、クラスタ数を指定した上で行うクラスタ分析のことである。本研究では、あらかじめ一部のデータを用いて階層的クラスタ分析(Ward法)を行い、その結果から3~7クラスタ解と仮定した上で非階層的クラスタ分析を行い、解釈のしやすさから5クラスタ解を採用するという手順をとった。クラスタごとの各下位尺度得点平均値はTable
11のとおりである。また、各クラスタの特徴をわかりやすくするため、z得点化した各下位尺度平均値を用いてグラフ化した(Figure
)。
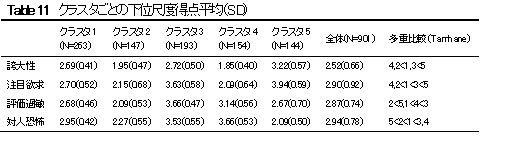
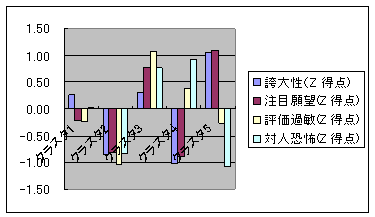
2 各クラスタ平均値の検討とクラスタの命名
4下位尺度得点のパターンから各下位尺度に命名を行った。
クラスタ1の平均値は、全ての下位尺度についてz=0に近い値を示していたため「平均群」とした(男141人,
女122人)。クラスタ2はすべての下位尺度において低い値を示しており、「自己愛低群」と命名した(男70人,
女77人)。クラスタ3は評価過敏性得点が最も高くなっていたため、「評価過敏群」とした(男69人,女122人,不明2人)。なお、この群は誇大性や注目欲求の得点も高めの値となっていた。クラスタ4は評価過敏性について全体平均より高い値を示したもののそれほど高い値ではなく、それよりも対人恐怖得点の高さを特徴とする群であると考えられた。また、この群は誇大性や注目欲求が低く、自己評価の高さや、その維持・顕示欲求をもたない群であると考えられる。これらのことから、「対人恐怖群」と命名した(男67人,女87人)。クラスタ5は誇大性や注目願望が明らかに他群よりも高く、「誇大群」とした(男72人,女70人,不明2人)。
「評価過敏群」、「誇大群」は自己愛の2下位分類のいずれかを強く持つグループであると考えられる。また、そもそも自己愛的ではない群(「自己愛低群」)や対人恐怖傾向のみ高い群(「対人恐怖群」)等、その存在が予測された被験者群を抽出することができた。そこで、これらの群を用いていくつかの分析を行った。
3 各クラスタの出現率の検討
青年期の自己愛傾向についてさらに理解を深めるため、中学・高校・大学生群における各クラスタの出現比率を比較検討した。
χ2検定を行った結果、分布の差が認められたため(χ2=24.589, p<.01)、Haberman法による残差分析を行った。調整済み残差(dij)の絶対値が1.96より大きい場合5%の有意水準で、2.575より大きい場合1%水準で、それぞれのセルについて「観測度数は期待度数に等しい」という帰無仮説を棄却できる(Everitt,
1977参照)。ゆえにdij>|1.96|、dij>|2.575|を基準にセルの検討を行った。中学生では、高校生・大学生に比して平均群が多く、対人恐怖群と誇大群が少なくなっていた。割合(%)を見ると、3分の1以上の被験者が平均群に分類されており、誇大性を特徴とする者や、高い対人恐怖心性を示す者が少ないことが伺えた。しかし、有意ではないが、評価過敏群に分類される被験者の割合は比較的多く、中学生期は評価にさらされる機会が増え、評価過敏になる人が多い時期であるということも示唆された。高校生では、自己愛低群が少なく、真の不安群・誇大群に分類される被験者が多いことがわかった。大学生では有意なセルは見られなかった。
各下位尺度得点の推移を見た結果、「誇大性」「注目願望」で最も高い得点を示したのは高校生であった(Table
8)。ここで再度高校生において誇大群に分類される被験者が多かったことは、全体的な傾向としてだけでなく、誇大性を特徴とする個人、すなわち誇大的で他者の評価を気にかけない者が多いということが理解できる。それに対し、高校生と同様に「誇大性」得点が高いとされた大学生被験者群において、誇大群に分類される被験者は高校生ほど多くなく、むしろ自己愛低群の方が目立っている。ここから、大学生においては、全体的に誇大性得点は高くなるが、個人のスタイルとして誇大性を特徴とする者は多くないということが示唆された。
4 自己愛傾向のパターンと精神的健康との関連
自己愛傾向のパターンと精神的健康の関連を見るため、各クラスタのGHQ得点を比較検討した。クラスタごとにGHQ全項目・各下位尺度の項目平均値を算出し、一要因分散分析を行った(Table
13)。多重比較の結果から、自己愛低群は全体として低い値を示しており、精神的健康度の高い群であることが示唆された。平均群、誇大群は自己愛低群とほとんど差がなく、同様のことが言える。得点が高く、精神的健康度の低さが伺われたのは、「対人恐怖群」と「評価過敏群」であった。特に心理的な健康度を測定する尺度であることがその内容から示唆される「不安・不眠」「うつ傾向」については、「対人恐怖群」「評価過敏群」に差が見られ、「評価過敏群」の方が有意に高くなっていた。
これらのことから、自己報告による精神的健康度を比較した場合、評価過敏性を特徴とする自己愛人格が最も健康度の低い人格であることがわかった。また、誇大性を示す自己愛人格は自己愛性の低い被験者と同様、精神的健康の高さを示していた。
|