丂帺屓堄幆偼丄僋儕僥傿僇儖僔儞僉儞僌巙岦惈偲庛偄惓偺憡娭偑傒傜傟偨偑丄巹揑帺屓堄幆偲斾妑揑嫮偄惓偺憡娭偑傒傜傟偨堦曽偱丄岞揑帺屓堄幆偲偺憡娭偼傒傜傟側偐偭偨丅偙傟偼丄乽僋儕僥傿僇儖僔儞僉儞僌巙岦惈偼丄岞揑帺屓堄幆偲惓偺憡娭傪傕偪丄巹揑帺屓堄幆偲晧偺憡娭傪傕偮偩傠偆乿偲偄偆壖愢嘥偲惓斀懳偺寢壥偱偁偭偨丅
丂偙傟偼丄僷僽儕僢僋側帺屓傪堄幆偡傞偙偲偑丄暔帠傪懡柺揑偵尒傛偆偲偡傞僋儕僥傿僇儖僔儞僉儞僌巙岦惈偵偼偮側偑傜側偄偲偄偆偙偲傪昞偟偰偄傞丅懠幰偺栚偐傜尒傞帺屓傪堄幆偡傞偙偲偼丄帠幚偱偼側偔偨偩偺憐憸偵夁偓側偄偙偲偐傜丄帠幚傗徹嫆傪廳帇偡傞僋儕僥傿僇儖僔儞僉儞僌巙岦惈偲偼憡斀偟丄岞揑帺屓堄幆偲僋儕僥傿僇儖僔儞僉儞僌巙岦惈偲偼憡娭偑弌側偐偭偨偺偱偁傠偆丅堦曽偱丄帺屓偺姶忣傗婅朷側偳偺巹揑側懁柺傪廳帇偡傞偙偲偑丄僋儕僥傿僇儖僔儞僉儞僌巙岦惈偵偮側偑傞偲偄偆寢壥偑弌偰偄傞偑丄偙傟偼晛抜壗婥側偔巚偆偙偲傗婅偆偙偲側偳丄巹揑側懁柺偵拲栚偡傞偙偲偱丄帺屓偵偮偄偰懡柺揑偵峫偊偰偄傞偙偲偵憡摉偟丄條乆側帠徾偵懳偡傞徣嶡擻椡偱偁傞僋儕僥傿僇儖僔儞僉儞僌巙岦惈偲惓偺憡娭偑傒傜傟傞偺偩偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅
丂偝傜偵丄偦傟偧傟偺壓埵広搙偵偮偄偰憡娭傪嶼弌偟偨偲偙傠丄巹揑帺屓堄幆偵偍偄偰丄嫮庛偺嵎偼偁傞傕偺偺丄僋儕僥傿僇儖僔儞僉儞僌巙岦惈偺壓埵広搙偺慡偰偲惓偺憡娭偑摼傜傟偨丅傑偨丄僋儕僥傿僇儖僔儞僉儞僌巙岦惈丒帺屓堄幆偺廳夞婣暘愅偺寢壥丄僋儕僥傿僇儖僔儞僉儞僌巙岦惈偺壓埵広搙偱偁傞媞娤惈偼丄巹揑帺屓堄幆偵庛偄惓偺塭嬁傪梌偊丄恖娫懡條惈棟夝傕拞掱搙偺惓偺塭嬁傪梌偊偰偄傞偙偲偑暘偐偭偨丅偙傟偼丄巹揑帺屓堄幆偵偼丄媞娤揑偵帺暘傪尒偮傔捈偡戝愗側梫慺偑娷傑傟偰偄傞偲尵偊傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅堦曽偱丄偄傠偄傠側恖娫偺懚嵼傪擣傔傞偙偲偼丄摨帪偵懡條側恖娫偺拞偵帺屓偺摿挜傪杽傔傞偙偲偑偱偒傞巚峫偺僗僞僀儖偱偁傞偲峫偊傜傟傞偙偲偐傜丄巹揑側懁柺偵偮偄偰怳傝曉傞偙偲偑偁偭偰傕丄乽懠偵傕傕偭偲偄傠偄傠側僞僀僾偺恖娫偑偄傞乿偲巚偆偙偲偱丄帺暘傪抪偠偨傝偡傞偙偲偑側偄偩傠偆丅偮傑傝丄寬峃揑側巚峫偺僗僞僀儖傪傕偭偰偄傞偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅僋儕僥傿僇儖僔儞僉儞僌巙岦惈広搙偺偆偪丄巹揑帺屓堄幆偲嵟傕嫮偄憡娭傪傕偭偰偄偨偺偑恖娫懡條惈棟夝偱偁傞偙偲偐傜丄恖娫偺懡條惈傪棟夝偡傞偙偲偑丄傕偭偲傕巹揑側懁柺偵栚傪岦偗丄撪柺傪廩幚偝偣傞梫場偱偁傞偲峫偊偰椙偄偩傠偆丅Scheier丆Buss,A.H., & Buss,D.M.乮1978乯偵傛傞偲丄巹揑帺屓堄幆偑崅偄恖偼丄帺屓昡壙偑傛傝惓妋偱偁傞偲偄偆偙偲傪帵偟偰偄傞丅傛偭偰丄僋儕僥傿僇儖僔儞僉儞僌巙岦惈偲巹揑帺屓堄幆偲偺娭楢偑偁偭偨偲偄偆偙偲偼丄僋儕僥傿僇儖僔儞僉儞僌巙岦惈偑惓妋側帺屓棟夝傪懀偡梫場偲偟偰桳椡偱偁傞偲峫偊偰椙偄偩傠偆丅
丂傑偨丄岞揑帺屓堄幆偵娭偟偰偼丄媞娤惈偲庛偄晧偺憡娭偑偁傝丄恖娫懡條惈棟夝偲偼庛偄惓偺憡娭偑偁偭偨丅偝傜偵丄廳夞婣暘愅偺寢壥丄岞揑帺屓堄幆偼媞娤惈偐傜拞掱搙偺晧偺塭嬁傪庴偗丄恖娫懡條惈棟夝偐傜拞掱搙偺惓偺塭嬁傪庴偗偰偄偨丅傛偭偰丄岞揑帺屓堄幆偲僋儕僥傿僇儖僔儞僉儞僌巙岦惈偲偺娫偵憡娭偑弌側偐偭偨偺偼丄媞娤惈偲恖娫懡條惈棟夝偺娫偵弌偨憡娭偑憡嶦偝傟偨傕偺偩偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅岞揑帺屓堄幆偼丄懠幰偺栚偐傜尒偨帺屓偺憸傪彑庤偵憐憸偡傞偙偲偱偁傞偑丄媞娤惈偲晧偺憡娭偑傒傜傟傞偙偲偐傜丄乽帺暘偑憐掕偟偨乿懠幰偺帇揰偐傜帺暘傪尒偰偄傞偲尵偆偙偲偑偱偒丄寢壥偲偟偰庡娤揑側帺屓憸偵棅偭偨憐憸偲偄偆偙偲偵側傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅偝傜偵丄恖娫懡條惈棟夝偲偺憡娭偑偁傞偙偲偐傜丄條乆側恖偑憐掕偟偨帺屓憸傪憐憸偡傞偙偲偵傛傝丄帺暘偺峴摦傪條乆側恖偺巚榝偵崌傢偣偰懆偊傛偆偲偡傞偙偲偱丄帺暘偺峴摦傪斀徣偡傞婡夛偼憹偊傞丅惵擭婜偼乽帺変摨堦惈乿乮傾僀僨儞僥傿僥傿乯偺宍惉偺帪婜偱偁傞偙偲偐傜丄乽帺暘傜偟偝乿傪堄幆偡傞偁傑傝丄帺暘傜偟偝偵斀偡傞峴摦偵晀姶偵側傞偁傑傝丄懡條側恖娫偑偄傞偙偲傪棟夝偟偮偮丄偦偺帇揰傪傪帺暘偵揔梡偡傞偨傔偵昁梫側媞娤惈偑掅偄偨傔丄偄偮傕偲堘偆帺暘偺峴摦傪昁梫埲忋偵婥偵偟偨傝丄傂偳偄応崌偵偼抪偠偰偟傑偆偺偱偼側偄偩傠偆偐丅傛偭偰丄岞揑帺屓堄幆偑崅偄恖偼丄懠幰偐傜尒偨懡條側帺屓憸傪婥偵偡傞偑丄帺屓傪傕媞娤揑偵尒傞帇揰傪帩偨側偄偨傔丄帺屓偵懳偡傞抪偺姶忣偑戝偒偔側傞壜擻惈偑偁傝丄乽帺暘偑曄側恖偵巚傢傟偰偄傞偐傕偟傟側偄乿偲偄偭偨懳恖晄埨堄幆偑崅偔側傞偙偲偑悇應偝傟傞丅
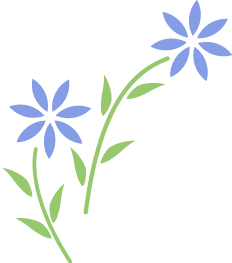
|
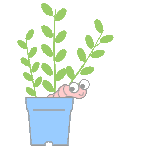
![]()