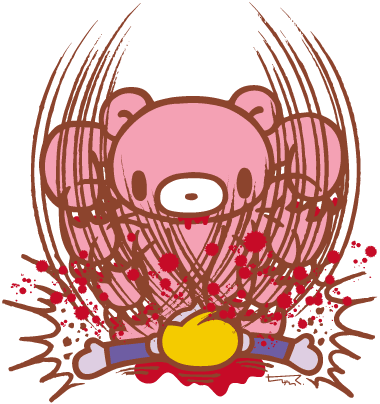1.はじめに
人間の攻撃行動は、従来、比較行動学者などによってしばしば動物の攻撃と比較され、その残忍さ、無制限さ等が指摘されている。事実、我々が歴史書をひもとく時、人間の歴史とは戦争の歴史であったのかと感じさせられるほどである(滝村,1991)。大渕(2000)も我々は暴力を憎み、その根絶を強く望んでいるにもかかわらず、暴力は依然として我々のすぐ身近にあり、またその萌芽は、我々自身の内部に確かに存在すると述べている。そしていつしか、我々人間にとって「攻撃行動」は、何かしら統制不可能な、衝動的なものであるように考えられるようになった。しかし、近年の諸研究の蓄積によって、攻撃行動は、後天的に形成され、社会的要因によって制御されるものであるという考え方が優勢になってきた(滝村,1991)。
攻撃の定義には様々な見解があり、攻撃をどの様に定義するのかについては、現在でも議論が絶えないようである。本稿では、何をどこまで攻撃と考えれば、最も攻撃という概念を捉え易いかを考慮した上で、以下の大渕(2000)の定義を用いることとする。
それでは攻撃を制御する社会的要因として考えられ得るのは何であろうか。先行研究では、その直接的な抑制要因として向社会性を取り上げたものや(藤田・眞田,2000)、社会的スキルを取り上げたものなどがある(安藤・吉村,2002)。だが、攻撃とはもともと様々な要因が複雑に絡みあって生起するものであり、どのような状態においても効果のある、いわば万能薬のような抑制要因は見つかっていない。そもそも「攻撃」とは何なのか。そして、どのように生起するものなのか。制御する要因を考えていく上では、まずそのあたりの現在における見解からみていく必要があるだろう。
"攻撃とは「他者に危害を加えようとする意図的行動」である。"
この定義の第一の要素は「危害」である。これには身体的苦痛や損傷だけでなく、多様な心理的苦痛や不快が含まれている。第二の要素は「意図」である。うっかり人にぶつかっても、攻撃とはみなされない。それは、故意に危害を加えようとしたものではないからである。反対のケースは、拳銃を撃ったが当たらなかった場合で、危害は生じていないが、このケースは攻撃とみなされる。未遂であっても、人に危害を加えようとする意図が認められる限り、攻撃である(大渕,2000)。
また大渕(2000)は、「攻撃」と「攻撃性」を次のように使い分けている。「攻撃」とは意図的危害行為で、観察可能な行動反応のことである。一方、「攻撃性」とは、そうした行動や反応が生み出される内的な心理過程を指して用いる。例えば、攻撃的な思考や関心、攻撃的な感情、攻撃への意欲や願望などである。また攻撃的な思考や感情を発生させやすい性格特性も、攻撃性の一部であるとしている。

3.攻撃性の三つのパースペクティブ
現時点で統一的な見解は得られていないが、攻撃性の本質についてさまざまな立場の共通点と相違点を整理すると、以下の三つの理論的グループに分けることが可能であると大渕(1993)は述べている。その三つのパースペクティブとは、内的衝動説、情動発散説、社会的機能説である。
前節でも述べたようにすべての葛藤において攻撃が行われるわけではない。攻撃が選択されやすい葛藤タイプというものが存在する。攻撃が適するか適さないかは攻撃の機能に依存する。大渕(1989)はその社会的機能を、防衛・回避、強制、制裁・報復、印象操作の四つに分類している。この中で私が特に注目したいと考えているのが、制裁・報復としての攻撃である。大渕(1993)は怒りの経験調査によって、人々の怒りの80%は他者の不正に向けられていることを明らかにしており、この機能には人間の怒りと攻撃の本質的な特徴が暗示されていると述べている。
しかし、合理性の判断に関し、それを決定するための上記三要因の判断は、常に外的事実のみに依存して行われるわけではない。理由の正当性の判断には被害者の道徳的価値観が影響するであろうし、制御能力と意図性の有無の判断は、それぞれが対人認知の一要素と言える。特に相手がどう思っているのかという他者の心の推測である意図性の有無の判断には、被害者の認知スタイルが影響しやすいと考えられている(後藤・倉戸,1997)。例えば滝村(1991)によれば、ドッヂ(1980,1981)は、挑発者の意図が曖昧であるような欲求不満事態への反応において、攻撃的でない少年は、挑発者が親切な意図を持って行動したと判断するのに対し、攻撃的少年は挑発者が敵意的意図で行動したと判断し、攻撃的にふるまいがちであることを発見している。
攻撃的少年のパラノイド傾向が、そもそも、いつ、どのようにして生じたのか、詳しいことはまだ解明されていない。パラノイド性格者の基本的特徴は他者に対する不信感であるという。この点について幼児期の「基本的安全感の欠如」がその一要因ではないかという指摘もある。ホーネィ(1937)は、この感情を「敵意に満ちた世界に、頼るものもなく、無防備に放り出されている」心情と描写している(大渕,1993)。こうした他者への不信感を緩和するためには周囲からの温かいサポートが有効に働くのではないだろうか。ソーシャルサポートは、他者からの社会的支援に関する認知であり、メンタルヘルスに果たす役割が大きいことなどから近年、社会心理学、発達心理学など様々な分野で注目されてきている。Cobb(1976)によれば、ソーシャルサポートとは、「社会的ネットワークにおける他者から愛され、尊敬され、価値あるものとみなされ、コミュニケーションのネットワークの一員であると信じさせてくれる"情報"」であると定義されている(渡辺,1995)。周りからのこうした強力なソーシャルサポートがあれば、パラノイド傾向の生起の一要因と言われている「基本的安全感の欠如」が緩和され、「パラノイドの悪循環」は弱められるだろうし、そもそもパラノイド傾向の生起を抑制することができるのではないだろうか。また、ソーシャルサポートと一口に言っても、細かくわけると実に多様な種類が考えられ、その数も呼び名も統一的な見解は得られていない。しかし、大まかには情緒的サポートと道具的サポートに分類できるようである。もっと具体的に言えば、道具的サポートには、ストレス処理のための資源を提供したり、問題解決に介入するという形での直接的なサポートと、それらについての情報を提供するという形での間接的なサポートの二種類あることが、そして情緒的サポートには、愛情や愛着、親密性のような情緒的な側面への働きかけと、評価やフィードバックなどのような認知的な側面への働きかけの二種類があることが多くの研究から示唆されている(浦,1992)。こうした、サポートの種類の違いによってもパラノイド傾向への影響は違ってくるのではないかと考えられる。本研究ではそれらの違いにも注目していきたい。
今までの研究においても、攻撃に直接働きかける抑制要因を研究するものは数多くなされてきた。しかし、攻撃性が行動として生起するまでの対人認知過程を考慮にいれた研究はあまりなされていない。本研究ではパラノイド傾向と攻撃性の関係に注目し、ソーシャルサポートがそれらに及ぼす影響についてみていくことを目的とする。
内的衝動説・・・・この立場では、攻撃を起こす心理的エネルギーが個体内にある、つまり、攻撃的な欲望が内側から自然に湧いてくると仮定する。この衝動の特徴は、他者に苦しみを与えることに快を感じ、また、破壊そのものに満足感を覚えるサディスティックな欲望である。この立場の代表的人物にフロイト(1933)やエソロジストのローレンツ(1963)がいる。
情動発散説・・・・この立場では攻撃を不快な感情の表現あるいは発散とみなす。この思想の代表は、ダラードたち(1939)の欲求不満説である。近年は、バーコビッツ(1989)らがより洗練された理論を展開しており、彼の理論は認知的新連合理論と呼ばれている。この立場では、不快な経験をすることが攻撃の原因であり、その最終的な目標は、不快経験によって生じた不快な感情を外部に発散することであり、その意義は、欲求不満を攻撃行動によって解決することではない。
社会的機能説・・・・この立場では攻撃の手段的機能を強調する。一つのグループはバンデューラ(1973)などの社会的学習理論家である。攻撃行動の生起を左右するのは内的衝動ではなく外的事象であり、事象と行動の関係は経験によって形成されるというのが彼らの基本的な姿勢である。特に結果の影響は重要で、何が目標であれ、攻撃反応が有効だという経験をすると、類似の状況では攻撃を喚起しやすくなる。
そして、もう一つのグループはルール(ファーガソン&ルール,1983)やテダスキー(1983)などの認知志向の社会心理学者たちである。彼らは、自己と他者に対する人々の認知や判断過程、人間関係を規制する暗黙の社会規範などを重視し、葛藤場面での人々の心理過程と反応制御を分析している。この立場では、攻撃行動は葛藤場面に対する人々の対処行動の一つとして位置付けられている。
大渕(2000)は特にこの最後の立場である認知志向的な立場に立って研究を行っている。葛藤を解決するためには、譲歩、説得、哀願など多くの方略が可能なのに、なぜ、ある条件下で、ある人々は攻撃という危険な手段を選択するのか。多くの研究者達がこれに答えるため、攻撃を採用するに至る行為者の意思決定過程を分析しようと今日まで苦心してきた。本研究でも対人関係、特にその葛藤場面における攻撃性の生起の過程、そしてそれを制御する社会的要因を研究したいと考え、大渕に倣いこの社会的機能説の認知志向的な見方に焦点を当てることにした。
大渕(1993)によれば、テダスキーやアベリルなどの攻撃理論家は、怒りを他者の不当な行動に対する告発感情だとみなしており、他者の規範逸脱を知覚することが怒りの感情を喚起し、自分が直接被害を受けても受けていなくても、不正を知覚すると怒りが生じ、その怒りは、不正行為を矯正し、社会的公正を回復すること、逸脱された規範の価値を再確認することなどを目指して、攻撃行動を動機づけると述べている。また、ファーガソンとルール(1983)によれば、規範逸脱とは「こうあるべき」と人々が信じているものと現実とのずれであると定義されている。さらにミクラたち(1990)はいくつかの文化圏の人々に不快事象をあげさせ、それを基に三種類の公正を区別した。それは以下の分配的公正、手続き的公正、それに相互作用的公正である。
分配的公正・・・・・利益や負担の不公平な配分、偏った裁判結果、業績や努力の評価におけるひいき、など。
手続き的公正・・・・規則が合理的でない、根拠のない権威、試験の内容や評価の仕方が不適切、など。
相互作用的公正・・・人の感情に対する配慮がない、人を軽視したり批判する、自己中心的、敵意・悪意を向けられる、など。(大渕,2000)
中でも最も多くあげられた不快事象は、最後の相互作用的公正の違反であったという
そして、これら制裁・報復としての攻撃を規定する最も重要な認知過程は責任判断である。責任の認定に関しては多くの理論的分析が行われてきたが(ハイダー,1958:シェーバー,1985)、現在最も広く受け入れられているのは責任帰属の三次元説である(大渕,1993)。アベリル(1983)などの研究者たちは「意図性(intentionality)」、「動機の正当性(justifiability of motives)」、「制御能力(controllability)」から成る三次元階層モデルを提唱した。被害者は原因帰属の認知過程において、まず最初に加害者に悪意があったかどうかを判断し、そしてその上で道徳的にその動機が正当かどうかということと、その事態を回避できる能力が相手にあったかどうかを判断することで、加害者の提供する原因情報の合理性を判断すると考えられている。ここで、その原因が合理的と判断されれば、攻撃反応は生起しにくく、不合理と判断されれば攻撃反応が生起しやすくなるわけである。
ドッヂの研究は、攻撃行動とそれに影響を与えると思われる帰属の偏りの個人差との関連を探ったものであるが、滝村(1991)はこの研究から、2つの結論を導き出している。第1に、他者の敵意的意図を知覚し易いという帰属の偏りには個人差があるということ。第2に、このような偏りを持つ人は、攻撃反応を行い易いということ。特に第2の認知的偏りと攻撃行動の関連性は注目されるべきものであると滝村(1991)は述べている。
繰り返しになるが、人々の中には、他者の言動に悪意を推測し易い人とそうでない人がいる。特に、攻撃的な人々は、非攻撃的な人々に比べ、他者の行動をより悪意的なものとして知覚する傾向が強いようである。他者の悪意を知覚し易いというこうした傾向を滝村(1991)は「パラノイド傾向」と呼んでいる。
以上のように、先行研究からも攻撃性とパラノイド傾向の間には強い正の相関関係があると考えられる。大渕(1993)も、パラノイド傾向の強い者に逸脱行動の危険性があることを示唆している。実際滝村(1991)はパラノイド傾向と少年非行の関係性を検討しており、男女とも一般の高校生に比べて、少年院入所者には高いパラノイド傾向がみられることを発見している。それならば、このように攻撃性と関係の深いパラノイド傾向を低減させることができれば、パラノイド傾向を介して間接的ではあるが攻撃性をも低減させることができるのではないだろうか。
ところで、後藤と倉戸(1997)によれば、さらにドッヂとフレイム(1982)は、攻撃的少年は、他の少年たちから攻撃を受けるよりもむしろ自分の方から攻撃を仕掛けていくことが多いことを発見している。そしてこれらの研究より、ドッヂとフレイムは、攻撃的少年が「自分は他者から敵意を向けられやすい」という認知スタイル、つまりパラノイド認知を持っている可能性と、他者から敵意を向けられる事実が少年の攻撃行動に起因していることに着目し、彼らは攻撃的少年のパラノイド認知過程について次のようなモデルを仮定した。
即ち、パラノイド性格者の認知スタイルは、意図性の曖昧な状況において他者の意図を敵意的に解釈させ、少年の攻撃反応を喚起する。それに対し他者が報復的に反応することで少年は自分の予期が真実であったと思い、さらに認知スタイルを強化する。つまりこのパラノイド認知スタイルは、敵対的な対人関係を繰り返すことで徐々に助長される悪循環的なものである(後藤,1997)。
では、この「パラノイドの悪循環」を弱め、最終的には断ち切れるような何らかの外部からの働きかけがあればパラノイド傾向は抑制されるのではないだろうか。その社会的要因として本研究ではソーシャルサポートに注目したいと考える。
また、前述したようにソーシャルサポートにもいくつかの種類があり、パラノイド傾向など人に対する不信感や猜疑心などを低減させる上では、直接情緒的な安定を導くサポートである情緒的サポートが特に有効であり、道具的サポートよりもパラノイド傾向に及ぼす影響は強いと考えられる。このようにソーシャルサポートの種類によっても差がみられると予想されるので、サポートの種別にも検討を試みることにする。
ところで、日本の文化では、特に男性において自立が美徳と考えられている傾向が未だ根強く、先行研究でもソーシャルサポートは男性より女性の方が高いとされている(渡辺,1995)。また滝村(1991)はパラノイド尺度を作成したが、このパラノイド得点には性差があり女性よりも男性の方が高いことが明らかになっている。さらに男性ホルモンやジェンダーステレオタイプなどの影響から今までの先行研究(大渕,2000)では一般的に攻撃性は女性より男性の方が高いということが言われている。以上のように、ソーシャルサポート、パラノイド傾向、攻撃性にはそれぞれ性差がみられることが予想されるので、本研究においてはそれらの性差の確認を行い、男女別でも検討を試みることとする。
本研究の目的は以下の通りである。
第一の目的
ソーシャルサポートとパラノイド傾向の間には、ソーシャルサポートが高ければパラノイド傾向が低くなるという負の関連があるかどうかを明らかにする。
第二の目的
ソーシャルサポートの下位尺度にも注目し、ソーシャルサポートの種類ごとにパラノイド傾向に及ぼす影響に違いがあるのかどうかを明らかにする。
第三の目的
パラノイド傾向と攻撃性の間には、パラノイド傾向が高いと攻撃性も高くなるという正の関連があるかどうかを明らかにする。
第四の目的
ソーシャルサポートと攻撃性の間に、直接的な関連があるのかどうかを明らかにする。
第五の目的
ソーシャルサポート、パラノイド傾向、攻撃性のそれぞれの尺度における性差を確認する。

仮説
1.ソーシャルサポートには、パラノイド傾向の生起の一要因と言われている「基本的安全感の欠如」を緩和する効果があると考えられるので、ソーシャルサポートとパラノイド傾向との間には、ソーシャルサポートが高ければ、パラノイド傾向が低くなるという負の関連があるだろう。
2.パラノイド傾向など人に対する不信感や猜疑心などを低減させる上では、直接情緒的な安定を導くサポートである情緒的サポートが特に有効であると考えられるので、情緒的サポートの方が道具的サポートよりもパラノイド傾向に及ぼす影響は強いであろう。
3.先行研究(ドッヂ,1980,1981など)でも言われているように他者の悪意を知覚し易い傾向は、人を攻撃的な衝動へ駆り立て易くなると考えられるので、パラノイド傾向と攻撃性との間には、パラノイド傾向が高ければ、攻撃性も高くなるという正の関連があるだろう。
4.ソーシャルサポートの効果はパラノイド傾向を介して、間接的に攻撃性に働くと考えられるので、ソーシャルサポートと攻撃性の間には、直接的な関連はみられないだろう。
5.日本の文化では、特に男性において自立が美徳と考えられている傾向が未だ根強く、先行研究でもソーシャルサポートは男性より女性の方が高いとされている(渡辺,1995)。よって、本研究でもソーシャルサポートは男性より女性の方が高くなるだろう。
また滝村(1991)はパラノイド尺度を作成したが、このパラノイド得点には性差があり女性よりも男性の方が高いことも明らかにしている。さらに男性ホルモンやジェンダーステレオタイプなどの影響から今までの先行研究(大渕,2000)では一般的に攻撃性は女性より男性の方が高いと言われている。よって本研究においてもパラノイド傾向と攻撃性は女性より男性の方が高くなるだろう。