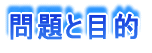
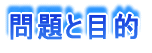
1.箱庭療法の歴史
箱庭療法(Sandplay therapy)は、カルフ(Kalff,D,M.;1904−1990)がメラニ−・クライン(Klein,M.;1882−1960)の弟子だったローウェンフェルト(Lowenfeld,M.;1890−1973)の「世界技法」(The World Technique)をもとに、ユング(Jung.C,G.;1875−1961)の分析心理学の考え方を加味して発達させたものであり、1965年に河合隼雄(1928−)によって日本に紹介された。
河合隼雄(1969)は、「箱庭療法の特徴を遊戯療法と絵画療法の中間にあるものとして把握することができる。」と述べている。空間が箱という形で限られていることで、クライエントは、保護された空間の中で安心することができる。そして、与えられた多種多様な玩具を使うことで、自由に自己を表現することが可能である。このようにすることによって箱庭療法は、クライエントの自己治癒力を引き出すことができるのである。また、箱庭療法において箱庭は、治癒者とクライエントとの間に媒介として存在する。対面法という治癒者とクライエントの2者の関係から、箱庭が入ることによって三者関係になる。岡田(1984)は、箱庭が治癒者とクライエントの関係の潤滑油になると述べている。3者関係になったことで、それぞれが相互作用し、クライエントの自己治癒力を高め、治癒に向かっていくのである。
河合(1982)は、箱庭療法は日本人に適していると述べている。非言語的な自己表現が日本人に向いているのだろう。現在、日本では箱庭療法が広まり、言葉で上手く表現することができない児童から大人に至る幅広い年代に適用され、効果をあげている。
光元(2001)は、箱庭療法は心理療法の場面で用いられ、言葉という象徴ではまだうまくとらえられないでいる自分自身の全体性、もしくは自分が他者や世界と関わっている姿の全体を、箱・砂・パーツといった言葉以外の象徴表現でとらえようとする試みであるとし、箱庭を用いた表現を広く〈箱庭表現〉と呼び、心理療法の場で箱庭表現がなされる場合を〈箱庭療法〉と呼ぶとしている。
2.先行研究の流れ
箱庭に関する研究の報告がたくさんなされているが、その多くは、問題を抱えた児童や成人に対して定期的に箱庭を用い、問題が解消あるいは軽減されたという、箱庭を心理療法として用いた報告である。日常生活に問題なく適応できている人に対して箱庭を行っている例も見受けられるが、その目的は精神発達遅滞の人との比較対象であったり(岩堂・奈比川;1970)、幼児、小学生、中学生、高校生、大学生などの年齢による比較であったり(岡田;1981)と、何かに対する比較対象としての統制群的な役割を重視する、箱庭療法の基礎研究である。また、日常生活に問題なく適応できている人に対してのみ箱庭を行っている場合でも、箱庭の砂に触れたり、ミニチュアを置いてみたりすることに関する研究(秋山;1999)や、大学生の箱庭の解釈に関する研究(佐藤;1989)がある。これらは数回の箱庭で完結している。具体的には、佐藤による大学生の箱庭の解釈に関する研究は、大学生が箱庭を1度行い、その箱庭を作者自身が自己分析することによって、自己理解が高まるということが考えられるとされ、佐藤は論文の最後に、「自己理解を深めるために箱庭を作らせ、自己分析をさせることは、条件さえ揃えば自己理解に有効な方法と思われる。」と述べている。これは、大学生という日常生活に問題なく適応できている人に対して箱庭を行ったもので、しかもたった1度の箱庭での自己分析による効果が期待される。このように先行研究では、問題を抱えた人に対して行う箱庭療法としての効果はもちろん、日常生活に適応できている人に対して行う1度きりの箱庭表現の効果も立証されている。これらの研究成果から、日常生活に適応できている人に対して行う箱庭表現においても、定期的に行うことによってさらなる効果が期待できるのではないだろうかと考えられる。本研究では、日常適応児*が定期的に箱庭表現を行うよって、何らかの変化が起こりうるのではないだろうかと考え、そこから日常適応児に対して定期的に行う箱庭の意味を見出していきたいと考えている。
3.日常適応児に対して行う箱庭の有効性を高める要因
箱庭療法の治癒力に関して小野(2002)は、箱庭制作は、自我の関与度が高いため、意識的な作品を作ることも可能であるが、クライエントの態度が無意識に対して開かれたものでなければ、十分な治癒力を発揮することはできないと述べている。意識的な作品を作るのではなく、無意識的な部分を表現した作品を作ることは、箱庭を表現として用いた場合の効果においても多大な影響を及ぼすと考えられる。無意識のうちに感じていることなどを箱庭という形で表現し、目に見える状態にしたことによって、何かを感じ、気づくという意識化の過程を経て、これまでの状態からの変化が期待されると考えている。
箱庭の制作において意識的か無意識的かを決める要因は、箱庭を行う際に関わる人との関係が大きく影響してくると考える。基本となるのは、箱庭を作る側と見守る側との関係が信頼で結ばれていることである。そうでなければ、作る側は安心して表現をすることができないだろう。このように考えると、箱庭療法は、1人で行うのでは全く意味がないものである。つまり、本来の箱庭療法の効力を発揮するためには、箱庭を作る側が安心し、見守られているという感覚を抱かなくてはならない。安心して自己を表現できる場であるということが、たとえ無意識的にであっても実感することができなければ、良い影響は期待できないどころか、箱庭制作を継続していくことさえ難しくなってくるだろう。小野(2002)は、治癒者によってクライエントがどれだけ受容され、どれだけ理解され、どういう関係が作り出せるかによって、箱庭は変化すると述べている。これは箱庭表現に対しても同じことが言えると考える。変化を及ぼす要因として、箱庭制作者が得る箱庭表現からの影響、箱庭制作を見守る側の姿勢、箱庭制作者に対する理解の度合いなどが挙げられる。
大人に比べて感情表現が豊かな子どもにとって、箱庭は自己を表現できる場としてより親しみやすいのではないだろうか。子どもは箱庭表現をする過程で、無意識的に感じていることを箱庭という場で表現し、出来上がった箱庭から様々なことに気づき、また、見守られているという安心感を実際に体感することができる。このことによって、その人自身の今後の生活おいて、何かしら良い影響を与えることができるのではないだろうかと考える。
以上のことから、箱庭には、箱庭療法として用いたときの有効性の他にも、箱庭表現として用いたときの有効性も見出すことができるのではないだろうかと推測する。
本研究では、学校や家庭などをはじめとする日常生活に問題なく適応し、一般的に見て健常であると言うことができる児童に対して、定期的に箱庭表現を行うことの有効性を検討していきたい。具体的には、定期的に箱庭表現をすることによって変化していく箱庭の過程や見守る側との人間関係を観察することで、箱庭表現を定期的に行うことの意味を明確化することである。さらに、箱庭表現が児童の日常生活やその児童自身の性格などに何かしらの影響を与えうる可能性を見出すことができるのではないだろうかと推測する。
