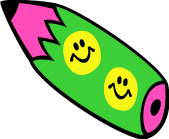
問題・目的
1.はじめに
2.自己複雑性
3.反すう傾向
4.精神的健康
5.本研究の目的
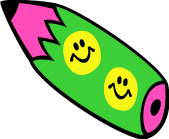
問題・目的
1.はじめに
2.自己複雑性
3.反すう傾向
4.精神的健康
5.本研究の目的
|
私たちは日常の中で様々なストレスや、気持ちが落ち込んで嫌になるような否定的な出来事を経験することがある。それによって、一日中気分が落ち込んでいることも、ひどく傷ついて何もしたくなくなることもある。しかし、そのような否定的な出来事の経験が、すべての人に不適応的な状態をもたらすわけではない。否定的な出来事を経験するなかで、困難な状況に一時的には陥っても、困難に向き合い、その経験を成長の糧として捉えることができる人もいる。このように、日常生活での様々な出来事が情緒反応に及ぼす影響には個人差があるのではないだろうか。 |
|
|
|
精神的健康を測定する概念として、抑うつと主観的幸福感を扱う。先行研究においても抑うつとの関連が多く検討されている。本研究では、一般学生における軽度の抑うつ状態に焦点を絞る。ストレスが社会問題となっている現在においては、大学生であれ日常において否定的な出来事を経験して、落ち込み何もしたくなくなることがある。そのような状態が長い間続き、軽度の抑うつ状態に至ることは誰にでも経験しうることだからである。主観的幸福感とは、感情状態を含み、家族・仕事などの特定の領域に対する満足や人生全般に対する満足を含む広範な概念である(Dinner, Suh, Lucas, & Smith, 1999)。近年、社会指標のような客観的指標だけでなく、個人の主観的判断や心理的側面を重視する必要が叫ばれ、主観的幸福感が問題とされるようになっている(石井, 1997)。本研究においても、従来の精神的不健康の指標である抑うつの測定だけでなく、より積極的な精神的健康の指標である主観的幸福感を扱うことで、自己複雑性が精神的健康に及ぼす影響をより深く検討できると考える。 |
|
本研究ではLinville(1985, 1987)の自己複雑性モデルを基に新たに「膜」モデルを提案し、自己複雑性の側面間の「膜」は思考や感情の活性化拡散を選択的に促進・抑制する2つの働きをすると捉える。そして本研究の目的は、肯定的自己複雑性と否定的自己複雑性、及び反すう傾向が精神的健康に及ぼす影響を検討することである。 仮説を以下に示す。 1. 反すう傾向が高い場合、反すう傾向が低い場合よりも抑うつは高く、肯定的自己複雑性が低いほどその差は大きいであろう。 2. 反すう傾向が高いほど抑うつが高く、さらに否定的自己複雑性が高い方が低い方よりも抑うつが高いであろう。 3. 反すう傾向が低い場合、反すう傾向が高い場合よりも主観的幸福感は高く、肯定的自己複雑性が低いほどその差は大きいであろう。 4. 反すう傾向が高いほど主観的幸福感が低く、さらに否定的自己複雑性が高い方が低い方よりも主観的幸福感が低いであろう。 |