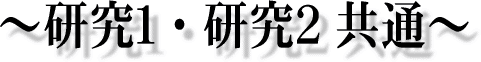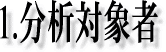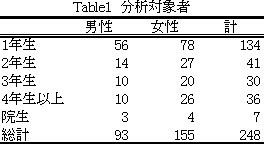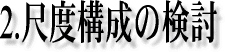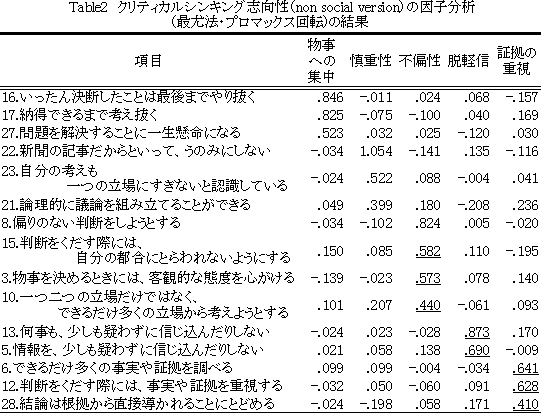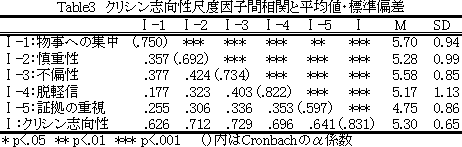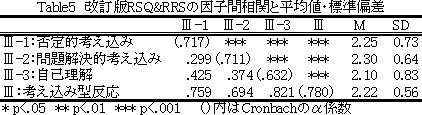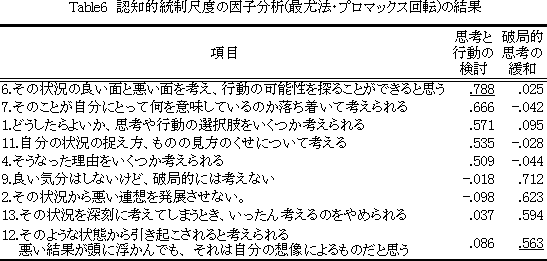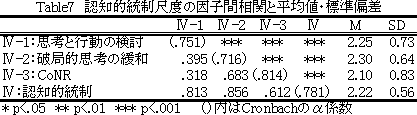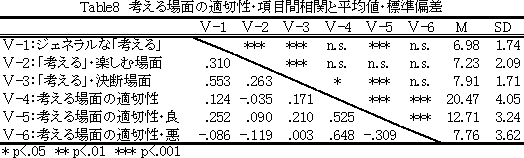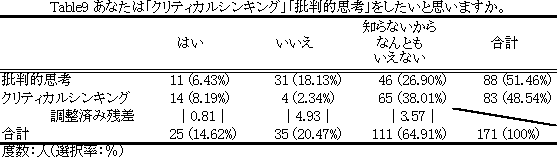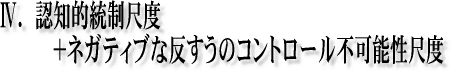|
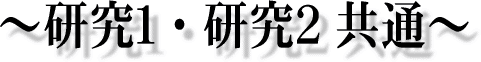 |
|
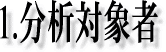 |
調査対象者の合計は263名のうち、欠損があった14名と、63歳の女性1名を除いた248名(男性93名,女性155名,平均年齢19.84歳,SD1.68)を分析対象とした。(Table1)
|
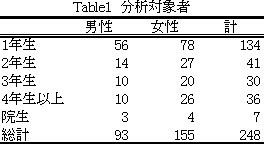
|
| ページトップへ |
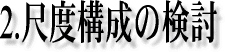 |
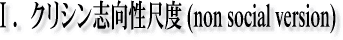
クリシン志向性尺度のうち、天井効果が生じていた3項目を除く26項目について、最尤法・プロマックス回転による因子分析を行った。複数の因子に|.35|以上の負荷を示した項目及び、どの因子にも|.35|以上の負荷を示さなかった項目を削除し、再度最尤法・プロマックス回転による因子分析を行うという手順をくり返した結果、最終的に5因子が抽出された。(Table2)
|
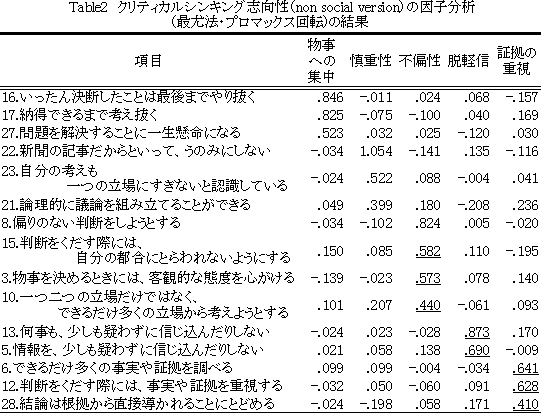
|
第1因子は「16.いったん決断したことは最後までやり抜く」「17.納得できるまで考え抜く」といった項目に高い負荷を示したため、「物事への集中」因子と解釈した。第2因子は、「22.新聞の記事だからといって、うのみにしない」「23.自分の考えも一つの立場にすぎないと認識している」といった項目に高い負荷を示したため、「慎重性」因子と解釈した。第3因子は、「8.偏りのない判断をしようとする」「15.判断をくだす際には、自分の都合にとらわれないようにする」といった項目に高い負荷を示したため、「不偏性」因子と解釈した。第4因子は、「13.何事も、少しも疑わずに信じ込んだりしない」「5.情報を、少しも疑わずに信じ込んだりしない」の2項目に高い負荷を示したため、「脱軽信」因子と解釈した。第5因子は、「6.できるだけ多くの事実や証拠を調べる」「12.判断をくだす際には、事実や証拠を重視する」といった項目に高い負荷を示したため、「証拠の重視」因子と解釈した。
「不偏性」「脱軽信」「証拠の重視」は、先行研究と同じ項目に高い負荷を示しており、先行研究と同一の因子であると考えられる。しかしながら、先行研究で見られた「探求心」「決断力」という因子は本調査では抽出されず、その代わりに「物事への集中」「慎重性」という因子が抽出された。
各因子のα係数は、「物事への集中」は.750、「慎重性」は.692、「不偏性」は.734、「脱軽信」は.822、「証拠の重視」は.597であった。「慎重性」と「証拠の重視」の内的一貫性については問題が残るが、その他の因子について、内的一貫性は問題なかった。また、クリシン志向性尺度全体のα係数は.831であり、内的一貫性は高かった。(Table3)
各因子間の相関は、「物事への集中」と「脱軽信」の間のみ.155と相関がなかったが、それ以外の項目においては.269〜.481の因子間相関を示していた(Table3)。これより、クリシン志向性の下位因子は相互に独立した次元ではなく、「一般的なクリティカルシンキングに対する志向性次元」が存在し、その下位次元として各因子が位置付くと考えられ、廣岡・小川・元吉(2000)の結果と整合する。
各因子に負荷の高かった項目から合成得点を算出し、それぞれ因子名の通り「物事への集中得点」「慎重性得点」「不偏性得点」「脱軽信得点」「証拠の重視得点」とした。
以下に、クリシン志向性の平均値・標準偏差を示す(Table3)。
|
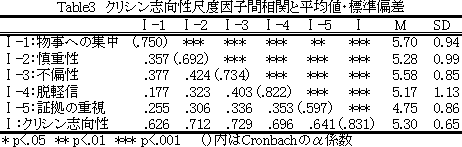
|
| ページトップへ |
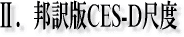
島・鹿野・北村・浅井(1985)に従い、逆転項目を逆転したのち、A=0点、B=1点、C=2点、D=3点として、20項目を足し合わせ得点化した。
本調査におけるCES-Dスコアの平均値は17.40(SD9.63)であり、かなり高い平均値を示した。正常群と気分障害群を分けるcut-off pointは、日本においても16点とするのが妥当であると考えられており(島ら,1985)、CES-Dスコアが16点以上のものは、「気分障害」の可能性が高くなる(糖野,2004)。本調査の被験者集団は、全体の50%がcut-off pointを上回っていたことから、抑うつ傾向が強い集団であったことが推測される。
なお、島ら(1985)では男性と女性のCES-D得点の間に有意差が見られたが、本調査では男女差は見られなかった。

改訂版RSQ&RRS尺度のうち、床効果が生じていた17項目を除いた11項目について、最尤法・プロマックス回転による因子分析を行った。その結果、3因子が抽出された。(Table4)
|

|
第1因子は「26.「なぜ私は物事をうまく処理していけないのだろう」と考える」「13.「気分がすぐれないせいで自分の仕事や課題をやり遂げられないだろう」と考える」といった項目に高く負荷していたため、「否定的考え込み」因子と解釈した。第2因子は「7.問題を克服するために計画を立てる」「14.自分の生活をどこか改善しようと決意する」といった項目に高く負荷していた。これら第2因子に高く負荷した項は全て、名倉・橋本(1999)において「分析的考え込み」に分類されていた反応である。しかしながら、分析的考え込みの中核と考えられる項目(e.g. 名倉・橋本,1999 野口・藤生,2005)は、その多くに床効果が生じており、第2因子には含まれていない。そのため、第2因子は何かを分析するように考え込みを行うというよりは、問題解決の意図を持って考え込みを行うという要素が強い。よって、「問題解決的考え込み」と解釈するのが妥当であると判断した。第3因子は「1.自分の憂うつな気持ちに注目することで自分自身を理解しようとする」「20.自分がなぜ憂うつなのかを理解するために最近の出来事を分析する」の2項目に高く負荷しており、自己に焦点を当て理解しようとする因子と考えられたため、「自己理解」因子とした。
各因子のα係数は、「否定的考え込み」は.717、「問題解決的考え込み」は.711、「自己理解」は.632、尺度全体では.780であった。「自己理解」については内的一貫性に疑問が残るが、それ以外の因子及び尺度全体ついては、内的一貫性は問題なかった。(Table5)
考え込み型反応の下位因子の間には、.299〜.425の相関があった。このことから、考え込み型反応の下位因子は、相互に独立したものではないことが伺われる。
各因子に負荷の高かった項目から合成得点を算出し、それぞれ因子名の通り「否定的考え込み得点」「問題解決的考え込み得点」「自己理解得点」とした。
以下に、考え込み型反応の因子間相関及び、平均値・標準偏差を示す(Table5)。
|
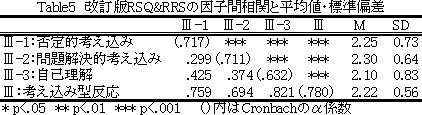
|
| ページトップへ |
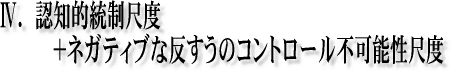
認知的統制尺度、ネガティブな反すう尺度のうち「ネガティブな反すうのコントロール不可能性」因子の両方とも、天井効果・床効果のいずれも見られなかった。
そこで、認知的統制尺度の11項目に対して、最尤法・プロマックス回転による因子分析を行った。その結果、複数の因子に|.35|以上の負荷を示した項目及び、どの因子にも|.35|以上の負荷を示さなかった2項目を削除し、再度最尤法・プロマックス回転による因子分析を行った結果、2因子が抽出された。(Table6)
|
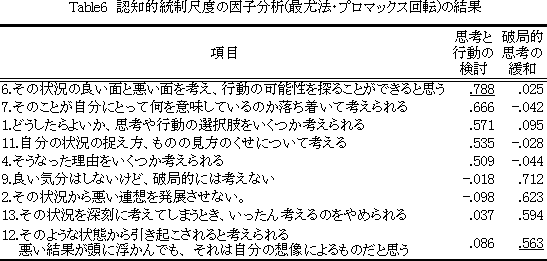
|
第1因子は、「6.その状況の良い面と悪い面を考え、行動の可能性を探ることができると思う」「7.そのことが自分にとって何を意味しているのか落ち着いて考えられる」といった項目に高く負荷していたため、「思考と行動の検討」因子と解釈した。第2因子は、「9.良い気分はしないけど、破局的には考えない」「2.その状況から悪い連想を発展させない」といった項目に高く負荷していたため、「破局的思考の緩和」因子と解釈した。
これら2因子は先行研究と同じ項目に高い負荷を示しており、先行研究と同一の因子であると考えられる。α係数は、「思考と行動の検討」は.751、「破局的思考の緩和」は.716、尺度全体では.781であり、内的一貫性は問題ないと言えた(Table7)。
「ネガティブな反すうのコントロール不可能性」については、因子分析の結果、1因子性が確認された。今回は分析の方向性から、逆転項目として扱い、「ネガティブな反すうのコントロール可能性(Control of Negative Rumination:CoNR)」とした。α係数は.814であり、内的一貫性は高かった(Table7)。
各因子に負荷の高かった項目から合成得点を算出し、それぞれ因子名の通り「思考と行動の検討得点」「破局的思考の緩和得点」とした。また、ネガティブな反すうのコントロール可能性も一因子性が確認されたため、各項目から合成得点を算出し、「ネガティブな反すうのコントロール可能性得点」とした。
次に、認知的統制およびネガティブな反すうのコントロール可能性の平均値・標準偏差を示す(Table7)。
|
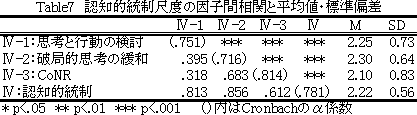
|
思考と行動の検討、破局的思考の緩和の両因子とも、ネガティブな反すうのコントロール可能性との間に有意な正の見出された。しかし、破局的思考の緩和とネガティブな反すうのコントロール可能性との相関は.683(p<.001)であるのに対し、認知的統制全体とネガティブな反すうのコントロール可能性との相関は.612(p<.001)となっており、因子単位で見た相関よりも尺度全体で見た相関のほうが低い値を示していた。また、思考と行動の検討と破局的思考の緩和との間にも有意な正の相関が見出されている(r=.318
, p<.001)ことから、思考と行動の検討とネガティブな反すうのコントロール可能性との間にある相関は疑似相関である可能性が高い。よって、破局的思考の緩和を統制した偏相関分析を行った。その結果、思考と行動の検討とネガティブな反すうのコントロール可能性との間の偏相関は見出されなかった(r=.074
, n.s.)。このことから、思考と行動を検討することができることと、自らの思考をコントロールし、嫌なことを考えているときはそれを中断し、思考を切り替えることができることとは違う次元のものであることが示唆された。
|
| ページトップへ |
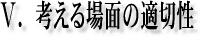
ジェネラルな「考えよう」とする志向性については、それぞれ独立した項目として扱った。全体的な「考えよう」とする志向性については、ジェネラルな「考える」とした。楽しむ場面に限定した「考えよう」とする志向性については、「考える」・楽しむ場面とした。ものごとを決める場面に限定した「考えよう」とする志向性については、「考える」・決断場面とした。
考える場面の適切性を尋ねる項目については、田中・楠見(2006)の場面分けに従い、適切な場面を表す項目については、「考えようとする」を1点、「どちらでもない」を0点、「考えようとしない」を-1点とした。不適切な場面を表す項目については、「考えようとする」を-1点、「どちらでもない」を0点、「考えようとしない」を1点とした。適切な場面9項目について足し合わせたものに9を加えたものを、「考える場面の適切性・良」得点とした。同様に、不適切な場面9項目をについて足し合わせたものに9を加えたものを「考える場面の適切性・悪」得点とした。すなわち、「考える場面の適切性・良」も「考える場面の適切性・悪」も、得点が高いほど適切な場面を選んで考えようとしていることを示している。それら2つの得点を足し合わせたものを、「考える場面の適切性」得点とした。
「考える場面の適切性」は0〜36点の得点域を持ち、中間点は18点である。18点よりも点数が低い場合は、不適切な思考場面が多く、18点よりも点数が高い場合は、適切な思考場面が多いことを表す。「考える場面の適切性・良」「考える場面の適切性・悪」は0〜18点の得点域を持ち、中間点は9点である。9点よりも点数が低い場合は、不適切な思考場面が多く、9点よりも点数が高い場合は、適切な思考場面が多いことを表す。以下に、各得点間の相関および各得点の平均値と標準偏差を示す(Table8)。
|
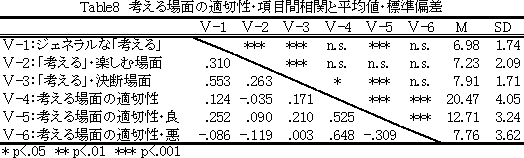
|
「考える場面の適切性・良」と「考える場面の適切性・悪」は、有意な負の相関を示しており(r=-.309 , p<.001)、適切な場面で考えようとしている者は、不適切な場面でもまた考えようとしていることが伺われた。考えようとする姿勢は場面を選んで意識的に発揮されているというよりも、考えようとする傾性を持つ者は、どのような場面においても「考えよう」としていると推測される。
また、ジェネラルな「考えよう」とする志向性と「考える場面の適切性・良」との間には有意な相関が見出され(r=.252 , p<.001)、「考える場面の適切性・悪」との間には有意な相関は見出されなかった(r=-.086 , n.s.)。このことから、「考えよう」という志向性を自らが持っていることを自覚している者は、少なくとも考えることが適切な場面をある程度選択できていることが伺われた。
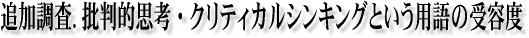
クリティカルシンキングと批判的思考は同じ概念を指す用語である。クリティカルシンキング教育を行う場合、学生に対してどちらの表現を用いることが有益なのかを検討した。2つの質問の文中に「クリティカルシンキング」という用語を用いたか、「批判的思考」という用語を用いたかによって、回答に違いがあるかを検討するため、χ2検定を行った。なお、この調査項目のみ、調査協力者の質問紙により本質問紙とは別に行われた。追加調査対象者176名のうち、項目に欠損がなかった171名(男性61名, 女性109名, 性別未回答1名, 平均年齢19.55歳, SD1.40 )が分析対象となった。
その結果、用語を知っているかどうかには有意な差は見られなかった。しかし、その用語の内容について「したくない」と思うかどうかには違いが見られた(Table9)。
|
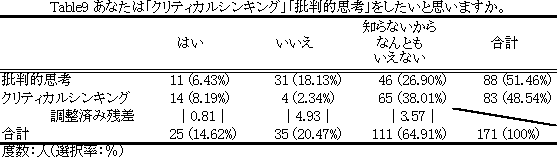
|
クリティカルシンキングという用語を用いる場合と、批判的思考を用いる場合とでは、対象者の反応に有意な連関が見られた(x2=24.055 df=2
p<.001)。以下、調整済み残差の値から判断する。
批判的思考という用語を用いた場合、クリティカルシンキングという用語を用いた場合に比べ、調査対象者はそのような思考を行いたくないと判断していた(p<.05)。また、クリティカルシンキングという用語を用いた場合、批判的思考という用語を用いた場合に比べ、調査対象者はそのような名前の思考をしたいかどうかの判断を保留していた(p<.05)。
これらのことより、批判的思考という用語を用いることはデメリットが大きく、クリティカルシンキングという用語を用いるほうが無難であることが示された。
なお、本分析はもともとその用語を知っていた者も分析対象に入っている。批判的思考およびクリティカルシンキングという用語をあらかじめ知っていた者を除いた分析の結果では、「クリティカルシンキング×いいえ」のセルの度数が1となってしまい、また、期待度数が5未満のセルが33.3%生じていたため、分析結果を採用しなかった。
|
| ページトップへ |
|
|
|
|
|