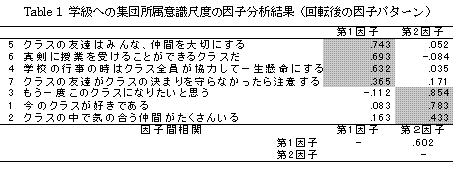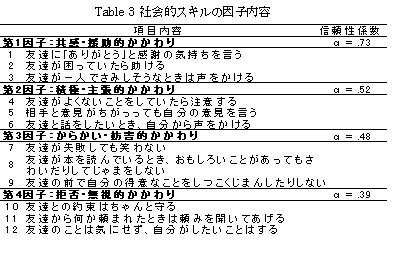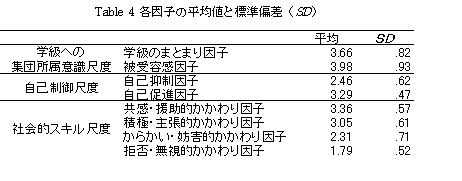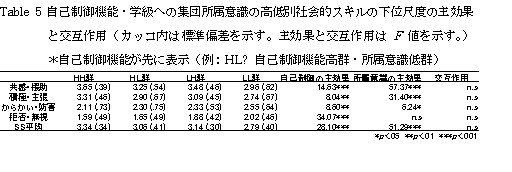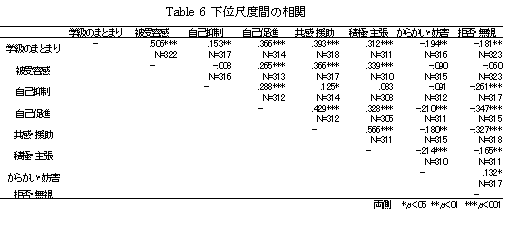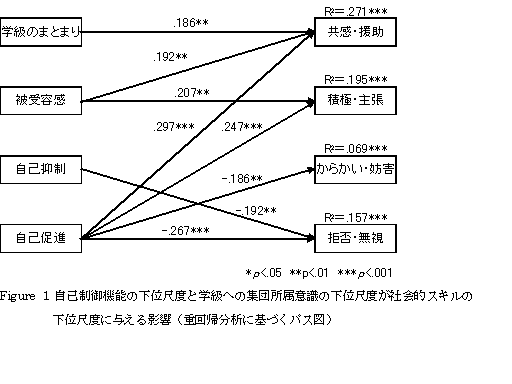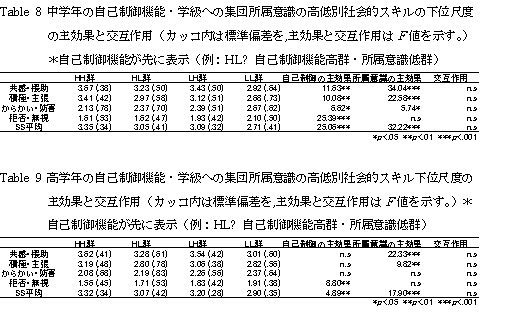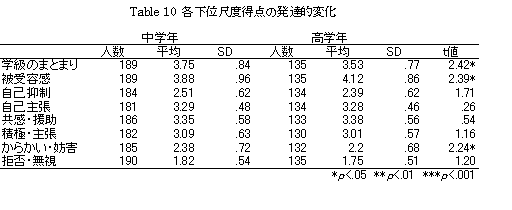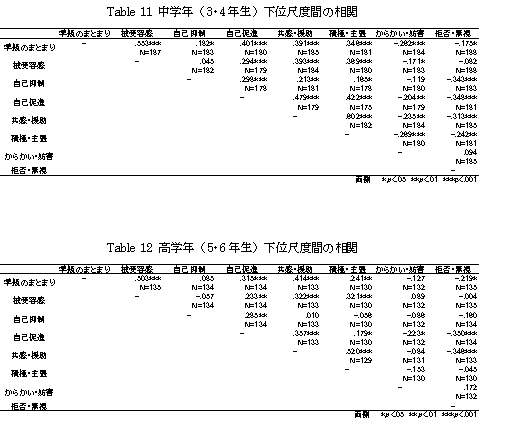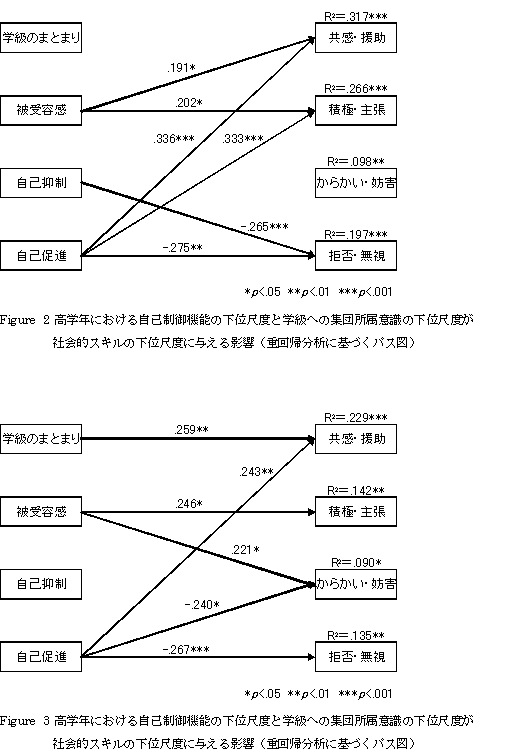●各尺度の因子分析
学級への集団所属意識尺度
全8項目について男女込みで、重みなし最小二乗法のプロマックス回転による因子分析を行った。固有値の減退状況と因子の解釈可能性から2因子解が妥当であると判断した。 本多・井上(2005)では4因子解だったが、項目を減らし項目の表現も変えているため、本研究では因子分析通り、2因子解を採用することとした。そして、十分な因子負荷量がみられなかった1項目を削除し、合計7項目で再度因子分析を行った。プロマックス回転後の因子パターンはTable 1 に示す。
本多・井上(2005)を参考に、第1因子を「学級のまとまり」、第2因子を「被受容感」と命名した。そして、因子ごとの信頼性係数を算出した。第1因子、第2因子それぞれにおいて順にα=.72、.74で、尺度全体の信頼性係数はα=.80であった。
自己制御機能尺度
全14項目について男女込みで、重みなし最小二乗法のプロマックス回転による因子分析を行った。固有値の減退状況と因子の解釈可能性から2因子解が妥当であると判断した。
庄司(1993)では4因子解だったが、項目を減らし項目の表現も変えているため、本研究では因子分析通り、2因子解を採用することとした。そして、十分な因子負荷量が見られなかった1項目を削除し、合計13項目で再度因子分析を行った。さらに、十分な因子負荷量が見られなかった1項目を削除し、合計12項目で再度因子分析を行った。その際、2因子について因子負荷量が高かった1項目を削除し、合計11項目で再度因子分析を行った。プロマックス回転後の因子パターンはTable 2 に示す。
庄司(1993)を参考に、第1因子を「自己抑制」、第2因子を「自己促進」と命名した。そして、因子ごとの信頼性係数を算出した。第1因子、第2因子それぞれにおいて順にα=.66、.59で、尺度全体の信頼性係数はα=.73であった。
社会的スキル尺度
全12項目について男女込みで、重みなし最小二乗法のプロマックス回転による因子分析を行った。固有値の減退状況と因子の解釈可能性から、3因子解が妥当であると判断した。庄司ら(1992)では4因子解だったが、項目を減らし表現も変えているため、因子分析通り、3因子解で分析を進めることとした。そして、十分な因子負荷量が見られなかった1項目を削除し、合計11項目で再度因子分析を行った。しかし、各因子について十分な信頼性が得られなかったため、全12項目で因子数を2に指定し因子分析を行った。そして、十分な因子負荷量が見られなかった1項目を削除し、合計11項目で再度因子分析を行った。さらに、十分な因子負荷量が見られなかった1項目を削除し、合計10項目で因子分析を行った。しかし、今回も各因子について十分な信頼性が得られなかった。
因子分析において十分な信頼性が得られなかったが、本研究では本多・井上(2005)の因子分析結果に習い、4因子に分類し研究を進めることとした。各因子を形成する項目と各因子の信頼性係数はTable 3 に示す。
因子分析の結果から、「学級のまとまり」、「被受容感」、「自己抑制」、「自己促進」、「共感・援助的かかわり」、「積極・主張的かかわり」、「からかい・妨害的かかわり」、「拒否・無視的かかわり」のそれぞれの項目の平均値を算出し、各因子の下位尺度得点とした。各因子の平均と標準偏差(SD)はTable 4 に示す。
●自己制御機能、学級への集団所属意識と社会的スキルとの関係
自己制御機能と学級への集団所属意識の高低によって社会的スキルの下位尺度得点に違いがあるかを検討するために、自己制御機能と学級への集団所属意識を要因とする2要因分散分析を行った。自己制御機能と学級への集団所属意識は平均値を基準に高群・低群に分けた。自己制御機能の平均値は2.97、学級への集団所属意識の平均値は3.20であった。結果をTable 5 に示す。「共感・援助的かかわり」(F(1,301)=14.63, p<.001)、「積極・主張的かかわり」(F(1,296)=8.04, p<.01)、「からかい・妨害的かかわり」(F(1,301)=8.60, p<.01)、「拒否・無視的かかわり」(F(1,303)=34.07, p<.001)、社会的スキル全体の平均(SS平均)(F(1,294)=28.10, p<.001)、全てに対して自己制御機能の有意な主効果がみられた。また、「共感・援助的かかわり」(F(1,301)=57.37, p<.001)、「積極・主張的かかわり」(F(1,296)=31.40, p<001)、「からかい・妨害的かかわり」(F(1,301)=6.24, p<.05)、社会的スキル全体の平均(SS平均)(F(1,294)=51.29, p<.001)に対して学級への集団所属意識の有意な主効果がみられたが、「からかい・妨害的かかわり」に対してはみられなかった。自己制御機能と学級への集団所属意識について有意な交互作用はみられなかった。
●各下位尺度の関係
各下位尺度間に関係があるかを検討するために全ての下位尺度間の相関係数を算出した。結果をTable 6 に示す。「被受容感」と「学級のまとまり」、「自己抑制」と「学級のまとまり」、「自己促進」と「学級のまとまり」、「自己促進」と「被受容感」、「自己促進」と「自己抑制」、「共感・援助的かかわり」と「学級のまとまり」、「共感・援助的かかわり」と「被受容感」、「共感・援助的かかわり」と「自己抑制」、「共感・援助的かかわり」と「自己促進」、「積極・主張的かかわり」と「学級のまとまり」、「積極・主張的かかわり」と「被受容感」、「積極・主張的かかわり」と「自己促進」、「積極・主張的かかわり」と「共感・援助的かかわり」、「からかい・妨害的かかわり」と「拒否・無視的かかわり」の間に有意な正の相関がみられた。「からかい・妨害的かかわり」と「学級のまとまり」、「からかい妨害的かかわり」と「自己促進」、「からかい妨害的かかわり」と「共感・援助的かかわり」、「からかい・妨害的かかわり」と「積極・主張的かかわり」、「拒否・無視的かかわり」と「学級のまとまり」、「拒否無視的かかわり」と「自己抑制」、「拒否・無視的かかわり」と「自己促進」、「拒否・無視的かかわり」と「共感・援助的かかわり」、「拒否・無視的かかわり」と「積極・主張的かかわり」の間に有意な負の相関がみられた。
●自己制御機能、学級への集団所属意識が社会的スキルへ与える影響
自己制御機能の下位尺度と学級への集団所属意識の下位尺度が社会的スキルの下位尺度に与える影響を検討するために、重回帰分析を行った。重回帰分析に基づくパス図をFigure 1 に示す。「学級のまとまり」と「被受容感」と「自己促進」から「共感・援助的かかわり」に対する標準偏回帰係数と「被受容感」と「自己促進」から「積極・主張的かかわり」に対する標準偏回帰係数が有意であった。また、「自己促進」から「からかい・妨害的かかわり」に対する負の標準偏回帰係数と「自己抑制」と「自己促進」から「拒否・無視的かかわり」に対する負の標準偏回帰係数が有意であった。
●自己制御機能、学級への集団所属意識と社会的スキルとの関係の発達的変化
自己制御機能と学級への集団所属意識の高低による社会的スキルの下位尺度得点の変化に発達的な違いがみられるかを検討するために、中学年(3・4年生)と高学年(5・6年生)に群分けをし、それぞれにおいて自己制御機能と学級への集団所属意識を要因とする2要因分散分析を行った。学年差を検討したかったが、各学年の対象児の人数が十分ではなかったため、中学年と高学年に分類した。自己制御機能と学級への集団所属意識は全体の平均値を基準として高群・低群に分けた。自己制御機能の平均値は2.97、学級への集団所属意識の平均値は3.20であった。中学年の結果をTable 8 に、高学年の結果をTable 9 に示す。中学年は「共感・援助的かかわり」(F(1,169)=11.63, p<.01)、「積極・主張的かかわり」(F(1,166)=10.08, p<.01)に対して自己制御機能の有意な主効果がみられ、「からかい・妨害的かかわり」に対して自己制御機能の有意な主効果と学級への集団所属意識の有意な主効果(F(1,169)=6.62, p<.05, F(1,169)=5.74, p<.05)がみられた。一方で、高学年では、「共感・援助的かかわり」(F(1,128)=22.33, p<.001)、「積極・主張的かかわり」(F(1,126)=9.82, p<.01)に対して学級への集団所属意識の有意な主効果、「拒否・無視的かかわり」(F(1,129)=8.80, p<01)に対する自己制御機能の有意な主効果、社会的スキル全体(SS平均)に対する自己制御機能と学級への集団所属意識の有意な主効果(F(1,125)=4.89, p<.05, F(1,125)=17.90, p<.001)がみられた。自己制御機能と学級への集団所属意識についての有意な交互作用は、中学年でも高学年でもみられなかった。
●各下位尺度得点の発達的変化
各下位尺度得点に中学年(3・4年生)と高学年(5・6年生)で発達的変化が見られるかを検討するために、「学級のまとまり」、「被受容感」、「自己抑制」、「自己主張」、「共感・援助的かかわり」、「積極・主張的かかわり」、「からかい・妨害的かかわり」、「拒否・無視的かかわり」について、T検定を行った。その結果をTable 10 に示す。「学級のまとまり」(t(322)=2.42, p<.05)と「からかい・妨害的かかわり」(t(315)=2.24, p<.05)について中学年より高学年のほうが有意に得点が低いことが示された。また、「被受容感」(t(307)=-2.39, p<.05)は中学年より高学年のほうが有意に得点が高いことが示された。
●各下位尺度の関係の発達的変化
各下位尺度間の関係に発達的変化があるかを検討するために、中学年(3・4年生)と高学年(5・6年生)に分けて、それぞれにおいて全ての下位尺度間の相関係数を算出した。中学年の結果をTable 11 に、高学年の結果を Table 12 に示す。中学年において、「自己抑制」と「学級のまとまり」、「共感・援助的かかわり」と「自己抑制」、「積極・主張的かかわり」と「自己抑制」の間に有意な正の相関がみられたが、高学年ではこれらの有意な相関はみられなかった。また、中学年において、「からかい・妨害的かかわり」と「学級のまとまり」、「からかい・妨害的かかわり」と「被受容感」、「からかい妨害的かかわり」と「共感・援助的かかわり」、「からかい・妨害的かかわり」と「積極・主張的かかわり」、「拒否・無視的かかわり」と「自己抑制」、「拒否・無視的かかわり」と「積極・主張的かかわり」の間に有意な負の相関がみられたが、高学年ではこれらの有意な相関はみられなかった。
●自己制御機能、学級への集団所属意識が社会的スキルへ与える影響の発達的変化
自己制御機能の下位尺度と学級への集団所属意識の下位尺度が社会的スキルの下位尺度に与える影響の発達的変化を検討するために、中学年(3・4年生)と高学年(5・6年生)に分けて、それぞれについて重回帰分析を行った。中学年の結果をFigure 2 に、高学年の結果をFigure 3 に示す。中学年では「学級のまとまり」から「共感・援助的かかわり」に対する標準偏回帰係数、「被受容感」から「からかい・妨害的かかわり」に対する標準偏回帰係数と「自己促進」から「からかい・妨害的かかわり」に対する負の標準偏回帰係数は有意ではなかったが、高学年では有意になった。また、中学年では「被受容感」から「共感・援助的かかわり」に対する標準偏回帰係数、「自己促進」から「積極・主張的かかわり」に対する標準偏回帰係数、「自己抑制」から「拒否・無視的かかわり」に対する負の標準偏回帰係数が有意だったが、高学年では有意ではなくなった。