研究1 動機づけを測定する尺度の開発
【問題と目的】
実験場面において内発的動機づけを測定する指標としては行動指標と態度指標とに大別できる。行動指標には、自発的な行動生起の程度を問うものと行動遂行の質を評価するものの2つがある。このうち自発的な行動生起については、自由選択場面における標的課題への従事時間を内発的動機づけの指標とするものが圧倒的に多い。鹿毛(1990, 1993)や鹿毛・並木(1990)では、課題を被験者に渡し、その遂行に随伴性がないことを示した上で、自主的にそれを遂行するか否かにより内発的動機づけを測定している。また、小倉・松田(1988)は、標的課題の作業量について他の課題の作業量と比較した割合を内発的動機づけの指標としている。もうひとつの行動指標である行動遂行の質は、質の高い遂行が認識や技能を高めようとする内発的動機づけの特質のあらわれであるという見方を前提としている。Amabile(1979)は内発的動機づけと創造性との間に正の関連性があると指摘し、デザイン課題における創造性の評価値を内発的動機づけの指標としている。次に態度指標であるが、多くの場合行動指標と併せて用いられている。多くは、標的課題に対する興味やおもしろさ、楽しさといった情緒的な側面に焦点を当てている。鹿毛(1993)は課題に対する興味を測定する知的好奇心項目、卓越した水準での課題への取り組みを測定する挑戦項目、自主的な課題への取り組みを測定する自律性項目の3つの側面を区別しそれぞれを態度指標としている。なお本研究においては行動指標を用い自由時間においての従事時間を内発的動機づけの指標とし検討する。
また動機づけを測定する尺度は、動機づけを自己決定性の視点からとらえた自己決定理論(Deci & Ryan, 1985;Ryan & Deci, 2002)に基づくものも数多くあり、自己決定性の度合いから「内発的動機づけ」「同一視的調整」「取り入れ的調整」「外的調整」「無動機」といった複数の概念が想定されており、動機づけレベルを段階的にとらえることができるという利点から、これらの5つの概念を下位尺度として尺度項目を構成し、学習・スポーツ、恋愛場面、政治活動などさまざまな分野で質問紙調査が行われこの概念に基づく尺度が検討されている。学習場面においての研究で、吉野(2008) は中学生向けに、「内発的動機づけ」「同一視的調整」「取り入れ的調整」、「外的調整」、「無動機」の5つの下位尺度からなる英語学習に関しての動機づけ尺度を作成している。また対人場面においては、岡田(2005) は大学生を対象に外的調整、取り入れ的調整、同一視的調整、内発的動機づけからなる友人関係に関する動機づけ尺度を作成している。しかし対人場面においても「対乳児」に関しては動機づけを測定する尺度が開発されていない。そこで本研究では、対乳児場面での内発的動機づけを測定する尺度を新たに開発し、その妥当性を検討する。乳児とかかわることに対しての動機づけを自律性の視点から段階的に検討するためには、自己決定理論を用いることが有用だと考えられる。またこれまで作成されてきた、学習場面や対人場面においての動機づけを測定する尺度はその場面のみに適応する尺度であった。そのため本研究では自己決定理論に基づき、新たに対乳児場面における動機づけを測定する尺度を開発する。
研究1【方法】
対象:国立M大学の学生43名。男子9名、女子34名。
手続き:質問紙による調査を行った。調査時期は2009年11月下旬。大学の講義時間中に配布し回収した。
質問紙の構成
1.対乳児場面動機づけ尺度
吉野(2008) を参考に、「無動機」・「外的調整」・「取り入れ的調整」・「同一視的調整」・「内発的動機づけ」の5つの下位尺度からなる、乳児とかかわる場面での動機づけ尺度25項目を作成した。「強くそう思う」から「全くそう思わない」までの4件法で回答を求めた。
2.対乳児場面認知尺度
乳児とかかわることに対しての認知をたずねる尺度10項目(ネガティブ認知・ポジティブ認知、各5項目)を作成したものを用いた。「強くそう思う」から「全くそう思わない」までの4件法で回答を求めた。なおネガティブな認知は得点が高いほどよりネガティブに、ポジティブな認知は得点が高いほどよりポジティブになるようにした。
3.対乳児感情尺度
花沢(1992) を参考に、乳児に対して接近的な感情や回避的な感情を28項目でたずねた。「強くそう思う」から「全くそう思わない」までの4件法で回答を求めた。
研究1【結果】
1.尺度構成
1-1)対乳児場面動機づけ尺度
対乳児場面動機づけ尺度25項目について、先行研究を参考に5因子解(主因子法・プロマックス)で因子分析を行った。その結果因子負荷量が.40に満たない項目が多くなったため、「無動機」の項目を削除し4因子解で再び因子分析(主因子法・プロマックス)を行った。因子負荷量が.40に満たなかった1項目(項目8:乳児と遊べる人は格好が良いから)を削除し、再度同じ手続きで因子分析を行った。その結果4因子を抽出した。また第1因子を「内発的動機づけ因子」、第2因子を「外的調整因子」、第3因子を「同一視的調整因子」、第4因子を「取り入れ的調整因子」と命名した。その結果をTable 1に示す。
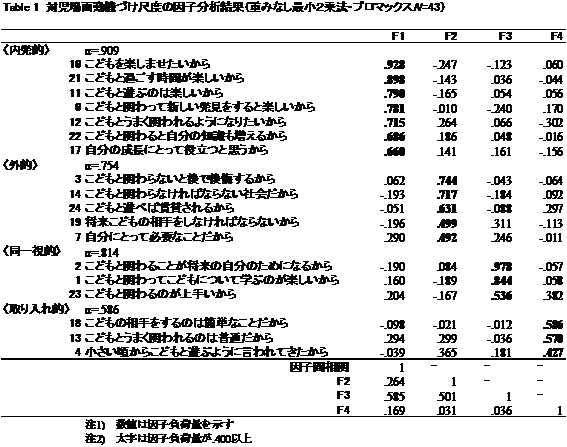
次に各因子に.40以上の負荷を示した項目群を下位尺度の項目とし,それらの加算平均を下位尺度得点とした。また各下位尺度において、内的整合性を検討するために、Cronbachのα係数を算出したところ内発的動機づけ=.909、外的調整=.754、同一視的調整=.814、取り入れ的調整=.586であった。「取り入れ的調整」については、項目の削除を行ったが、α係数の上昇がみられなかったため、以降の分析から除外した。そして下位尺度ごとの平均値・標準偏差、下位尺度間の相関係数を算出した。結果をTable 2に示す。
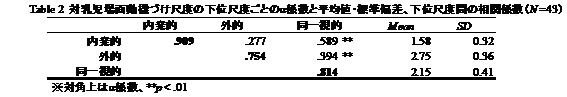
Table 2 より、下位尺度間の相関に関して「内発的動機づけ」と「同一視的調整」で高い有意な正の相関がみられ、「外的調整」と「同一視的調整」で有意な正の相関がみられた。
1-2)対乳児場面認知尺度
対児場面認知尺度を、乳児とかかわることへの認知において、ネガティブな認知を示しているものを「認知ネガティブ」(5項目)、乳児とかかわることへの認知においてポジティブな認知を示しているものを「認知ポジティブ」(5項目)として、2つの下位尺度にわけ、平均値・標準偏差を算出した。結果をTable 3 に示す。
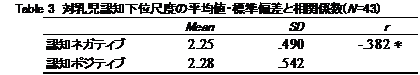
1-3)対乳児感情尺度
対乳児感情尺度を花沢(1992)に基づき、乳児に対し接近的な感情をたずねたものを「対乳児感情接近」(14項目)、乳児に対し回避的感情をたずねたものを「対乳児感情回避」(14項目)として、2つの下位尺度にわけ、平均値・標準偏差を算出した。結果をTable 4 に示す。
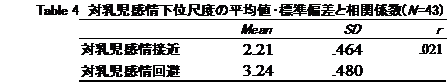
1-4)対乳児場面認知と対乳児感情の関連
対乳児場面認知と対乳児感情の下位尺度間の関連をみるため相関係数を算出した。結果をTable 5に示す。
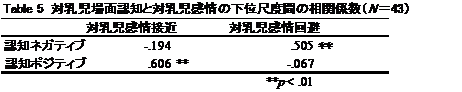
Table 5 より、対乳児場面認知のネガティブと対児感情の回避に有意な正の相関がみられた。また対乳児場面ポジティブと対児感情の接近に有意な正の相関がみられた。
2.各尺度間の関連
対乳児場面動機づけ・対乳児場面認知・対乳児感情の関連
対乳児場面動機づけ尺度と対乳児場面認知尺度・対乳児感情尺度の下位尺度間の関連を検討するため、相関係数を算出した。結果をTable 6 に示す。
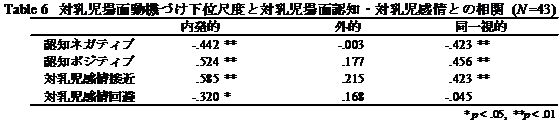
Table 6より、対乳児場面動機づけの内発的動機づけと認知ネガティブ、対乳児感情回避にそれぞれ有意な負の相関、内発的動機づけと認知ポジティブ、対乳児感情接近にそれぞれ有意な正の相関がみられた。また同一視的と認知ネガティブに有意な負の相関、同一視と認知ポジティブ、対乳児感情接近に有意な正の相関がみられた。
研究1【考察】
本研究では、対乳児場面における動機づけを測定する尺度を新たに開発するという目的のため、「対乳児場面動機づけ尺度」を作成し質問紙調査を行い、尺度の信頼性、下位尺度間の関連、他の尺度との関連を検討した。
1.尺度構成
対乳児場面動機づけ尺度の因子分析の結果4因子を抽出した。その結果これまでの研究で見出されていた「内発的動機づけ」「外的調整」「同一視的調整」「取り入れ的調整」という因子に対応する結果が得られた。この結果を参考に下位尺度を参考にしたところ、「取り入れ的調整」については十分な信頼性係数が得られなかった。これについては、今後の検討が必要である。また因子分析の結果尺度を作成する段階で「同一視的調整」として作成したもの(項目12:うまくかかわれるようになりたいから、項目22:こどもとかかわると自分の知識も増えるから)が「内発的動機づけ」の因子に高い負荷を示した。これは、項目の内容が大学生には自律性の高いものとして捉えられたということが考えられる。
2.対乳児場面動機づけの下位尺度間の関連
対乳児場面動機づけの下位尺度間の関連をみるため、相関係数を算出した(Table 2)。その結果、下位尺度間の相関に関して、内発的動機づけと同一視的調整で高い正の相関がみられ、外的調整と同一視的調整で正の相関がみられた。Deci & Ryan (2002)では自己決定理論において、「内発的動機づけ」「同一視的調整」「取り入れ的調整」「外的調整」「無動機」が自己決定性の観点から一次元の連続体上に並ぶものと考えられており、近い位置関係にある概念間では強い相関がみられ、また対極的な位置関係にある概念間では強い負の相関がみられるという、シンプレックス構造をなすことが仮定されている。例えば隣接する概念である「内発的動機づけ」と「同一視的調整」では強い正の相関を示し、対極な位置関係の概念である「内発的動機づけ」と「無動機」では無相関ないし強い負の相関を示す。本研究では、隣接する概念である「内発的動機づけ」と「同一視的調整」の間に強い正の相関がみられ、先行研究と同様の結果が得られた。また「外的調整」と「同一視的調整」の間に有意な正の相関がみられ、「外的調整」と「内発的動機づけ」には中程度の正の相関がみられた。廣森(2003)では「外的調整」と「同一視的調整」、「外的調整」と「内発的動機づけ」の間に負の相関がみられ、本研究は先行研究とは異なる結果であった。「同一視的調整」と「外的調整」の間で負の相関がみられなかったのは、項目を作成する際に、同一視的調整の項目として作成したもの(項目7:自分にとって必要なことだから)が因子分析の結果、外的調整因子に入り、また取り入れ的調整の項目として作成したもの(項目23:乳児とかかわるのが上手いから)が因子分析の結果、同一視的調整因子に入ったため、正の相関がみられたと考えられる。しかし隣接する「内発的動機づけ」と「同一視的調整」間の相関ほど高い相関は得られず、「内発的動機づけ」「同一視的調整」「外的調整」の概念の位置関係が近いほど強い相関を示しており、シンプレックス構造をなしていると考えられる。このことから、自己決定性に基づいて「内発的動機づけ」「同一視的調整」「外的調整」の順に連続体をなしていることが確認された。
3.各尺度間の関連
3-1)対乳児場面認知と対乳児感情の関連
対乳児場面認知と対乳児感情の下位尺度間の関連をみるため相関係数を算出した(Table 5)。その結果、「認知ネガティブ」と「対児感情回避」に有意な正の相関がみられた。また「認知ポジティブ」と「対児感情接近」に有意な正の相関がみられた。これは乳児とかかわることに関してネガティブな認知の者は乳児に関して回避的な感情を抱き、乳児とかかわることに関してポジティブな認知の者は乳児に関して接近的な感情を抱いているということがいえる。
3-2)対乳児場面動機づけと対乳児場面認知・対乳児感情の関連
対乳児場面動機づけと対乳児場面認知・対乳児感情の下位尺度間の関連を検討するため、相関係数を算出した(Table 6)。その結果、対乳児場面動機づけの「内発的動機づけ」と「認知ネガティブ」、「対児感情回避」にそれぞれ有意な負の相関、「同一視的」と「認知ネガティブ」に有意な負の相関がみられた。これは、乳児とかかわることに対しての内発的動機づけが低い者は、乳児とかかわることに関してネガティブな認知であり、さらに乳児に関して回避的感情を抱いているということを示している。また「内発的動機づけ」と「認知ポジティブ」、「対乳児感情接近」にそれぞれ有意な正の相関、「同一視」と「認知ポジティブ」、「対児感情接近」に有意な正の相関がみられた。これは先ほどと反対に、乳児とかかわることに関しての内発的動機づけや、より自律的な外発的動機づけが高い者は、乳児とかかわることに関してポジティブな認知であり、さらに乳児に関して接近的感情を抱いているということがいえる。
また「対児感情回避」に着目してみると、「内発的動機づけ」には負の相関を示しているが、「同一視的調整」には無相関に近い状態である。この結果から、自己決定理論において「内発的動機づけ」に次いで「同一視的調整」は自己決定性が高いものとして扱われているが、本質的には外発的動機づけであり、内発的な動機づけとは異なるものであるということを改めて示したといえる。