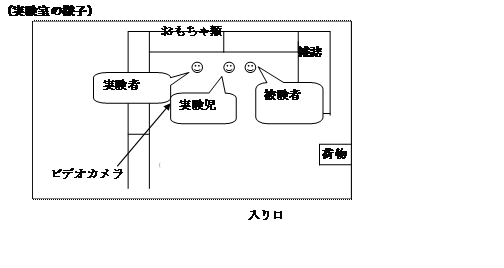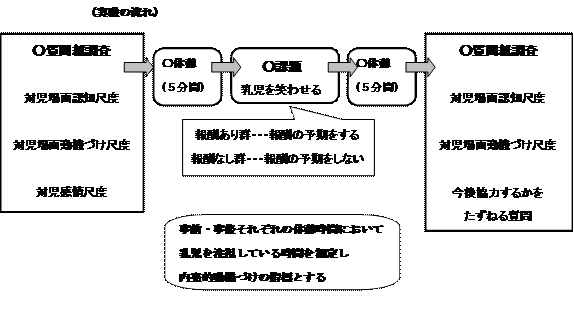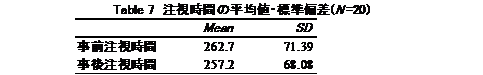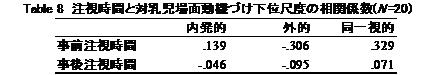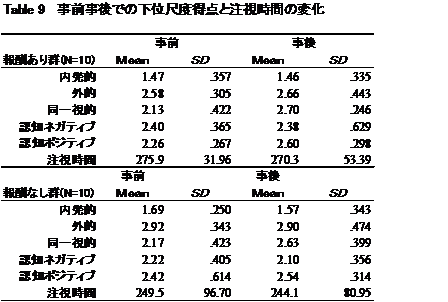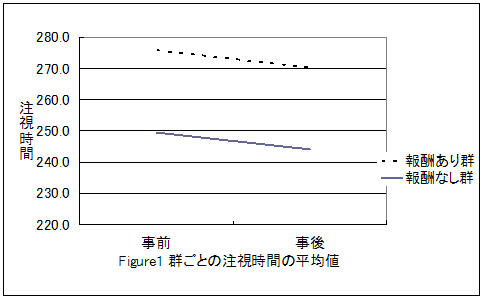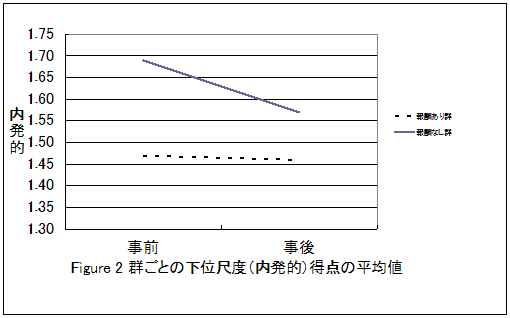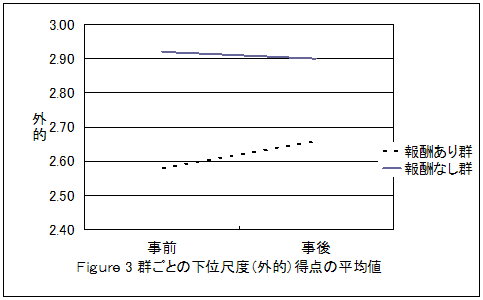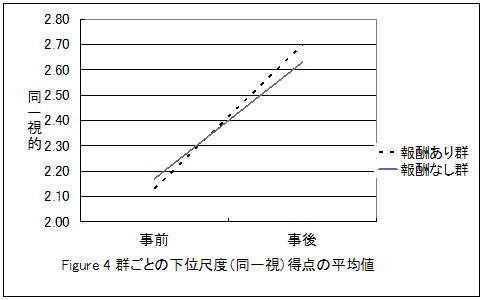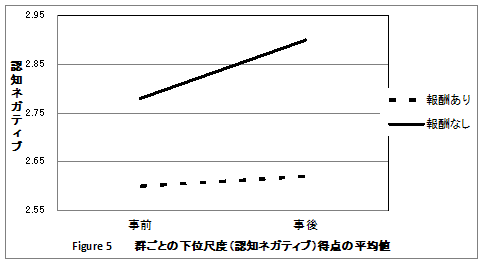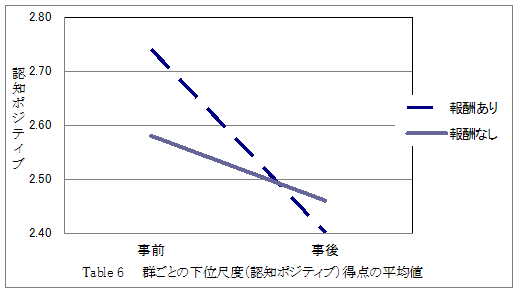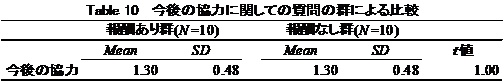�����Q�@��V���Γ�����ʂɂ���������I���@�Â��ɗ^����e��
�y���ƖړI�z
�@�S���w�̌����ɂ����Ă�1960�N�㍠�܂ŁA�O�I��V�͐l�Ԃ̓����I�w�K�ӗ~�����߂���ʂ�����ƍl�����Ă����B�Ƃ��낪1970�N��ɓ���A�O�I��V�͓����I���@�Â����������(�A���_�[�}�C�j���O����)������Ƃ������Ƃ������ɂ��m���߂�ꂽ�iDeci, 1971�j�BDeci (1971) �͑�w����팱�҂Ƃ��Ď������s���A���K��V��^���邱�Ƃɂ���Ėʔ����p�Y���Ɋւ��鋻�������Ȃ��邱�Ƃ���Ă���B�܂�Lepper ,Greene, & Nisbett (1973)�͕ۈ牀����팱�҂Ƃ��āA��V�\�����s����V��^���邱�ƂŊG��`�����Ƃւ̋������ቺ���邱�Ƃ���Ă���B���̂悤�ɊO�I��V�ɂ������I���@�Â��ւ̑����I���ʂ͍L�͈͂ȔN��ɂ����ĔF�߂��Ă���(Deci��Ryan,1980) �B
�@�܂�����܂ŊO�I��V�����@�Â��ɗ^����e�����������������ɂ����ẮA�w�Ə�ʂł̓��@�Â��ɒ��ڂ������̂������݂���B��{�E���c�i1987�j�͊����w�K��ʂɂ����ď�Ƃ����`�ŕ�V�����A�����̓����I���@�Â��ւ̉e�������������B�������ΐl��ʂɂ����ĕ�V�\���̌��ʂ��������������͂Ȃ���Ă��Ȃ��B����Č����Q�ł́A�ΐl��ʂɂ����Ă̕�V�\���̌��ʂ���������B
�܂��u�ΐl��ʁv�Ƃ����Ă��A���肪�N�ł���̂��ɂ���ĕ�V�\���̌��ʂɂ��Ⴂ���݂��邾�낤�B�����Ƃ�����邱�Ƃ́A�킽����������l�ɂȂ�A�₪�Ďq��Ă��o������ہA�傢�ɖ𗧂d�v�Ȍo���ɂȂ邾�낤�B�����������Ƃ�������ʂł́A�Ƃ��ɑΏ�������ȏɂȂ�A���S�������邱�Ƃ�����B���Ɏq��ď�ʂł͕��S�������₷���X�g���X�ƂȂ邱�Ƃ�����B�q��Ē��̕��S���Ɋւ��Ă̓��v�ɂ����āA�V���ȏ�̏������q��Ăɕ��S�������邱�Ƃ�����Ƃ������Ƃ������ꂽ(�q��Ďx���f�[�^�W, 2006)�B�܂����c�E�r��E��q�c�E����(2003)�́A���A�J��������e�͏A�J��������e�ɔ�玙���S���������Ƃ������Ƃ���Ă���B���̂悤�ɕ��S�������邱�Ƃ���������Ƃ�������ʂɂ����ẮA�����Ƃ�����邱�Ƃɑ��ē��@�Â����邱�Ƃ��d�v�ł���B���@�Â����邱�Ƃɂ��A���S�������邱�Ƃ������Ă��A�����ƑO�����ɂ�����邱�Ƃ��ł��邾�낤�B����Č����Q�ł͓����Ƃ�������ʂɂ����Ă̕�V�\���̌��ʂ��������A�Γ�����ʂɂ����ē����Ƃ�����邱�Ƃɑ��ē��@�Â����邱�Ƃ̏d�v���𖾂炩�ɂ���B
�����Q�y���@�z
�Ώ��F�����l��w����w���̏��q��w���Q�O���B�Ȃ���V��^����Q(�ȉ���V����Q)�P�O���E��V��^���Ȃ��Q(�ȉ���V�Ȃ��Q)�P�O���Ƃ����B
�����͒j����菗���̕������S��������₷���A���S�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��珗�q��w����팱�҂ɑI�B
�葱��
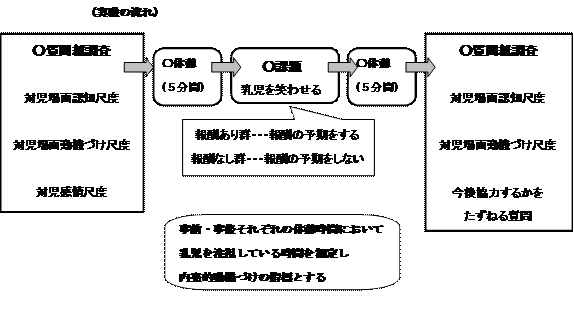
����������2009�N11�����{����12�����{�B��w�̍u�`���ɁA�����Ƃ�����邱�Ƃ̌������s���Ă�������ƗV�Ԏ����ɋ��͂��Ă��炢�����Ƃ������Ƃ�������A�����ɋ��͂��Ă����w���Q�O�����W�����͂��Ă�������B�w���ɂ͌���������ɗ��Ă��炢�����Ƃ������������s�����B�������͂P�O�����i���������j�̒j�̎q�ŁA�팱�҂ɂ͂��炩���ߎ������Ƃ�������Ă��炤���Ƃ���������B
�����̗���Ƃ��ẮA�ŏ��ɔ팱�҂Ɏ��O�̎��⎆�ړn���A�����܂łɉ��Ă���悤�˗����A���O�̎��⎆�������s�����B����팱�҂��P�����������ɌĂѓ����Ƃ�������Ă�������B�ۑ�Ɏ��g��ł��炤�O�Ɏ��O�̂T���Ԃ̋x�e���Ԃ�݂��A���̌�u�ł��邾���������������킹��v�Ƃ����ۑ�ɂT���Ԏ��g��ł�������B�Ȃ��A��V����Q�Ɋւ��Ă͉ۑ�O�̐������ɕ�V�̗\�����s�����B�����ĉۑ�I����ĂтT���Ԃ̋x�e���Ԃ�݂����B����ɂ��̌㎖��̎��⎆�ɉ��Ă�������B
�Ȃ����@�Â��̎w�W�Ƃ��Ă͎����J�n�O�E�����I����̎��⎆�Ɖۑ�Ɏ��g�ގ��O�E����̋x�e���Ԃɂ����Ă̒������Ԃ�p�����B�s���w�W�Ɋւ��āADeci�i1975�Ȃǁj�ɂ��Ɓu���Y�����ɑ��Ċώ@�\�ȊO�I�U�������݂��Ȃ��ꍇ�A���̊����͓����I�ɓ��@�Â����Ă���v�Ƃ��������I���@�Â��̑���I��`���s���Ă���B����Ē������Ԃ�����I���@�Â��̎w�W�ɂ����B���O�E���セ�ꂼ��̋x�e���Ԃœ����𒍎����Ă��鎞�ԂɊւ��āA�����̗l�q���r�f�I�J�����ŎB�e�������̂�����Đ����A�ۑ�Ɏ��g�ގ��O�E����ł̎������𒍎����Ă��鎞�ԁi�b���j���X�g�b�v�E�H�b�`�ő��肵���B�Ȃ��A�������̍s�������Ă��鎞�Ԃ𒍎����Ă��鎞�ԂƂ݂Ȃ����Ƃɂ����B�܂��������Ԃ̍ő�l��300(�b)�A�ŏ��l��0(�b)�ł���B
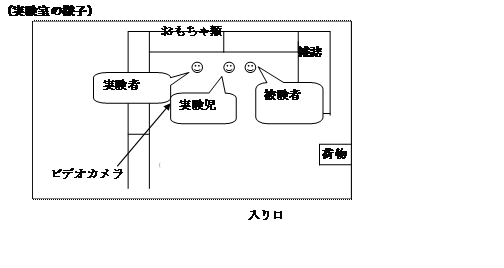
�܂��������͎����҂Ǝ������A�팱�҂̂R�l�̂ݓ������A�������ƗV��ł��炤���߂̂�������Ɣ팱�҂��������ȊO�ɋ������Ђ����̂Ƃ��āA�t�@�b�V�������S���E���s�K�C�h�Q�������{�P���̌v�V���̎G����p�ӂ����B�Ȃ��������̂�������ɑ��鋻���E�S���ቺ�������߁A�����̔팱�҂̎������I���������_�ŐV���Ȃ��������lj������B�܂��팱�҂Ǝ������̗l�q���ώ@�����͂ɗp���邽�ߎ����X�y�[�X�̊p�Ƀr�f�I�J�����P���ݒu�������̗l�q���B�e�����B
�@���O�̎��⎆����
�@�@�����O�ɂ��炩���ߎ��O���⎆��팱�҂ɓn���A�������ɉ������̂������Ă��Ă�������B
���⎆�̍\��
1.�Γ�����ʔF�m�ړx
�����Ƃ�����邱�Ƃɑ��Ă̔F�m�������˂�ړx10���ځi�l�K�e�B�u�F�m�E�|�W�e�B�u�F�m�A�e�T���ځj���쐬�����B�u���������v���v����u�S�������v��Ȃ��v�܂ł̂S���@�ʼn����߂��B�Ȃ��l�K�e�B�u�ȔF�m�͓��_�������قǂ��l�K�e�B�u�ɁA�|�W�e�B�u�ȔF�m�͓��_�������قǂ��|�W�e�B�u�ɂȂ�悤�ɂ����B
2.�Γ�����ʓ��@�Â��ړx�i�����P�����Ƃɉ��ʎړx�̍\�����s�������̂��g�p�j
�g��(2008) ���Q�l�ɁA�u�����@�v�E�u�O�I�����v�E�u������I�����v�E�u���ꎋ�I�����v�E�u�����I���@�Â��v�̂T�̉��ʎړx����Ȃ�A�����Ƃ�������ʂł̓��@�Â��ړx25���ڂ��쐬�����B�u���������v���v����u�S�������v��Ȃ��v�܂ł̂S���@�ʼn����߂��B
3.�Γ�������ړx�i���O���⎆�̂݁j
�@�@�ԑ�(1992) ���Q�l�ɁA�����ɑ��ĐڋߓI�Ȋ������I�Ȋ����28���ڂł����˂��B�u���������v���v����u�S�������v��Ȃ��v�܂ł̂S���@�ʼn����߂��B
�A���O�̂T���Ԃ̋x�e
�@�@��قǎ������Ɖۑ�Ɏ��g��ł��炤�Ƃ������Ƃ��ŏ��ɐ������A�������팱�҂Ɠ�����Ԃɂ��邱�ƂɊ���Ȃ��Ɖۑ肪��肭�����Ȃ��ꍇ������̂ŁA����邽�߂ɂ܂��T���ԉ߂����Ă��炤�Ƃ����������s������T���Ԃ̋x�e���Ƃ����B
�@�@�i�����������e�j
�u���݂����߂Ċ�����킹��킯�ł����A�������m��Ȃ��l�Ƃ����Ȃ�������s���Ƌْ����Ă��܂����܂������Ȃ��ꍇ������܂��B�����ɂƂ��Ă͓�����Ԃɂ��邾���ŋْ����ق����̂ŁA�Ƃ肠�����T���Ԉꏏ�ɂ��Ă��炦�܂����B�����Ƃ�������Ă��悢���A����������Ȃ��Ă����\�ł��̂ŁA���̃X�y�[�X���ɂ��Ă���������Ύ��R�ɉ������Ă��������Ă��悢�ł��B������ɎG�����p�ӂ��Ă����܂����̂ŁA�����R�Ɍ��Ă�����Ă����\�ł��B�v�Ƌ������T���Ԃ̋x�e���Ƃ����B�Ȃ��x�e���Ԃ̂T���Ԃ̓X�g�b�v�E�H�b�`�ő��肵�A�x�e���Ԃ̗l�q���r�f�I�J�����ŎB�e�������̂�����Đ����A�������𒍎����Ă��鎞�ԁi�b���j���X�g�b�v�E�H�b�`�ő��肵���B
�B�ۑ�Ɏ��g��ł��炤
�@�@�@�@�@�@�x�e�I����A�ۑ�ɂ��Ă̐����Ə����ӂ��s���u���������ł��邾�������킹��v�Ƃ����ۑ�Ɏ��g��ł�������B
�i�����������e�j
��V����Q�Ɋւ��ẮA�u�����N�������ɉ����ĕ�V�����������܂��B�P������Ƃ�100�~��������V�̃O���[�h���オ��܂��B�ł��邾�������킹�Ă��������B�v�Ƌ������A��V�̗\���������B�܂����Q�Ƃ��A�u�����͖₢�܂���̂Ŏ��R�Ɏ��g��ł��������B�����ɗp�ӂ��Ă��邨��������g���Ă�����Ă��ǂ��ł��B���������������ꂽ��A�K�v�ȏ�ɐG���ꂽ�肷��ƁA���̎q���s���Ɋ����܂��̂ł����������s���͉������������B�Ȃ��ۑ�Ɏ��g��ł����������Ԃ͂T���Ԃł��B�T���o�����琺�������܂��B�ł̓����b�N�X���ėV��ł����Ă��������B�v�Ƌ������ۑ�Ɏ��g��ł�������B
�C����̂T���Ԃ̋x�e
�@�@�ۑ�I����A���̌���������������s�������������������Ă��܂��̂ň�U�x�e���Ƃ肽���Ɛ������A�T���Ԃ̋x�e���Ƃ����B
�@�@�@�i�����������e�j
�u���肪�Ƃ��������܂����B�T���o�߂��܂����̂ʼnۑ�I���Ƃ��܂��B�������������ɋ��͂������������̂ł����A���܂蒷���ԑ�����Ƃ��̎q�����Ă��܂��܂����A�T���ԋx�e���Ƃ�܂��傤�B�����Ɗւ���Ă��悢���A�������ւ��Ȃ��Ă����\�ł��̂ŁA���̃X�y�[�X���ɂ��Ă���������Ύ��R�ɉ������Ă��������Ă��悢�ł��B�������G���������R�Ɍ��Ă�����Ă����\�ł��B�v�Ƌ������T���Ԃ̋x�e���Ƃ����B�Ȃ��x�e���Ԃ̂T���Ԃ̓X�g�b�v�E�H�b�`�ő��肵�A�x�e���Ԃ̗l�q���r�f�I�J�����ŎB�e�������̂�����Đ����A�������𒍎����Ă��鎞�ԁi�b���j���X�g�b�v�E�H�b�`�ő��肵���B
�D����̎��⎆����
�@�x�e�I����A����̎��⎆�ɉ��Ă�������B
���⎆�̍\��
1.�Γ�����ʔF�m�ړx(���O���⎆�Ɠ���)
2.�Γ�����ʓ��@�Â��ړx(���O���⎆�Ɠ���)
�@3.����̋��͂Ɋւ��Ă̎���(���㎿�⎆�̂�)
�@�@���㓯���悤�ɓ����Ƃ������������������狦�͂��������ǂ�����₤������u���Ћ��͂������Ǝv���v�i�P�j�u�s�����������͂������Ǝv���v�i�Q�j�u���͂���͓̂���Ǝv���v�i�R�j�̂R���@�ʼn����߂��B
�@4.�����̊��z
�@�@�������I���Ă̊��z�����R�ɋL�q���Ă�������B
�E�f�u���[�t�B���O
����̎��⎆�ɉ��Ă��������A�ǂ������������ł�����������������B
�@�i�����������e�j
�u����Ŏ����̓��e�͂��ׂďI�����܂����B�����͂��肪�Ƃ��������܂��B�����ɂ��Ă̐������ɂ́A���ǂ����킹�鎞�ɂƂ������s�����Ƃ�̂��Ƃ�������������Ɛ������܂������A���͕�V��^����Ƃ������Ƃ���邱�Ƃ���̎������Ƃ̂��������ɂǂ������e����^����̂����݂�����ł����B�Ƃ������ƂŁA�������ɂ͕�V��^����Ɠ`���܂������A�c�O�Ȃ�����ۂɕ�V��^���邱�Ƃ͂ł��܂���B�\����܂���B�Q�����Ă�������������ɂ�����������グ�܂��B�v�Ɛ������A�팱�҂ɂ���̕i�����������A�ו��������đގ����Ă�������B
�Ȃ��l���݂͂�ꂽ���A�����S�̂�ʂ��ĂQ�O�����x�̎��Ԃ�v�����B
�����Q�y���ʁz
�P�D�������Ԃ̕ω�
�팱�҂��ۑ���s�����O�E���セ�ꂼ��̋x�e���Ԃɂ����āA�������𒍎��������Ԃ̕��ϒl�ƕW�������Z�o�����B���ʂ�Table 7 �Ɏ����B
�@�@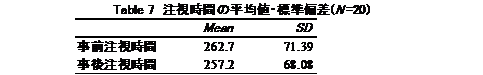
�Q�D�������ԂƑΓ�����ʓ��@�Â��Ƃ̊֘A
�@���O�E����ł̒������ԂƑΓ�����ʓ��@�Â��̊e���ʎړx�Ƃ̊֘A���݂邽�ߑ��W�����Z�o�����B���ʂ�Table 8 �Ɏ����B�Ȃ��A�Γ�����ʓ��@�Â��̊e���ʎړx�̕��ϒl�A�W������Table 9�Ɏ����B
�@�@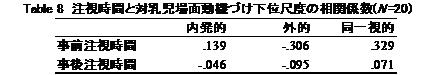
Table 8 �̂Ƃ���A�������ԂƊe���ʎړx�ɗL�ӂȑ��ւ݂͂��Ȃ������B���������O�̂������ƁA�O�I�����E���ꎋ�I�����ɂ͗L�ӂł͂Ȃ����A�����x�̑��ւ��݂�ꂽ�B
�R�D��V�i����E�Ȃ��j�ɂ����钍�����ԁE�e���ʎړx���_�̔�r
��V����Q�E�Ȃ��Q�ŁA���ʎړx���Ƃ̎��O����̓��_�̕ω��ƒ������Ԃ̕ω����������邽�߁A���ϒl�ƕW�������Z�o�����B���ʂ�Table 9�Ɏ����B���̌��ʁA�������Ԃɂ����ėL�ӂȍ����݂�ꂽ�B
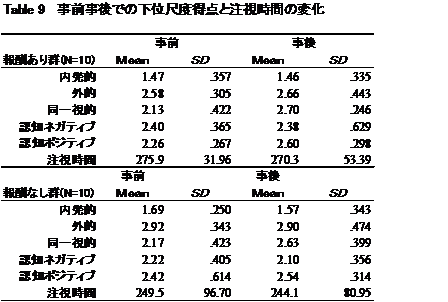
���Ɋe�w�W���]���ϐ��Ƃ����Q�i�Q�F��V����E�Ȃ��j�~�Q�i�����F���O�E����j�̂Q�v�����U���͂��s�����B�ȉ��Ɋe���U���͂̌��ʂ������B
�R-�P�j�������ԂƂ̊W
�����Ƃ̒������Ԃ��]���ϐ��Ƃ��A�Q(��V����E�Ȃ�)�~�Q(���O�E����)�̂Q�v�����U���͂��s�����B���ʂ�Figure 1�Ɏ����B
�@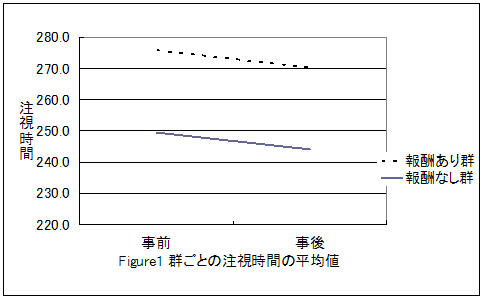
�@�Q�v�����U���͂̌��ʂ��A��V�i����E�Ȃ��j�A�����i���O�E����j�̎���ʂ݂͂��Ȃ������B�܂���V�i����E�Ȃ��j�Ǝ����i���O�E����j�̌��ݍ�p�݂͂��Ȃ������B
�R-�Q�j�����I���@�Â��Ƃ̊W
�Γ�����ʓ��@�Â��ړx�́u�����I���@�Â��v���]���ϐ��Ƃ��A�Q(��V����E�Ȃ�)�~�Q(���O�E����)�̂Q�v�����U���͂��s�����B���ʂ�Figure 2�Ɏ����B
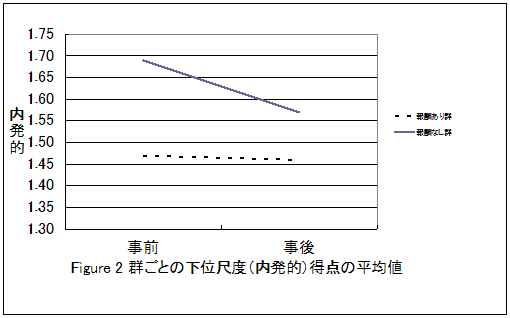
�Q�v�����U���͂̌��ʂ��A��V�i����E�Ȃ��j�A�����i���O�E����j�̎���ʂ݂͂��Ȃ������B�܂���V�i����E�Ȃ��j�Ǝ����i���O�E����j�̌��ݍ�p�݂͂��Ȃ������B
�R-�R�j�O�I�����Ƃ̊W
�Γ�����ʓ��@�Â��ړx�́u�O�I�����v���]���ϐ��Ƃ��A�Q(��V����E�Ȃ�)�~�Q(���O�E����)�̂Q�v�����U���͂��s�����B���ʂ�Figure 3�Ɏ����B
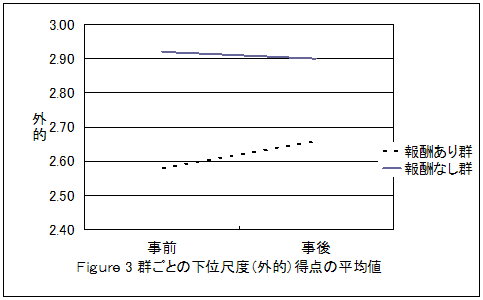
�Q�v�����U���͂̌��ʂ��A��V�i����E�Ȃ��j�A�����i���O�E����j�̎���ʂ݂͂��Ȃ������B�܂���V�i����E�Ȃ��j�Ǝ����i���O�E����j�̌��ݍ�p�݂͂��Ȃ������B
�R-�S�j���ꎋ�I�����Ƃ̊W
�Γ�����ʓ��@�Â��ړx�́u���ꎋ�I�����v���]���ϐ��Ƃ��A�Q(��V����E�Ȃ�)�~�Q(���O�E����)�̂Q�v�����U���͂��s�����B���ʂ�Figure 4�Ɏ����B
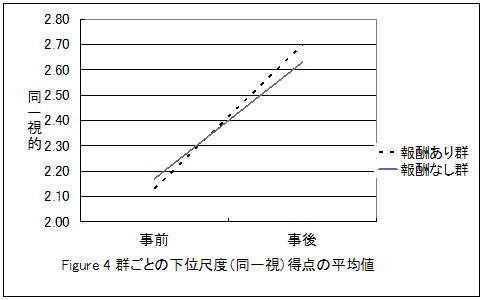
�Q�v�����U���͂̌��ʂ��A��V�i����E�Ȃ��j�̎���ʂ݂͂��Ȃ������������i���O�E����j�̎���ʂ��݂�ꂽ�iF(1,18)=19.44 , p<.01�j�B�܂���V�i����E�Ȃ��j�Ǝ����i���O�E����j�̌��ݍ�p�݂͂��Ȃ������B
�R-�T�j�F�m�l�K�e�B�u�Ƃ̊W
�Γ�����ʔF�m�ړx�́u�F�m�l�K�e�B�u�v���]���ϐ��Ƃ��A�Q(��V����E�Ȃ�)�~�Q(���O�E����)�̂Q�v�����U���͂��s�����B���ʂ�Figure 5 �Ɏ����B
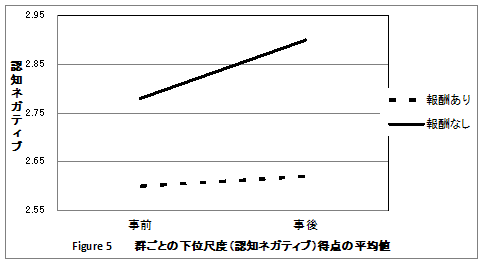
�Q�v�����U���͂̌��ʂ��A��V�i����E�Ȃ��j�A�����i���O�E����j�̎���ʂ݂͂��Ȃ������B�܂���V�i����E�Ȃ��j�Ǝ����i���O�E����j�̌��ݍ�p�݂͂��Ȃ������B
�R-�U�j�F�m�|�W�e�B�u�Ƃ̊W
�Γ�����ʔF�m�ړx�́u�F�m�|�W�e�B�u�v���]���ϐ��Ƃ��A�Q(��V����E�Ȃ�)�~�Q(���O�E����)�̂Q�v�����U���͂��s�����B���ʂ�Figure 6 �Ɏ����B
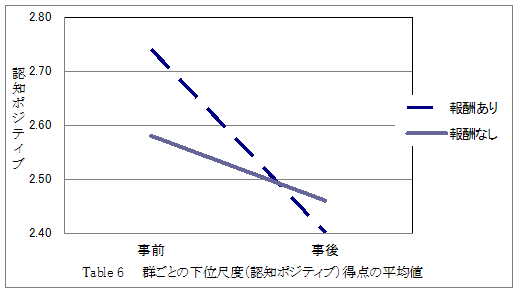
�Q�v�����U���͂̌��ʂ��A��V�i����E�Ȃ��j�̎���ʂ݂͂��Ȃ��������A�����i���O�E����j�̎���ʂ݂͂�ꂽ�iF(1,18)=8.74 p<.01
�j�B�܂���V�i����E�Ȃ��j�Ǝ����i���O�E����j�̌��ݍ�p�݂͂��Ȃ������B
�S�D��V�i����E�Ȃ��j�ɂ����鍡��̋��͓x�̔�r
����̋��͂Ɋւ��ČQ�ɂ��Ⴂ���������邽����������s�����B���ʂ�Table 10�Ɏ����B
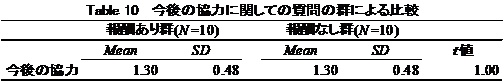
Table 10����V�i����E�Ȃ��j�ŗL�ӂȍ��݂͂��Ȃ������B
�����Q�y�l�@�z
�����Q�ł͑Γ�����ʂɁA��V�\�����s�����Ƃł��̌�̓����Ɗւ�邱�Ƃւ̓����I���@�Â����ǂ̂悤�ɕω�����̂����������邱�Ƃ�ړI�Ƃ����B���O�E����ł̓����𒍎����Ă��鎞��(�b)�ƁA�Γ�����ʂ̓��@�Â��Ɋւ��āu�����I���@�Â��v�E�u�O�I�����v�E�u���ꎋ�I�����v�̂R�̎ړx�Ɓu����̋��͈ӎu�̓x�����v�ւ̉@�Â��̎w�W�Ƃ��Č��������B�܂��Γ�����ʔF�m�Ɋւ��Ă���V�i����E�Ȃ��j�̈Ⴂ�ɂ��e�������������B
�P�D�������ԂƑΓ�����ʓ��@�Â��̊֘A
���O�E����ł̒������ԂƑΓ�����ʓ��@�Â��̊e���ʎړx�Ƃ̊֘A���݂邽�ߑ��W�����Z�o�����iTable 8�j�B���̌��ʒ������ԂƑΓ�����ʓ��@�Â��̊e���ʎړx�ŗL�ӂȑ��ւ݂͂��Ȃ������B���������O�̋x�e���Ԃɂ����Ă̒������ԂƁA�O�I�����E���ꎋ�I�����ɂ͒����x�̑��ւ��݂�ꂽ�B���O�̋x�e���Ԃɂ����Ă̒������ԂƓ����I���@�Â��Ƃ̊Ԃł͖����ւɋ߂��A���ꎋ�I�����ł͒����x�̐��̑��ւ��݂�ꂽ���Ƃ���A�����I���@�Â��͏��킹�ĕω�������̂ł���A���̏�̂������낳�ɍ��E����₷���A��т����X��������ꂸ�����ւɋ߂����ʂƂȂ�A�܂����ꎋ�I�����͎��Ȃ̖ڕW�I�ȊT�O�ł���A��ѐ���������̂Ƃ�����B���������āA�����x�̑��ւ�����ꂽ�ƍl������B�܂����O�̒������ԂƊO�I�����Ƃ̊ԂŒ����x�̕��̑��ւ��݂�ꂽ�̂́A�������Ԃ�����I���@�Â��̎w�W�Ƃ����̂őÓ��Ȍ��ʂł���Ƃ�����B
�Q�D��V�̌��ʂɂ���
�Q-�P�j��V�̂������ƍ���̋��͓x�̊֘A
����̋��͂̓x�����Ɋւ��āA�Q�ɂ��Ⴂ���������邽����������s����(Table 10)�B���̌��ʍ���̋��͂̓x�����Ɋւ��ĕ�V�̂������ɂ��L�ӂȍ��݂͂��Ȃ������B���̂��Ƃ����V�\���̑��삪�u����܂�������肽���v�Ƃ����悤�ȓ����I���@�Â���������ʂ݂͂��Ȃ������Ƃ�����B
�Q-�Q�j�������Ԃւ̉e��
��V�̈Ⴂ�ɂ������I���@�Â��̕ω����݂邽�������Ƃ̒������Ԃ��]���ϐ��Ƃ��A�Q(��V����E�Ȃ�)�~�Q(���O�E����)�̂Q�v�����U���͂��s����(Figure 1)�B���̌��ʕ�V�i����E�Ȃ��j�A�����i���O�E����j�̎���ʂ݂͂��Ȃ������B�܂���V�i����E�Ȃ��j�Ǝ����i���O�E����j�̌��ݍ�p�݂͂��Ȃ������B�������A��V�̈Ⴂ�ɂ�����炸�A���O���セ�ꂼ��ɂ����ē����Ƃ�����������Ԃ̕��ϒl(Table 7 �Q��)�̌��ʂƂ��킹�Ă݂Ă��A�����Ƃ�����鎞�Ԃ������������Ƃ�������B��V�i����E�Ȃ��j�ɂ�����炸�����Ƃ�����鎞�Ԃ����������̂́A�ۑ���s���ۂɁu�ł��邾���������������킹�Ă��������v�Ƃ������������邱�ƂŁA�]�����O�����������߁A�팱�҂̎����I�Ȃ�������W���A�ۑ�I����ɂ��e�����y�ڂ��A����ł̒������Ԃ��������ƍl������B�]�����O�Ƃ́A�����̍s�������҂���ے�I�ɕ]������邩������Ȃ��A���ۂ���邩������Ȃ��ƁA���҂���̕]���������ӎ����A�s���������Ƃł���i���R, 2005�j�B����ɒ��R�i2005�j�ł́A�]�����ӎ����s���������Ƃɂ���āA���҂̖ڂɂǂ̂悤�ɉf�邩�ɏd�_���������I���E�s�����Ƃ�A���Ȃ̕\�o��}�����Ă��܂��\��������Ƃ��Ă���B�{�����ɂ����Ă��A�u���������ł��邾�������킹�Ăق����v�Ƌ����������Ƃ��A�팱�҂ɑ��āu�킹���Ȃ�������ے�I�ɕ]������邩������Ȃ��v�Ƃ����悤�ȕs�����������邱�ƂɂȂ�A���̌��ʎ������Ƃ������s����}�������Ƃ������Ƃ����������B
�Q-�R�j�����I���@�Â��ւ̉e��
��V�̈Ⴂ�ɂ�鉺�ʎړx���Ƃ̓��_�̕ω����݂邽�߁A�Γ�����ʓ��@�Â��́u�����I���@�Â��v���]���ϐ��Ƃ��A�Q(��V����E�Ȃ�)�~�Q(���O�E����)�̂Q�v�����U���͂��s����(Figure 2)�B���̌��ʕ�V�i����E�Ȃ��j�A�����i���O�E����j�̎���ʂ݂͂��Ȃ������B�܂���V�i����E�Ȃ��j�Ǝ����i���O�E����j�̌��ݍ�p�݂͂��Ȃ������B���̌��ʂ���A�Γ�����ʂɂ����Ă̕�V�̗\���ɂ������I���@�Â��̑����I���ʂ݂͂��Ȃ������Ƃ�����B����(2003)�́A�O�I��V�̑����I���ʂ͌��肳�ꂽ��ʂł̂N������̂ł���Ƃ��Ă���B��̓I�ɂ́A�����I���@�Â��������҂ɂ͐����ɂ����A��V�̊��҂��Ȃ���ΐ����ɂ����A��V��^����҂Ɨ^������҂̊W���ǍD�ł���ΐ����ɂ����A�Ȃǂł���B�{�����̔팱�҂͓����Ƃ����������ɐϋɓI�ɋ��͂��Ă��ꂽ�҂ł��������߁A�����Ƃ�����邱�Ƃɑ��Ă̓����I���@�Â��������\��������A��V�\���ɂ������I���@�Â��̑����I���ʂ��݂��Ȃ������ƍl������B�����ɁA�����Ƃ�����邱�Ƃɑ��ē����I���@�Â��������҂́A�u��V�邽�߂ł͂Ȃ��A�����Ƃ������̂��y�������炩����낤�v�Ƃ����F�m�ł���ƍl�����邽�߁A��V�̊��҂����Ȃ����낤�B���̌��ʁA��V�\���ɂ������I���@�Â��̑����I���ʂ��݂��Ȃ������Ƃ������Ƃ��l������B
�Q-�S�j�O�I�����ւ̉e��
��V�̈Ⴂ�ɂ�鉺�ʎړx���Ƃ̓��_�̕ω����݂邽�߁A�Γ�����ʓ��@�Â��́u�O�I�����v���]���ϐ��Ƃ��A�Q(��V����E�Ȃ�)�~�Q(���O�E����)�̂Q�v�����U���͂��s����(Figure 3)�B���̌��ʁA��V�i����E�Ȃ��j�A�����i���O�E����j�̎���ʂ݂͂��Ȃ������B�܂���V�i����E�Ȃ��j�Ǝ����i���O�E����j�̌��ݍ�p�݂͂��Ȃ������B���̌��ʂ���O�I�����ƒ������Ԃɂ͊W���Ȃ��Ƃ������Ƃ������ꂽ�B�@
�Q-�T�j���ꎋ�I�����ւ̉e��
��V�̈Ⴂ�ɂ�鉺�ʎړx���Ƃ̓��_�̕ω����݂邽�߁A�Γ�����ʓ��@�Â��́u���ꎋ�I�����v���]���ϐ��Ƃ��A�Q(��V����E�Ȃ�)�~�Q(���O�E����)�̂Q�v�����U���͂��s����(Figure 4)�B���̌��ʕ�V�i����E�Ȃ��j�̎���ʂ݂͂��Ȃ������������i���O�E����j�̎���ʂ��݂�ꂽ�B�܂���V�i����E�Ȃ��j�Ǝ����i���O�E����j�̌��ݍ�p�݂͂��Ȃ������B���Q�Ƃ��ɓ��ꎋ�I�������_���㏸�����̂́A���ۂɓ����Ƃ�������Ă݂āA�����ɑ��ē����Ƃ�����邱�Ƃւ̕K�v����d�v�������������߂ł���ƍl������B���ǂ��Ƃ̂������̌������ǂ����֗^����e�����݂������ɂ����āA����E�����E�g�c�i2008�j�́A���ړI�Ȃ������̌��́A�������ǂ��������Ƃ̃C���[�W�����߁A���ǂ�����Ă�C���[�W�������炷���Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B���̂��Ƃ���A������ʂœ����Ƃ�����������Ƃ��A�������ǂ�����������z�������邱�ƂɂȂ���A���ǂ��Ƃ�����邱�Ƃ̉��l�����܂����̂ł͂Ȃ����ƍl������B
�Q-�U�j�F�m�l�K�e�B�u�ւ̉e��
��V�̈Ⴂ�ɂ�鉺�ʎړx���Ƃ̓��_�̕ω����݂邽�߁A�Γ�����ʔF�m�́u�F�m�l�K�e�B�u�v���]���ϐ��Ƃ��A�Q(��V����E�Ȃ�)�~�Q(���O�E����)�̂Q�v�����U���͂��s���� (Figure 5 )�B���̌��ʕ�V�i����E�Ȃ��j�A�����i���O�E����j�̎���ʂ݂͂��Ȃ������B�܂���V�i����E�Ȃ��j�Ǝ����i���O�E����j�̌��ݍ�p�݂͂��Ȃ������B����������ɂ����Ă͗��Q�Ƃ��ɓ��_�����������B���̌��ʂ���A���ۂɓ����Ƃ�����邱�Ƃ��o�����邱�Ƃő�ς����������A�����O���l�K�e�B�u�ɂȂ����Ƃ�����B�@
�Q-�V�j�F�m�|�W�e�B�u�ւ̉e��
��V�̈Ⴂ�ɂ�鉺�ʎړx���Ƃ̓��_�̕ω����݂邽�߁A�Γ�����ʔF�m�́u�F�m�|�W�e�B�u�v���]���ϐ��Ƃ��A�Q(��V����E�Ȃ�)�~�Q(���O�E����)�̂Q�v�����U���͂��s���� (Figure 6 )�B���̌��ʁA��V�i����E�Ȃ��j�̎���ʂ݂͂��Ȃ��������A�����i���O�E����j�̎���ʂ݂͂�ꂽ�B�܂���V�i����E�Ȃ��j�Ǝ����i���O�E����j�̌��ݍ�p�݂͂��Ȃ������B���̌��ʂ��玖��ɂ����Ă͗��Q�Ƃ��ɓ����Ƃ�����邱�Ƃɑ��āA�|�W�e�B�u�ł͂Ȃ��Ȃ����Ƃ�����B�܂����㎿�⎆�ƂƂ��ɋL�����Ă�����������̊��z�ɂ��ƁA�����̔팱�҂��u�����Ɛڂ���͓̂���v��u�����Ə킹��͓̂���v�u�����̋C������ǂݎ��͓̂���v�Ƃ��������Ƃ��q�ׂĂ����B�܂���ۂɓ����Ƃ�������Ă݂āA�v���悤�ɏ킹���Ȃ�������A���܂������̋C�������ǂݎ��Ȃ�������Ƃ������Ƃ��o�����A�����Ƃ�����邱�Ƃ̓�����ς��������������߁A�|�W�e�B�u�ł͂Ȃ��Ȃ����ƍl������B����i2001�j�͍��Z���ɂ��āA�ۈ�̌��w�K�O�̐Ԃ����C���[�W�͍m��I�ŗc���C���[�W�͔ے�I���������A�̌���ɂ͐Ԃ����C���[�W�͍m��I�E�ے�I�������������A�c���C���[�W�͍m��I���������ے�I�����������ƕ��Ă���B�{�����ł́A���������P�O�������ł��������߁A�팱�҂ɐԂ����Ƃ��ĂƂ炦���Ă����\���������A��s�����Ɠ��l�ɂ����������ے�I�C���[�W�����������̂ł͂Ȃ����ƍl������B