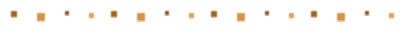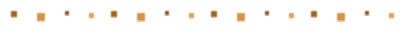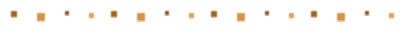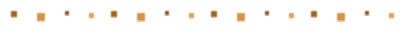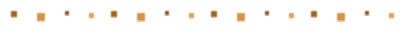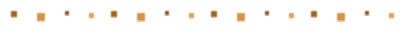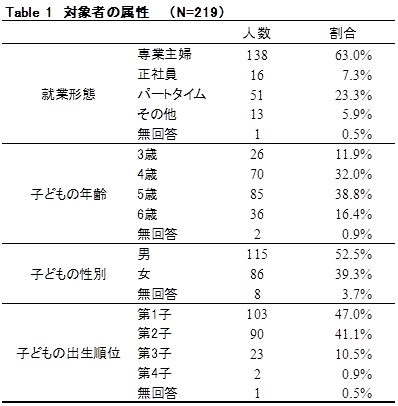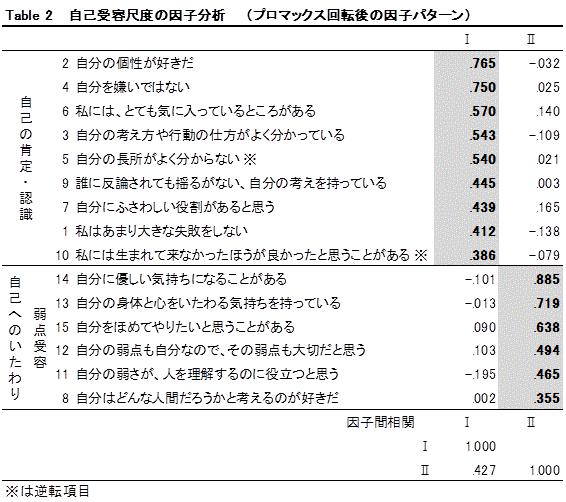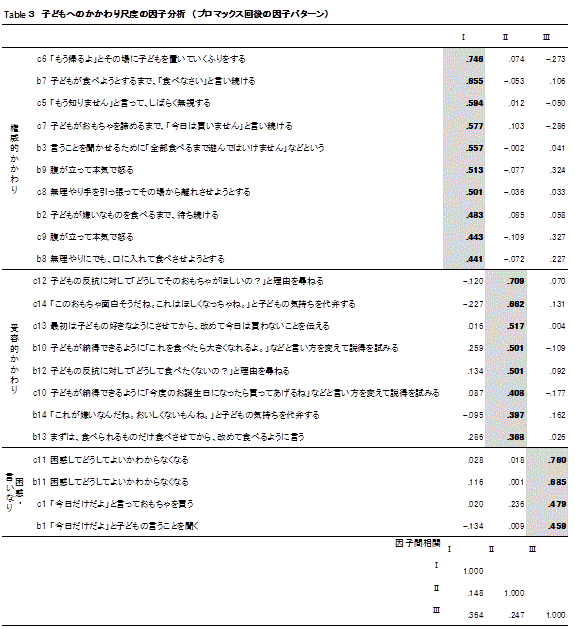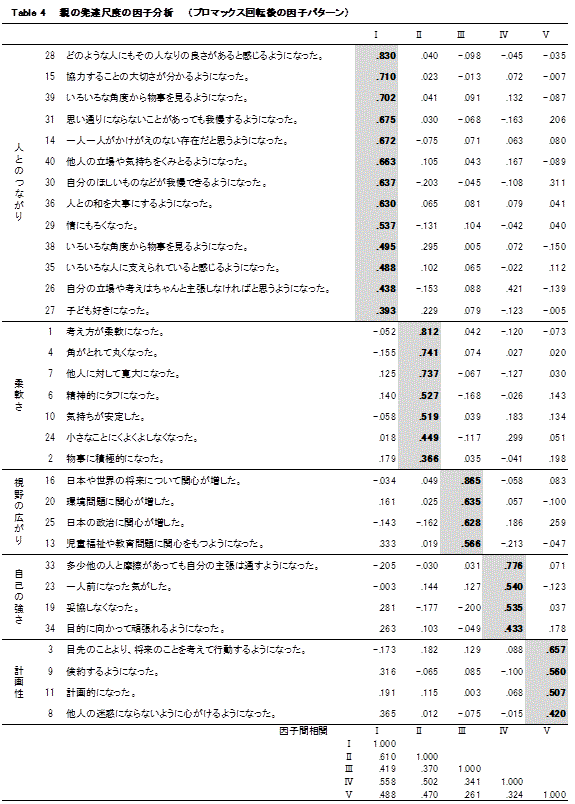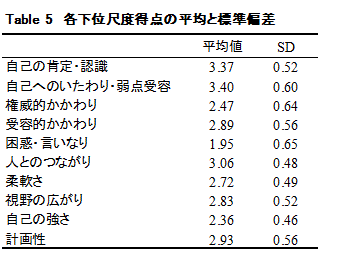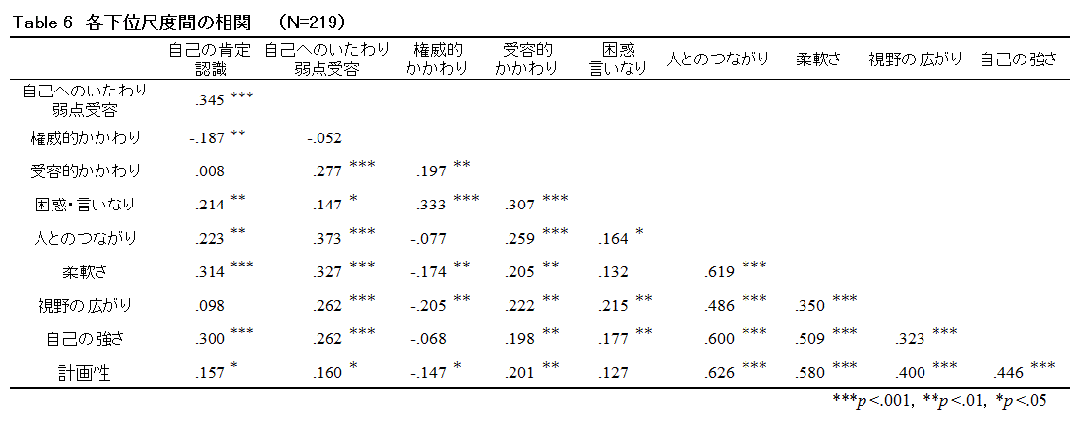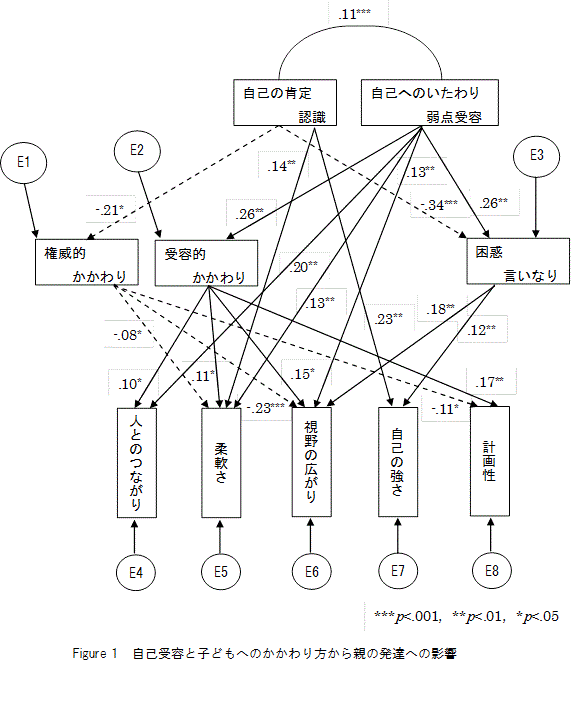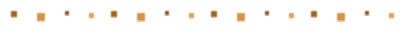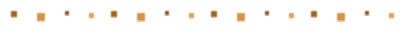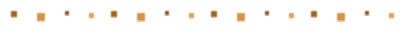
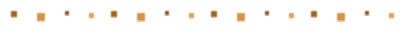
結果
【結果】
1.調査対象者の属性
分析対象者219名の属性をTable 1に示す。
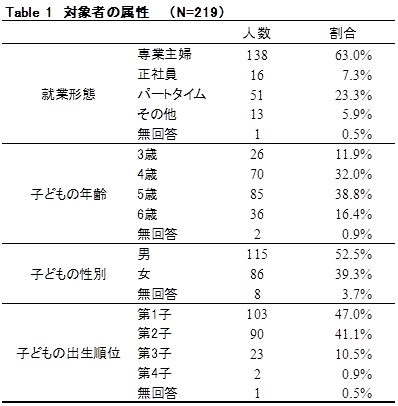
母親の就業形態は、専業主婦が138名で63.0%と半数以上であり、ついでパートタイムが51名で23.3%であった。子どもの年齢は3歳が26名、4歳が70名、5歳が85名、6歳が36名であり、年中児から年長児クラスの子どもが多かった。また、子どもの性別は男児が115名で52.5%、女児が85名で39.3%であった。さらに、子どもの出生順位は、第1子が103名、第2子が90名であり、8割以上を占めていた。
2.尺度構成
(1)自己受容
自己受容の構成要素を検討するために、自己受容尺度15項目について、主因子法による因子分析をおこなった。それぞれの要素に相関が想定されるため、プロマックス回転法を用いた。先行研究にならって3因子を仮定したが、因子を構成する項目数と、解釈可能性を考慮した上で、2因子解を抽出した。その結果をTable 2に示す。
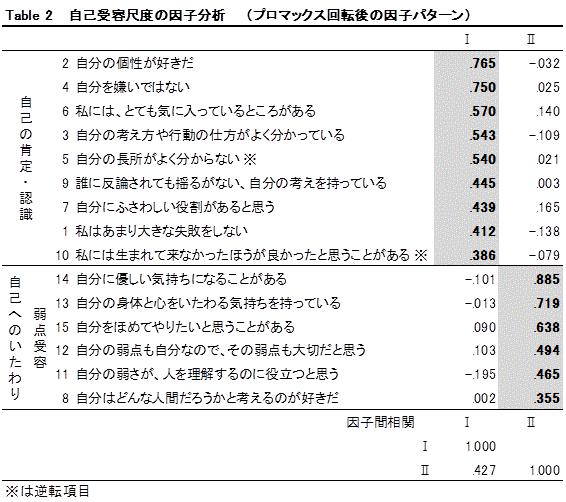
第1因子は、「自分の個性が好きだ」、「私にはとても気に入っているところがある」、「自分の考え方や行動の仕方がよく分かっている」のように、自分自身を肯定するような項目や、自分自身についてどう認識しているかという項目から成り立っていることから、「自己の肯定・認識」と命名した。第2因子は、「自分に優しい気持ちになることがある」、「自分の身体と心をいたわる気持ちを持っている」、「自分の弱点も自分なので、その弱点も大切だと思う」のように、自分のことをいたわる気持ちや弱点を受容しているという項目から成り立っているため、「自己へのいたわり・弱点受容」と命名した。
因子ごとのα係数は、第1因子.77、第2因子.74であった。
(2)子どもへのかかわり方
子どもへのかかわり方の構成要素を検討するために、子どもへのかかわり尺度の食事場面と買い物場面それぞれ14項目、合計28項目について、主因子法による因子分析をおこなった。それぞれの要素に相関が想定されるため、プロマックス回転法を用いた。解釈可能性を考慮した上で、3因子解を抽出した。その結果、十分な因子負荷量を示さなかった6項目を分析から除外し、残りの22項目に対して再度、主因子法・プロマックス回転による因子分析をおこなった。この結果をTable 3に示す。
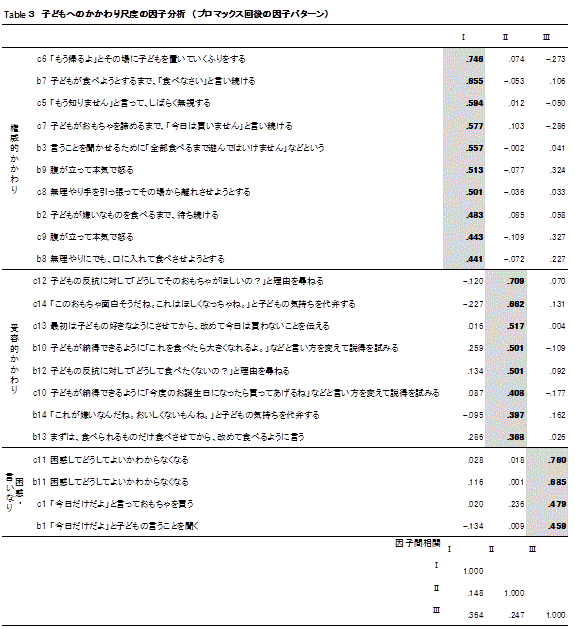
第1因子は、「『もう帰るよ』とその場に子どもを置いていくふりをする」、「子どもが食べようとするまで『食べなさい』と言い続ける」、「『もう知りません』と言って、しばらく無視する」のように、子どもの気持ちを考慮せず、権威的にかかわる項目から成り立っているため、「権威的かかわり」と命名した。第2因子は、「子どもの反抗に対して『どうしてそのおもちゃがほしいの?』と理由を尋ねる」、「『このおもちゃ面白そうだね。これはほしくなっちゃうよね。』と子どもの気持ちを代弁する」、「最初は子どもの好きなようにさせてから、改めて今日は買わないことを伝える」のような、子どもの気持ちを受け止めながらかかわる項目から成り立っているため、「受容的かかわり」と命名した。第3因子は、「困惑してどうしてよいかわからなくなる」、「『今日だけだよ』と言って、おもちゃを買う」という項目から成り立っているため、「困惑・言いなり」と命名した。
因子ごとのα係数は、第1因子.83、第2因子.75、第3因子.71であった。
(3)親の発達
柏木・若松(1994)にならって、親の発達尺度41項目について、5因子を仮定し、主因子法による因子分析をおこなった。それぞれの要素に相関が想定されるため、プロマックス回転法を用いた。その結果、十分な因子負荷量を示さなかった9項目を分析から除外し、残りの32項目に対して、再度、主因子法・プロマックス回転による因子分析をおこなった。この結果をTable 4に示す。
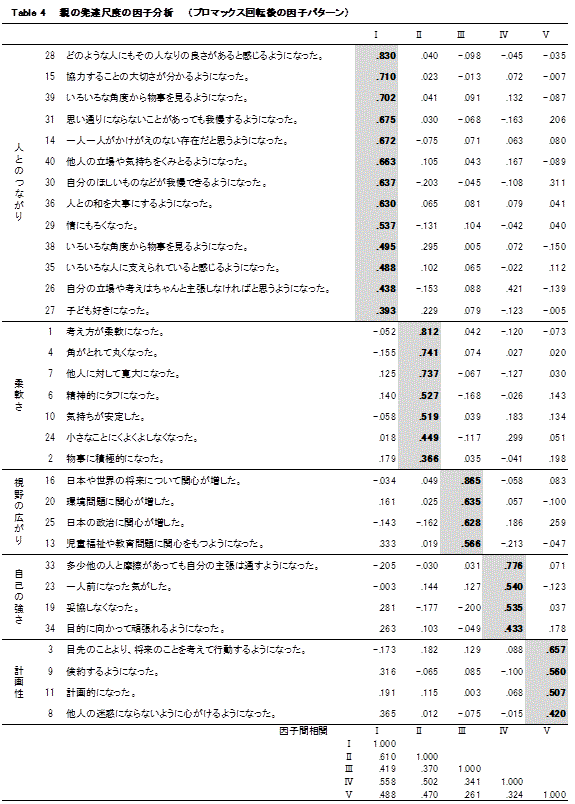
第1因子は、「どのような人にもその人なりの良さがあると感じるようになった」、「協力することの大切さが分かるようになった」のように、人との関係における変化を表すような項目から成り立っているため、「人とのつながり」と命名した。第2因子は、「考え方が柔軟になった」、「角がとれて丸くなった」のような、精神的な成長を表しており、先行研究の「柔軟さ」の因子の項目とも一致しているため、「柔軟さ」と命名した。第3因子は、「日本や世界の将来について関心が増した」、「環境問題に関心が増した」のような、自分の周囲のことへ関心の広がりを表す項目から成り立っており、先行研究の「視野の広がり」の因子の項目とも一致していることから、「視野の広がり」と命名した。第4因子は、「多少他の人との摩擦があっても、自分の主張は通すようになった」、「妥協しなくなった」のような項目から成り立っているため、「自己の強さ」と命名した。第5因子は、「目先のことより、将来のことを考えて行動するようになった」、「倹約するようになった」のような、将来を見据えて計画的になったという変化を表す項目から成り立っているため、「計画性」と命名した。
因子ごとのα係数は、第1因子.91、第2因子.83、第3因子.80、第4因子.71、第5因子.80であった。
3.それぞれの下位尺度得点の平均と標準偏差
因子分析の結果から、自己受容の下位尺度である「自己の肯定・認識」、「自己へのいたわり・弱点受容」、子どもへのかかわり方の下位尺度である「権威的かかわり」、「受容的かかわり」、「困惑・言いなり」、親の発達の下位尺度である「人とのつながり」、「柔軟さ」、「視野の広がり」、「自己の強さ」、「計画性」のそれぞれの項目について平均を算出し、各因子の下位尺度得点とした。各下位尺度得点の平均と標準偏差をTable 5に示す。
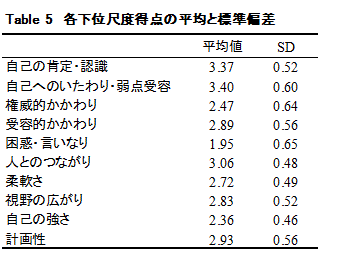
4.下位尺度間の関連
自己受容、子どもへのかかわり方、親の発達のそれぞれの下位尺度間の関連をTable 6に示す。
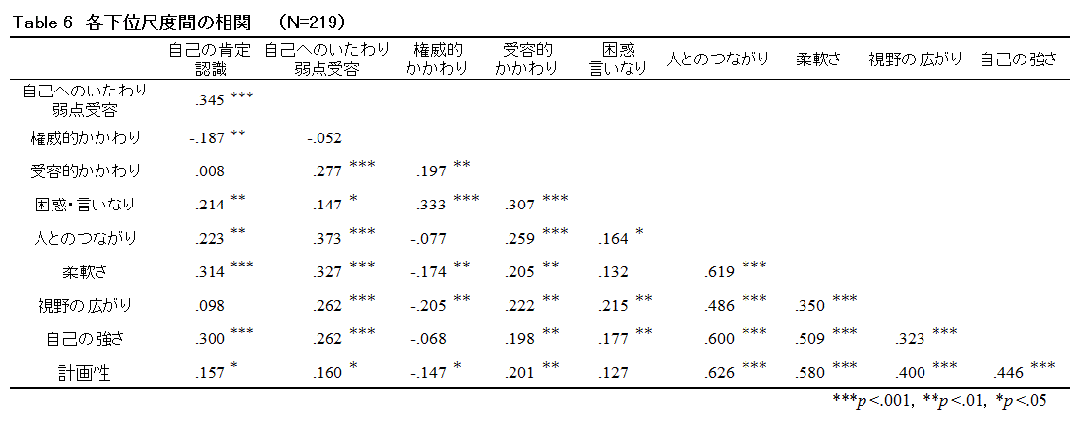
(1)各尺度内での下位尺度間の関連
Table 6より、自己受容の下位尺度である「自己の肯定・認識」と「自己へのいたわり・弱点受容」の間には、有意な正の相関がみられた。次に、子どもへのかかわりの下位尺度間の関連については、「権威的かかわり」と「受容的かかわり」、「困惑・言いなり」の間に有意な正の相関、「受容的かかわり」と「困惑・言いなり」の間に有意な正の相関がみられた。そして、親の発達の下位尺度間の関連については、すべての下位尺度間に有意な正の相関がみられた。
(2)自己受容と子どもへのかかわりの下位尺度の関連
Table 6より、自己受容の下位尺度である「自己の肯定・認識」について、「権威的かかわり」、「困惑・言いなり」それぞれとの間に有意な負の相関がみられた。また、「自己へのいたわり・弱点受容」については、「受容的かかわり」、「困惑・言いなり」それぞれとの間に有意な正の相関がみられた。
(3)自己受容と親の発達の下位尺度の関連
Table 6より、自己受容の下位尺度である「自己の肯定・認識」について、「人とのつながり」、「柔軟さ」、「自己の強さ」、「計画性」のそれぞれとの間に有意な正の相関がみられた。また、「自己へのいたわり・弱点受容」については、「人とのつながり」、「柔軟さ」、「視野の広がり」、「自己の強さ」、「計画性」のすべての下位尺度との間に、有意な正の相関がみられた。
(4)子どもへのかかわり方と親の発達の下位尺度の関連
Table 6より、子どもへのかかわり方の下位尺度である「権威的かかわり」について、「柔軟さ」、「視野の広がり」、「計画性」のそれぞれとの間に有意な負の相関がみられた。次に「受容的かかわり」については、「人とのつながり」、「柔軟さ」、「視野の広がり」、「自己の強さ」「計画性」のすべての下位尺度との間に、有意な正の相関がみられた。そして「困惑・言いなり」については、「人とのつながり」、「視野の広がり」、「自己の強さ」のそれぞれとの間に、有意な正の相関がみられた。
5.共分散構造分析による検討
親の発達への影響を検討するために、自己受容、子どもへのかかわり方を独立変数、親の発達を従属変数として、共分散構造分析をおこなった。
その結果、十分なモデル適合度が得られたモデルを採用し、Figure 1に示す。
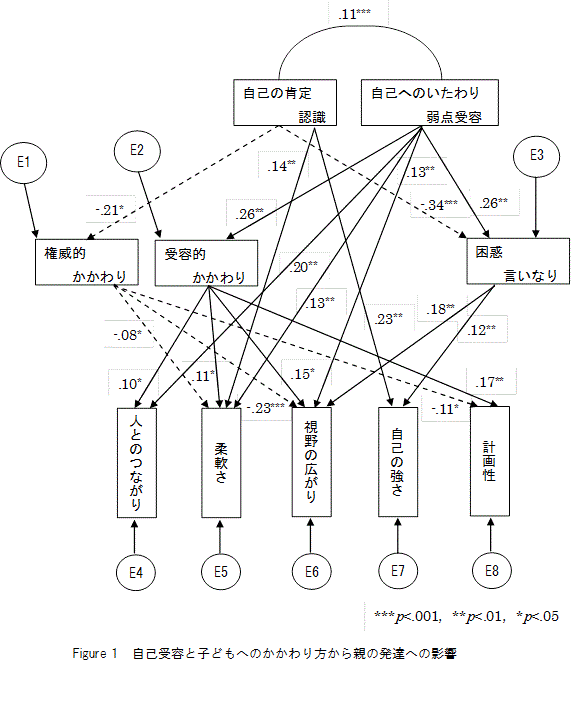
(1)自己受容から子どもへのかかわり方への影響
Figure 3より、自己受容の下位尺度である「自己の肯定・認識」から子どもへのかかわり方への影響については、「権威的かかわり」と「困惑・言いなり」へ有意な負の影響がみられた。また、「自己へのいたわり・弱点受容」からは、「受容的かかわり」と「困惑・言いなり」へ有意な正の影響がみられた。
(2)自己受容から親の発達への影響
Figure 3より、自己受容の下位尺度である「自己の肯定・認識」から親の発達への直接の影響としては、「柔軟さ」と「自己の強さ」へ有意な正の影響がみられた。また、「自己へのいたわり・弱点受容」からは、「人とのつながり」、「柔軟さ」、「視野の広がり」へ有意な正の影響がみられた。
(3)子どもへのかかわり方から親の発達への影響
Figure 3より、子どもへのかかわり方の下位尺度である「権威的かかわり」から親の発達への影響については、「柔軟さ」、「視野の広がり」、「計画性」へ有意な負の影響がみられた。また、「受容的かかわり」からは、「人とのつながり」、「柔軟さ」、「視野の広がり」、「計画性」へ有意な正の影響がみられた。そして、「困惑・言いなり」からは、「視野の広がり」と「自己の強さ」へ有意な正の影響がみられた。
←back