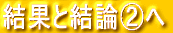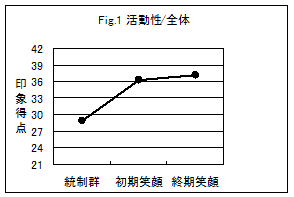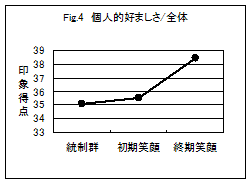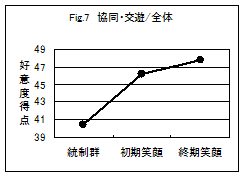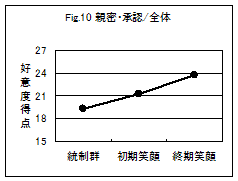Ⅴ 結果
1)各条件の被験者の差の検定
刺激人物A、刺激人物Bの笑顔表出条件を独立変数とし、1つ目のVTRの印象を測定した特性形容詞尺度の項目を合計したものの平均を従属変数として、一要因の分散分析をそれぞれ行った。その結果、刺激人物A、刺激人物Bの各笑顔表出条件群間に有意差は認められなかった。
2)VTRの不自然さのチェック
2つ目のVTRが不自然なものか否か、また笑顔表出3条件のVTRの不自然さの度合いに差があったかどうかを検討する目的で2つ目のVTRの印象を測定するための特性形容詞尺度に付け加えた<自然な-不自然な>の項目をみた。刺激人物A、刺激人物Bの笑顔表出条件を独立変数とし、質問項目の得点を従属変数とした一要因の分散分析をそれぞれ行った。
刺激人物Aにおいては笑顔表出条件間に有意差(F(2,91)=3.69, p<0.05)が見られた。その後Tukey
HSDにより多重比較を行ったところ、初期笑顔表出条件<終期笑顔表出条件の間に有意差(p<0.05)が認められた。刺激人物Bにおいては笑顔表出条件間に有意差は見られなかった。
また、刺激人物条件を独立変数とし、質問項目の得点を従属変数として一要因の分散分析を行ったところ、有意差(F(1,230)=36.67, p<0.05)が見られた。尚、不自然度の平均は刺激人物A:5.17>刺激人物B:4.23であり、得点が高いほど不自然に近づくことを示す。刺激人物Bの平均を見ると、中間値の4付近なので、刺激人物BのVTRは被験者に特に不自然な印象を与えていないことがわかる。(Table 1参照)
また、前述したように実験中の様子として刺激人物Aの終期笑顔表出条件のVTRを見た被験者群のみから笑い声が出されたことは、要因の統制という点で問題がある。このことも考慮し、これ以降の分析では刺激人物Bのデータのみを用いて分析を行うこととする。
3)因子分析
2つ目のVTRについての『特性形容詞尺度』と『対人魅力尺度』について因子分析を行った。
①『特性形容詞尺度』について
<自然な―不自然な>の項目を除く20項目について、因子数を2因子として主因子法・バリマックス回転による因子分析を行った。因子負荷が両因子について低かった、または高かった5項目を削除し、最終的な回転後の因子行列をTable2に示した。第1因子は、7.<社交的な―非社交的な>、12.<うきうきした-沈んだ>などに対して負荷量が高く、「活動性」に関する因子とした。第2因子は、14.<感じのよい-感じのわるい>、2.<人のよい―人の悪い>などに対して負荷量が高く、「個人的好ましさ」に関する因子とした。第1因子、第2因子の信頼性係数を算出したところ、それぞれα=0.88、α=0.87と高い値を示した。また、それぞれの因子の項目ごとに合計したものを「印象得点」とする。
②『対人魅力尺度』について
20項目の質問項目について、因子数を2因子として一般化された最小2乗法、バリマックス回転を用いた因子分析を行った。両因子ともに因子負荷が低かった、または高かった2項目を削除し、最終的な回転後の因子行列をTable3に示した。藤森(1980)を参考にして、因子名を付けた。第1因子は「一緒に遊びたい。」「一緒に専門書を読みたい。」などの項目に対して負荷量が高く、「協同・交遊」に関する因子とした。また、第2因子は「親しみを感じる。」「社会的に望ましい。」などに対して負荷量が高く、「親密・承認」に関する因子とした。第1因子、第2因子の信頼性係数を算出したところ、それぞれα=0.95、α=0.85と高い値を示した。また、それぞれの因子の項目ごとに合計したものを「好意度得点」とする。
4)認知的熟慮性について
刺激人物BのVTRを評定した全被験者の『認知的熟慮性―衝動性尺度』10項目を合計したものの平均を算出したところ、27.4点であった。平均点より得点の高かったものを熟慮群、同じく低かったものを衝動群とした。熟慮群の平均点は31.99点、衝動群の平均点は22.8点であった。その結果、各条件の被験者の人数、印象得点、好意度得点はTable4のようになった。尚、認知的熟慮性-衝動性尺度は4段階評定で10項目から成る尺度であるので、合計得点は10点以上40点以下の間をとる。
5) 笑顔の主効果について
笑顔表出(3)×被験者の性(2)×認知的熟慮性-衝動性(2)の三要因の分散分析を行ったところ、印象評定及び好意度評定の全ての因子次元において笑顔の主効果が見られた。
①印象評定(特性形容詞対尺度)
ⅰ)活動性
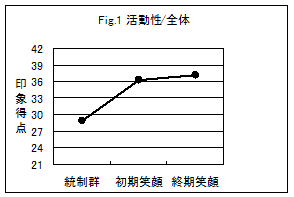
笑顔表出の主効果が有意であり(F(2,126)=39.08, p<0.05)、Tukey HSDによる多重比較の結果、統制群<初期笑顔表出群(統制群よりも初期笑顔表出群の方が印象得点が高かったことを示す。以下同様)、統制群<終期笑顔表出群の間で有意な差(p<0.05)が見られた。(Fig.1参照) よって、活動性の因子においては、笑顔表出のない場合よりもある場合の方がよりポジティブな印象をもたれたことが示された。しかし、笑顔の表出順序のちがいによる有意な差は得られなかった。
ⅱ)個人的好ましさ
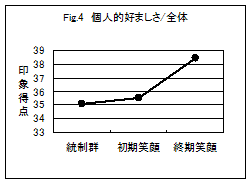
笑顔表出の主効果が有意であり(F(2,126)=3.96, p<0.05)、Tukey HSDによる多重比較の結果、統制群<終期笑顔表出群、初期笑顔表出群<終期笑顔表出群の間に有意差(p<0.05)が見られた。(Fig.4参照)これらのことより、個人的好ましさの因子においては笑顔表出のない場合や初期に笑顔を表出した場合よりも終期に笑顔を表出した場合の方がよりポジティブな印象を持たれることが示された。
②好意度評定(対人魅力尺度)
ⅰ)協同・交遊
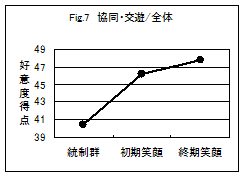
笑顔表出の主効果が有意であり(F(2,126)=3.79, p<0.05)、Tukey HSDによる多重比較の結果、統制群<終期笑顔表出群(統制群よりも終期笑顔表出群の方が好意度得点が高かったことを示す。以下同様)の間に有意差(p<0.05)が認められ、統制群≦初期笑顔表出群の間に有意傾向(p<0.10)が見られた。(Fig.7参照)これらのことから、協同・交遊の因子においては笑顔表出のない場合よりも終期に笑顔を表出した場合の方が好意度はより高くなり、また、笑顔表出のない場合よりも初期に笑顔を表出した場合の方が好意度はより高くなる傾向があることが示された。しかし、笑顔の表出順序のちがいによる有意な差は得られなかった。
ⅱ)親密・承認
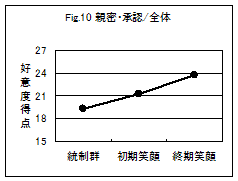
笑顔表出の主効果が有意であり(F(2,126)=10.87, p<0.05)、Tamhaneの多重比較の結果、統制群<終期笑顔表出群、初期笑顔表出群<終期笑顔表出群の間に有意な効果(p<0.05)が認められた。(Fig.10参照)これらのことより、親密・承認の因子においては、笑顔表出のない場合や初期に笑顔を表出した場合よりも終期に笑顔を表出した場合の方が好意度がより高くなることが示された。
結論①
これらのことから、総合的に考えると、被験者の性や認知的熟慮性-衝動性によって様相は異なるが、女性が友人をつくることを目的として初対面の他者に自己紹介をするとき、終期に笑顔を表出した場合の方が、初期に笑顔を表出した場合よりも相手によりポジティブな印象を抱かれ、また、より強い好意を抱かれる、と言える。