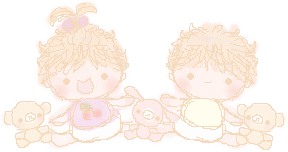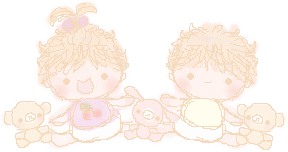◆ 1、発現率の男女差 ◆
子ども808人を対象に移行対象の発現率を検討した(表1)。
移行対象の発現率は過去に有った子どもと現在有る子どもを合わせ、36.76%となった。この数値は調査地域、対象年齢が異なるものの、藤井(1985)の31.1%、遠藤(1990)の38.0%に比較的近い結果となった。
男女間における移行対象の発現の差(表1)においても、移行対象を現在所有している子どもと過去に所有していた子どもを合わせ移行対象有群とし、移行対象を過去にも現在にも所有していなかった子どもを移行対象無群としχ2検定を行った。女児の移行対象発現率(45.1%)が男児の移行対象発現率(37.4%)よりも有意に大きいという結果となった(χ2=4.246,p<.05)。これは遠藤(1991)の結果と同様の結果となった。
しかし、他の文化圏で行われた研究の大半が移行対象の発現率に男女差は見られないという結果をだしている。(例えば:Setevenson,1954)。これに関して、遠藤(1991)は日本特異な社会文化的状況が関係しているかもしれないとし、1つの推論として、女児の方が愛着物を与えられやすいのではないかと述べている。
また、本研究において用いた刺激図版では、移行対象をぬいぐるみとしたため、移行対象物をぬいぐるみのみであると感じた影響があったかもしれない。
子どもに与えられるおもちゃの中で、女児にはぬいぐるみを与えられる機会が男児に比べて多い。
それに対し男児は、ロボットや車のおもちゃなどが与えられやすい。
もし、男児がぬいぐるみ以外のものを移行対象として所有していても、今回の調査ではそれを移行対象だと想起しにくかったために、男児の移行対象発現率が低くなったとも考えられる。
◆ 2、移行対象に対するイメージについて ◆
(1)母親の全体的イメージ
移行対象を所有する子どもに対するイメージは、「静かな」「消極的な」「ひとみしりする」「臆病な」「無口な」「やさしい」「おとなしい」「のんびりした」「かわいらしい」「おちついた」(ポジティブ、ネガティブにそれぞれ得点の高かった形容詞各5つ)といった形容詞をみると、「内向的でおちついている子ども」といったイメージが強いようである。また、子どもが不安を感じていることに関すること自由記述がみられた、例えば、「甘えたいという気持ちや不安のようなものはあると思います」「ぬいぐるみを離さない子は寂しがりや」「気持ちが落ち着く」などという記述である。落ち着かせ、慰めるもの(sooner)として移行対象の機能については、多くの母親が漠然とではあるが、認知していると考えてもいいであろう。
(2) 移行対象対象無群と有群のイメージの違いについて
移行対象を所有する子どもに対するイメージ測定尺度24項目について因子分析を行ったところ、「気が強い−気が弱い」「かわいらしい−にくらしい」の2項目を除き、2因子が抽出された。
第1因子では“あかるい−くらい”“積極的な−消極的な”“勇敢な−臆病な”という項目に高い負荷がみられ、行動面での積極性や対人関係においてのコミュニケーションに関係した項目が多いことから「社交性因子」の因子と命名した。
第2因子では、“おちついた−そわそわした”に高い負荷がみられ、“気長な−短気な”“行儀のよい−行儀のわるい”などから、子どもの気質がおちついていることに関する項目が多いことから「おちつき因子」と命名した。
それぞれの因子について高い負荷を示した項目ごとに合計したものを「イメージ全体」とし、分析を行った。イメージ得点が高いほどネガティブなイメージだったことを表す。
子どもの移行対象所有経験の有無によって、母親のイメージ得点に差があるのかどうかを検討した。
子どもに1人でも移行対象所有経験がある母親を「移行対象有群」、子どもに1人も移行対象所有経験がない母親を「移行対象無群」として、t検定を行った。(グラフ1)
移行対象有群は203名、移行対象無群は174名となった。
「社交性因子」(移行対象有群<移行対象無群,t=3.456,p<.005)、「イメージ全体」(移行対象有群<移行対象無群、t=2.253,p<.05)において有意差がみられたが、「おちつき因子」では差が見られなかった。
子どもに移行対象所有経験がない母親の方が、移行対象を所有している子どもに対し、「くらい」「消極的な」といったよりネガティブなイメージを持っており、人付き合いが苦手でおとなしい印象を持っていることが明らかとなった。
子どもが移行対象を所有していない母親の回答には「“愛情が足りない”とか“何か問題がある”という感じで私が責められると思います。自分でもそういう風に考えると思います」「夫も私もあまりよいことではないと思っていた。このA君のようにいつもぬいぐるみやタオルなどを持っているのは悪いくせとある教育ビデオでみたことがあります。」といった回答があった。
一方、子どもに移行対象所有経験がある母親の自由記述の中では、「いつかは手放す時もくるだろうし、それで気持ちが落ち着くなら構わない」「一昔前は常に手離さずものを持っていると愛情不足などと言ったが、今はそういう考えは少なくなっていると思う」「大きくなったらいつかはいらなくなると思っていますが−(中略)−私はほほえましいことだと思っています」といった回答があった。
以上の2点から推測されることは、子どもが移行対象を所有していない母親の方がネガティブに捉えているというよりも、子どもが移行対象を所有している母親がポジティブに捉えているのかもしれない。
その背景として、子どもに移行対象所有経験がある母親は、我が子が移行対象を所有していることで、移行対象を所有する子を尊重しようという気持ちや、肯定的に見ようとしている気持ちがより強くなるといったことが考えられる。
本研究の結果では、「イメージ全体」に比べ「社交性因子」での差が有意に大きかった。
そこで、「社交性因子」の項目に注目してみると、子どもに移行対象所有経験がない母親のもっているイメージは、移行対象を所有している子どもは暗く、臆病でひとみしりしやすいというイメージに近いものである。
これは、コミュニケーション能力に欠けると捉えているとも考えられ、従来の研究においての発達的意義があるという見解から考えると、これは移行対象に対し異なったイメージを母親が持っていると思われる。
子どもが移行対象を所有していない母親群が、子どもが移行対象を所有している母親群よりも、社交性因子でより得点が高いという結果は、移行対象を所有していない母親の方が移行対象を所有している子どもに対し、偏見的な認知をしている可能性が高いということになる。
本研究の目的では、子どもが移行対象を所有していることに不安を感じている母親に対しての援助としてこの調査を行ったが、移行対象を所有している母親に対して移行対象の知識を広めるということよりも、特に子どもが移行対象を所有していない母親に対して移行対象についての知識を持ってもらうことが必要であると考えられる。
そして、子どもが移行対象を所有していない母親が、移行対象所有に関してネガティブなイメージを持たなくなれば、子どもが移行対象を所有している母親も人からどう思われるかという点でのストレスはなくなるという意味でも、多くの母親に移行対象の知識を持ってもらうことは必要だろう。
そのためには、今後母親が移行対象に対してどのような知識を持っているのか、さらに詳しく検討していく必要があるであろう。
◆ 3.近親者の認知による影響について ◆
母親のイメージにどのような要因が影響しているのかを検討することについては、はっきりした要因を示すことはできなかった。
しかし、周りの人間の影響がないとは言い難い結果であり、更なる検討が必要だと思われる。
| |