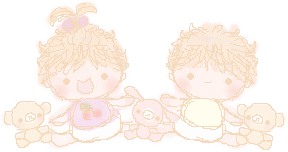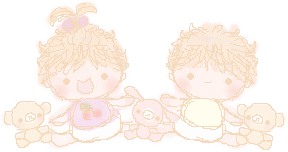乳幼児は、最初の自分でない所有物としてシーツや布きれを口に入れたり、ぬいぐるみや人形などをいつも持っていたりする。
Winnicott(1953)は、そういった乳幼児が特別の愛着をよせる対象や現象を、移行対象(transitional object)という言葉を使って概念化し、
移行対象の基盤には、母親との間にほどよい(good-enough)関係があると想定した。
そして、移行対象は、乳幼児にとって落ち着かせ、慰めるもの(soother)として機能するとした。
その後の研究により、移行対象を健常な発達の指標として考えられることが一般的に妥当とされている。
移行対象がWinnicott(1953)により概念化された後、さまざまな研究がなされているが、その中で、森定(1999)は、移行対象に対してネガティブな印象を持っている母親もいると述べている。
それは、移行対象の発現率が、母親を対象とした質問紙と子ども自身を対象にした質問紙(回想法)では大きく異なったことからの考察である。つまり、母親が移行対象所有に対しネガティブな印象を持っているために、子どもが移行対象を所有していることを認めたくないため、結果として発現率が低くなったのではないかというのである。
これまで、実際に母親の移行対象所有に対する印象について研究された例はない。
井原(1996)によると、相談機関に子どもが移行対象を手放さないことにより不安を感じ、相談にくるという実例もある。
子どもを育てる上で、母親はさまざまな悩みを抱えている。そして、すべての母親が同じ悩みを持つのではなく、それぞれの母親にそれぞれの悩みがある。
移行対象を離さないということも母親の1つの悩みになっているとも考えられる。
しかし、移行対象所有に対し不安を感じる母親もいれば、子どもがぬいぐるみを所有することは子どもらしくてむしろ好ましいと考えている母親もいるとも考えられる。
また、子どもが移行対象を所有する母親と子どもが移行対象を所有していない母親では、移行対象所有に対するイメージが異なってくるであろう。
実際に母親の移行対象に対するイメージがどのようなものなのか、明らかにすることは母親へのサポートとしての関わり方を改めて考え直すことにもなるのではないだろうか。
それに加え、母親の回りにいる多くの人も移行対象について十分な知識を持っていないだろう。
年齢が上がってからも移行対象を所有することが発達の遅れと考える人や愛情不足だと捉えている人も少なくない。
そういった人が周りにいることで、母親のイメージがネガティブになっていることもあると予想される。
周りの人間が移行対象所有に対し肯定的認知をしていると母親のイメージもポジティブになり、周りの人間が否定的認知をしていると母親のイメージもネガティブになると考えられるだろ。
周りの人間の中でも、関わる時間が多い人間の影響力は強いと考えられる。
例えば、近親者であれば同居していない場合よりも同居している場合の方が、影響力が強いだろう。
つまり、母親のイメージがどのようなものであるかを明らかにするとともに、母親のイメージにどのような要因が影響しているのかを検討する必要がある。
本研究においては、母親との関係が深く、影響力が強いであろうと考えられる近親者(夫、実父、実母、義父、義母)に焦点をあてて調査を行いたい。
そこで、本研究の目的は、第1に母親が移行対象を所有する子どもに対して持っているイメージを検討すること、
第2に子どもが移行対象所有している母親と所有していない母親とのイメージの違いを検討すること、
第3に母親の移行対象を所有する子どもに対するイメージには、どの近親者のどのような認知が影響を与えるのか検討することである。
それは、移行対象に対するイメージを明らかにすることで、子どもが移行対象を所有していることに不安を感じている母親に対して適切な援助ができるようになると考えられるからである。
また、子どもが移行対象を所有しているかどうかでイメージが異なり、近親者の認知によって母親の移行対象に対するイメージが異なってくるのであれば、子どもが移行対象を所有している母親に対して援助を行うよりも、周りの人に移行対象の知識を広め周りの意識を変えることが、子どもが移行対象を所有する母親に対す援助につながると考えられるからである。
| |