結果と考察
1.有効回答者数
2.尺度構成
3.学年と性による規範意識の違い
4.規範意識と生活関連意識の因果関係
1.有効回答者数
質問紙を回収し、得られた有効回答者数の学年別、男女別の内訳はTable 2の通りであった。
回収率は、小学校が95.4%、中学校が95.2%、高等学校92.9%であった。
Table 2 有効回答者数(学年・男女別)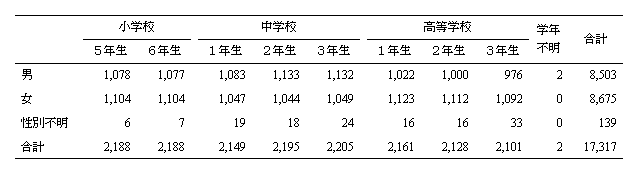
2.尺度構成
2-1.規範意識尺度の因子分析結果
全調査者を対象に、規範意識尺度について因子分析(主因子法、プロマックス回転)を行った結果、
5因子が抽出された。
各下位尺度のCronbachのα係数は、.89~.80の範囲にあり、高い内的整合性を示している。
第1因子は、「学校をさぼる」や「授業中、私語をしたりさわいだりする」、「先生の指導を
無視する」など9項目で負荷量が高く、学校内におけるルールや校則からの
逸脱した行動であると考えられるので、「学校内逸脱行動」因子と命名した。
第2因子は、「お店のものを万引きする」や「人をおどして、物や金をとりあげる」、「無断
で他人の自転車に乗る」などの6項目で負荷量が高く、法律違反や暴力行動から
成り立っているので、「違法・暴力行動」因子と命名した。
第3因子は、「点字ブロックの上に自転車をとめる」や「人の気持ちを考えずに発言する」、
「メールやチャットで人の悪口を書きこむ」などの5項目で負荷量が高く、特定
ではない他者を不快にさせるような行動であると考えられるため、「迷惑行動」因子
と命名した。
第4因子は、「髪の毛を染めて登校する」や「学校内でお菓子を食べる」、「友だちと一緒に
カラオケやゲームセンターに行く」などの4項目で負荷量が高く、友人関係や
学校内外の生活に遊びや快楽を追求しようとする行動を表す項目から成り立って
いるので、「遊び・快楽志向行動」因子と命名した。
第5因子は、「ボランティア活動に積極的に参加する」や「友だちのなやみを聞いたり、相談
相手になったりする」、「電車やバスで体の不自由な人やお年寄りに席をゆずる」
などの5項目で負荷量が高く、愛他的な行動や向社会的な行動を表す項目で成り
立っているので、「向社会的行動」因子と命名した。
各因子の評定値の平均を下位尺度得点とした。いずれの下位尺度も得点が高いほど規範意識の高さ
を表している。
2-2.生活関連意識の主成分分析結果
本研究では、規範意識との因果関係を明らかにするために、生活関連意識項目を因子分析的手法は
使わず、要約することとした。具体的には、主成分分析によって3つの成分として設定し、8つの
生活関連意識の各項目群ごとに、相互に相関が高い生活関連意識項目を成分として要約した。
各項目群の成分をTable 3に示す。
Table 3 生活関連意識の主成分分析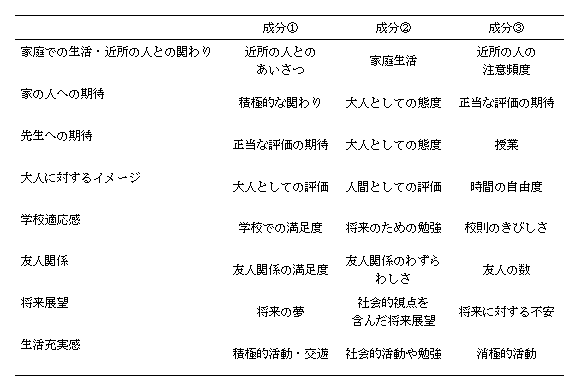 ただし、以後の分析において使用する成分はこのうちのいくつかである。
また、各成分を構成している項目の評定値の平均を成分得点とし、以後の分析に用いた。
ただし、以後の分析において使用する成分はこのうちのいくつかである。
また、各成分を構成している項目の評定値の平均を成分得点とし、以後の分析に用いた。
3.学年と性による規範意識の違い
因子分析によって得られた規範意識尺度の5つの下位尺度ごとに、学年や性によって異なっ
た特徴を示すかどうかを検討するために、規範意識尺度の各下位尺度得点を従属変数とした
学年(小5・小6・中1・中2・中3・高1・高2・高3)×性(男・女)の2要因分散分析
を行った。
以下は、下位尺度得点ごとの結果を記述する。
3-1.学校内逸脱行動に対する意識の分析結果(Fig. 1)
学年の主効果がみられた。また、学年と性の交互作用もみられた。学年の主効果がみられた
ことから、どの学年間に差があるかを比較するために、多重比較(Tukey法)を行った結果、
中2と中3、高1と高3、高2と高3以外の組み合わせの間に有意な差がみられた。
これらのことから、学年が上がるに従って、学校内のルールや校則を無視した行動、つまり、
学校をさぼることや授業中に私語をしたり騒いだりすることをしてもかまわないと思っている
ことが明らかになった。
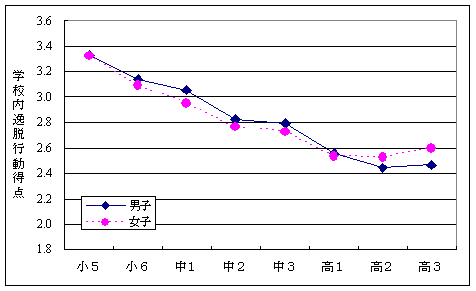 Fig. 1 学校内逸脱行動得点の学年・性別のグラフ
3-2.違法・暴力行動に対する意識の分析結果(Fig. 2)
学年と性の主効果がみられた。また、学年と性の交互作用がみられた。学年の主効果が
みられたことから、どの学年間に差があるかを比較するために、多重比較(Tukey法)を行
った結果、中2と中3、中3と高3、高1と高2、高1と高3以外の組み合わせの間に有
意な差がみられた。
Fig. 2を見ると、女子よりも男子の方が意識が低く、その差が顕著になるのは、中2以降
であるといえる。これは、学年が上がるほど、暴力・逸脱行動に対して許容的であるという
小嶋・松田(1999)と同様の結果を示している。これらのことから、男子は学年が上がるに
従って、法律違反や暴力的な行動に対して許容的になっていくのに対し、女子は、小5から
中2までは意識の低下がみられるものの、それ以降は意識に変化がないということが明らか
になった。つまり、男子と女子では、違法行為や暴力的な行動に対する意識の発達的な変化
の仕方に違いがあるといえる。その発達的な変化の違いが現れる時期は、中学2年生だろう
と考えられる。
Fig. 1 学校内逸脱行動得点の学年・性別のグラフ
3-2.違法・暴力行動に対する意識の分析結果(Fig. 2)
学年と性の主効果がみられた。また、学年と性の交互作用がみられた。学年の主効果が
みられたことから、どの学年間に差があるかを比較するために、多重比較(Tukey法)を行
った結果、中2と中3、中3と高3、高1と高2、高1と高3以外の組み合わせの間に有
意な差がみられた。
Fig. 2を見ると、女子よりも男子の方が意識が低く、その差が顕著になるのは、中2以降
であるといえる。これは、学年が上がるほど、暴力・逸脱行動に対して許容的であるという
小嶋・松田(1999)と同様の結果を示している。これらのことから、男子は学年が上がるに
従って、法律違反や暴力的な行動に対して許容的になっていくのに対し、女子は、小5から
中2までは意識の低下がみられるものの、それ以降は意識に変化がないということが明らか
になった。つまり、男子と女子では、違法行為や暴力的な行動に対する意識の発達的な変化
の仕方に違いがあるといえる。その発達的な変化の違いが現れる時期は、中学2年生だろう
と考えられる。
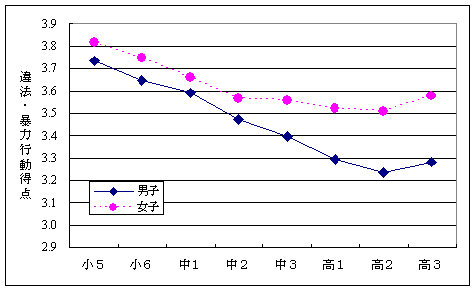 Fig. 2 違法・暴力行動得点の学年・性別のグラフ
3-3.迷惑行動に対する意識の分析結果(Fig. 3)
学年と性の主効果がみられた。また、学年と性の交互作用もみられた。学年の主効果が
みられたことから、どの果学年間に差があるかを比較するために、多重比較(Tukey法)を
行った結果、中2と中3、中2と高3、中3と高3、高1と高2以外の組み合わせの間に
有意な差がみられた。
Fig. 3を見ると、男子は学年が人に迷惑をかけるような行動に対して許容的になっていく
のに対し、女子は、小5から中1までは意識の低下がみられるものの、それ以降は意識に
変化がない。女子よりも男子の方が意識が低く、中学生のある時点でその差が顕著になる
という結果は、違法・暴力行動得点の結果の特徴と類似している。つまり、男子と女子では、
人に迷惑をかけるような行動に対する意識の発達的な変化の仕方に違いがあるといえる。
その発達的な変化の違いが現れる時期とは、中学1年生だろうと考えることができる。
Fig. 2 違法・暴力行動得点の学年・性別のグラフ
3-3.迷惑行動に対する意識の分析結果(Fig. 3)
学年と性の主効果がみられた。また、学年と性の交互作用もみられた。学年の主効果が
みられたことから、どの果学年間に差があるかを比較するために、多重比較(Tukey法)を
行った結果、中2と中3、中2と高3、中3と高3、高1と高2以外の組み合わせの間に
有意な差がみられた。
Fig. 3を見ると、男子は学年が人に迷惑をかけるような行動に対して許容的になっていく
のに対し、女子は、小5から中1までは意識の低下がみられるものの、それ以降は意識に
変化がない。女子よりも男子の方が意識が低く、中学生のある時点でその差が顕著になる
という結果は、違法・暴力行動得点の結果の特徴と類似している。つまり、男子と女子では、
人に迷惑をかけるような行動に対する意識の発達的な変化の仕方に違いがあるといえる。
その発達的な変化の違いが現れる時期とは、中学1年生だろうと考えることができる。
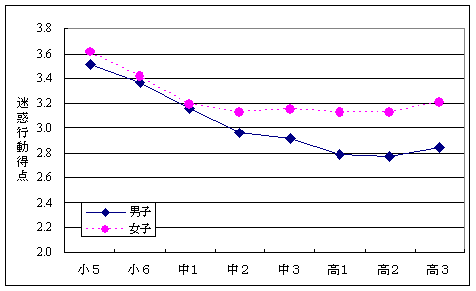 Fig. 3 迷惑行動得点の学年・性別のグラフ
3-4.遊び・快楽志向行動に対する意識の分析結果(Fig. 4)
学年と性の主効果がみられた。また、学年と性の交互作用もみられた。学年の主効果が
みられたことから、どの学年間に差があるかを比較するために、多重比較(Tukey法)を
行った結果、小5と中1、小6と中2、高2と高3以外の組み合わせの間に有意な差が
みられた。
Fig. 4を見ると、小5から小6にかけて意識の低下がみられるが、小6から中1にかけ
て意識の向上がみられる。また、他の規範意識下位尺度得点の分散分析結果と異なる点は、
男子よりも女子の方が得点が低い、つまり女子の方が遊びや快楽を求める行動に対する意
識が低いことである。これらのことから、自分の生活に遊びや快楽を追求しようとする行
動に対する意識は、学年が上がる従って次第に低下していく。また、全学年において、男
子よりも女子の方が、そのような行動に対して許容的である。
原田・鈴木(2000)では、以上のような遊びや快楽を追求する行動に対する規範意識は、
中学生と大人(保護者と教師)の間に有意差を見出している。本研究は、子どもの規範意
識を保護者や教師と比較はしていないが、遊び快楽志向行動得点の平均値は、他の規範意
識下位尺度得点の平均値と比較すると、相対的に低い。つまり、現代の子どもの規範意識
は、友だちとカラオケやゲームセンターに行ったり、髪の毛を染めるといったファッショ
ンや流行に対して許容的な特徴を持っているといえるだろう。
Fig. 3 迷惑行動得点の学年・性別のグラフ
3-4.遊び・快楽志向行動に対する意識の分析結果(Fig. 4)
学年と性の主効果がみられた。また、学年と性の交互作用もみられた。学年の主効果が
みられたことから、どの学年間に差があるかを比較するために、多重比較(Tukey法)を
行った結果、小5と中1、小6と中2、高2と高3以外の組み合わせの間に有意な差が
みられた。
Fig. 4を見ると、小5から小6にかけて意識の低下がみられるが、小6から中1にかけ
て意識の向上がみられる。また、他の規範意識下位尺度得点の分散分析結果と異なる点は、
男子よりも女子の方が得点が低い、つまり女子の方が遊びや快楽を求める行動に対する意
識が低いことである。これらのことから、自分の生活に遊びや快楽を追求しようとする行
動に対する意識は、学年が上がる従って次第に低下していく。また、全学年において、男
子よりも女子の方が、そのような行動に対して許容的である。
原田・鈴木(2000)では、以上のような遊びや快楽を追求する行動に対する規範意識は、
中学生と大人(保護者と教師)の間に有意差を見出している。本研究は、子どもの規範意
識を保護者や教師と比較はしていないが、遊び快楽志向行動得点の平均値は、他の規範意
識下位尺度得点の平均値と比較すると、相対的に低い。つまり、現代の子どもの規範意識
は、友だちとカラオケやゲームセンターに行ったり、髪の毛を染めるといったファッショ
ンや流行に対して許容的な特徴を持っているといえるだろう。
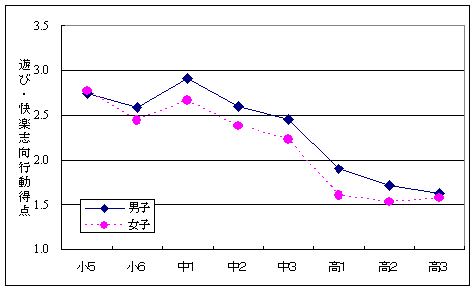 Fig. 4 遊び・快楽志向行動得点の学年・性別のグラフ
3-5.向社会的行動に対する意識の分析結果
学年と性の主効果がみられた。また、学年と性の交互作用もみられた。学年の主効果が
みられたことから、どの学年間に差があるかを比較するために、多重比較(Tukey法)を
行った結果、小6と中1、中2と中3、中2と高1、中2と高2、中2と高3、中3と高
1、中3と高2、中3と高3、高1と高2、高1と高3以外の組み合わせの間に有意な差
がみられた。
全般的に緩やかな低下がみられるが、学年間での急激な変化はあまりみられなかった。
つまり、小学生から高校生までの各発達段階における児童生徒が、ボランティア活動への
参加や友だちや社会的弱者に対する親切といった向社会的な行動をぜひすべきことである
と思っており、その意識が高いことが明らかになった。
「してはいけない」とされている行動に対する意識については、発達にともなってその
意識は低下する傾向がみられたが、「すべきである」というポジティブな行動に対する意識
については、発達にともなって意識の低下はみられなかった。つまり、このような援助や協力
といった行動に対する意識は発達とともにそれほど変化しないということが明らかになった。
Fig. 4 遊び・快楽志向行動得点の学年・性別のグラフ
3-5.向社会的行動に対する意識の分析結果
学年と性の主効果がみられた。また、学年と性の交互作用もみられた。学年の主効果が
みられたことから、どの学年間に差があるかを比較するために、多重比較(Tukey法)を
行った結果、小6と中1、中2と中3、中2と高1、中2と高2、中2と高3、中3と高
1、中3と高2、中3と高3、高1と高2、高1と高3以外の組み合わせの間に有意な差
がみられた。
全般的に緩やかな低下がみられるが、学年間での急激な変化はあまりみられなかった。
つまり、小学生から高校生までの各発達段階における児童生徒が、ボランティア活動への
参加や友だちや社会的弱者に対する親切といった向社会的な行動をぜひすべきことである
と思っており、その意識が高いことが明らかになった。
「してはいけない」とされている行動に対する意識については、発達にともなってその
意識は低下する傾向がみられたが、「すべきである」というポジティブな行動に対する意識
については、発達にともなって意識の低下はみられなかった。つまり、このような援助や協力
といった行動に対する意識は発達とともにそれほど変化しないということが明らかになった。
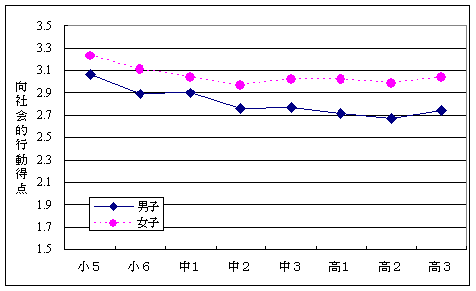 Fig. 5 向社会的行動得点の学年・性別のグラフ
Fig. 5 向社会的行動得点の学年・性別のグラフ
4.規範意識と生活関連意識の因果関係
生活関連意識から規範意識への因果関係を明らかにするため、「大人に対する態度」「学校
生活」「将来展望」の3つの観点から因果モデルを作成し、パス解析を行った。本研究では、
小学生では実施しなかった質問項目が存在するため、小・中・高のデータ(データⅠ)を使用
した分析と中・高のデータ(データⅡ)を使用した分析を行った。
データⅠとデータⅡの分析対象者数をTable 4 に示す。
Table 4 分析対象者数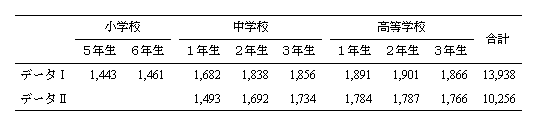 4-1.大人に対する態度が規範意識に及ぼす影響
身近な大人に対して期待が高いことや大人に誠実なイメージを持っていることが、児童・
生徒の規範意識に影響を及ぼす因果モデルを仮定し、データⅠを用いて多母集団における同時
分析を行った(Fig. 6~Fig.8)。想定した潜在変数は、「規範意識」「誠実な大人イメージ」「行動
規範の手本の期待」「正当な評価の期待」の4変数である。これらの潜在変数を説明するため
の観測変数は、生活関連意識の成分得点、及び規範意識における下位尺度得点を用いた。「規
範意識」が「誠実な大人イメージ」、「行動規範の手本の期待」、「正当な評価の期待」の
それぞれから直接影響するパスに加え、「行動規範の手本の期待」から「誠実な大人イメージ」
を経由して「規範意識」への間接的な影響を表現したパスと「正当な評価の期待」から「誠実
な大人イメージ」を経由して「規範意識」への間接的な影響を表現したパスを仮定した。その
結果、得られたモデルは、GFI=.976、AGFI=.954、RMSEA=.037と高い適合度を示した。
小・中・高校生とも「誠実な大人イメージ」(小:.30 、中:.28 、高:.15 )と「正当な
評価の期待」(小:.20、中:.42 、高:.44)から「規範意識」に直接のパスが認められた。
この結果から、小学生では、一般的な「大人」に対するイメージのよさが規範意識に強く影響
していたのが、発達するに従って、その影響は弱まっていき、一方、よいことをしたときは
ほめてほしい、悪いことをしたらきちんとしかってほしいなど正当な評価を期待することは、
発達するに従って規範意識に影響を与えるということが明らかになった。また、小学生と高校生
は、「行動規範の手本の期待」から「規範意識」へのパスは認められず、中学生では弱い負の
パスが認められた(-.09)。間接効果についてもあまり大きな影響はみられなかった。
4-1.大人に対する態度が規範意識に及ぼす影響
身近な大人に対して期待が高いことや大人に誠実なイメージを持っていることが、児童・
生徒の規範意識に影響を及ぼす因果モデルを仮定し、データⅠを用いて多母集団における同時
分析を行った(Fig. 6~Fig.8)。想定した潜在変数は、「規範意識」「誠実な大人イメージ」「行動
規範の手本の期待」「正当な評価の期待」の4変数である。これらの潜在変数を説明するため
の観測変数は、生活関連意識の成分得点、及び規範意識における下位尺度得点を用いた。「規
範意識」が「誠実な大人イメージ」、「行動規範の手本の期待」、「正当な評価の期待」の
それぞれから直接影響するパスに加え、「行動規範の手本の期待」から「誠実な大人イメージ」
を経由して「規範意識」への間接的な影響を表現したパスと「正当な評価の期待」から「誠実
な大人イメージ」を経由して「規範意識」への間接的な影響を表現したパスを仮定した。その
結果、得られたモデルは、GFI=.976、AGFI=.954、RMSEA=.037と高い適合度を示した。
小・中・高校生とも「誠実な大人イメージ」(小:.30 、中:.28 、高:.15 )と「正当な
評価の期待」(小:.20、中:.42 、高:.44)から「規範意識」に直接のパスが認められた。
この結果から、小学生では、一般的な「大人」に対するイメージのよさが規範意識に強く影響
していたのが、発達するに従って、その影響は弱まっていき、一方、よいことをしたときは
ほめてほしい、悪いことをしたらきちんとしかってほしいなど正当な評価を期待することは、
発達するに従って規範意識に影響を与えるということが明らかになった。また、小学生と高校生
は、「行動規範の手本の期待」から「規範意識」へのパスは認められず、中学生では弱い負の
パスが認められた(-.09)。間接効果についてもあまり大きな影響はみられなかった。
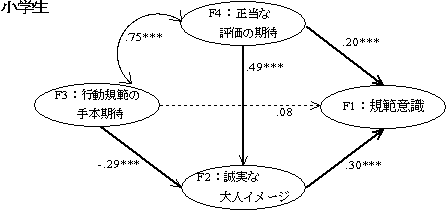 Fig. 6 大人に対する態度と規範意識の因果モデル(小学生)
Fig. 6 大人に対する態度と規範意識の因果モデル(小学生)
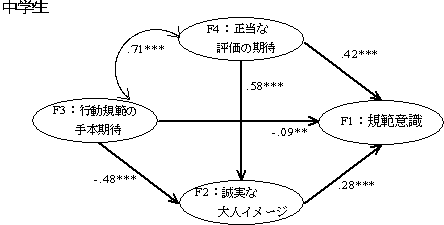 Fig. 7 大人に対する態度と規範意識の因果モデル(中学生)
Fig. 7 大人に対する態度と規範意識の因果モデル(中学生)
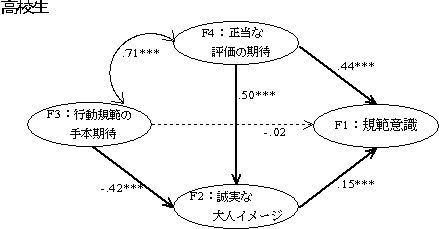 Fig. 8 大人に対する態度と規範意識の因果モデル(高校生)
4-2.学校での生活意識が規範意識に及ぼす影響
通学している学校での生活意識が児童・生徒の規範意識に影響を及ぼす因果モデルを仮定し、
データⅠを用いて多母集団における同時分析を行った(Fig. 9~Fig.11)。想定した潜在変数は、
「規範意識」と「学校適応感」、「先生への期待」、「友人関係」の4変数である。これらの
潜在変数を説明するための観測変数は、生活関連意識の成分得点、及び規範意識における下位
尺度得点を用いた。「規範意識」が「学校適応感」、「先生への期待」、「友人関係」のそれ
ぞれから直接影響を受けるパスに加え、「先生への期待」から「学校適応感」を経由して「規
範意識」への間接的な影響を表現したパスと「友人関係」から「学校適応感」を経由して「規
範意識」への間接的な影響を表現したパスを仮定した。その結果、得られたモデルは、GFI=.925、
AGFI=.887、RMSEA=.051と高い適合度を示した。
「規範意識」に最も大きな影響を与えているのは、「学校適応感」であった(小:.66、
中:.88、高:.52)。つまり、学校生活が楽しいと思っているほど、その子どもの規範意識は
高いということである。また、「友人関係」と「規範意識」の関係は、友だちとの関係がうまく
いっていると感じているほど、小学生の規範意識が高かった(.20)のに対して、中・高生の
規範意識には負の影響を与える(中:-.39 、高:-.17)という結果であった。しかし、中・高生
において、友だちとの関係が良好であると感じており、なおかつ学校で適応的に生活している
ほど、規範意識が高いということが明らかになった(中:.46、高:.17)。青年期初期の発達
的な特徴や友人関係維持の仕方の特徴を考慮すれば、友人関係がよいことが必ずしも規範意識
につながらないという結果は自然なことかもしれない。
Fig. 8 大人に対する態度と規範意識の因果モデル(高校生)
4-2.学校での生活意識が規範意識に及ぼす影響
通学している学校での生活意識が児童・生徒の規範意識に影響を及ぼす因果モデルを仮定し、
データⅠを用いて多母集団における同時分析を行った(Fig. 9~Fig.11)。想定した潜在変数は、
「規範意識」と「学校適応感」、「先生への期待」、「友人関係」の4変数である。これらの
潜在変数を説明するための観測変数は、生活関連意識の成分得点、及び規範意識における下位
尺度得点を用いた。「規範意識」が「学校適応感」、「先生への期待」、「友人関係」のそれ
ぞれから直接影響を受けるパスに加え、「先生への期待」から「学校適応感」を経由して「規
範意識」への間接的な影響を表現したパスと「友人関係」から「学校適応感」を経由して「規
範意識」への間接的な影響を表現したパスを仮定した。その結果、得られたモデルは、GFI=.925、
AGFI=.887、RMSEA=.051と高い適合度を示した。
「規範意識」に最も大きな影響を与えているのは、「学校適応感」であった(小:.66、
中:.88、高:.52)。つまり、学校生活が楽しいと思っているほど、その子どもの規範意識は
高いということである。また、「友人関係」と「規範意識」の関係は、友だちとの関係がうまく
いっていると感じているほど、小学生の規範意識が高かった(.20)のに対して、中・高生の
規範意識には負の影響を与える(中:-.39 、高:-.17)という結果であった。しかし、中・高生
において、友だちとの関係が良好であると感じており、なおかつ学校で適応的に生活している
ほど、規範意識が高いということが明らかになった(中:.46、高:.17)。青年期初期の発達
的な特徴や友人関係維持の仕方の特徴を考慮すれば、友人関係がよいことが必ずしも規範意識
につながらないという結果は自然なことかもしれない。
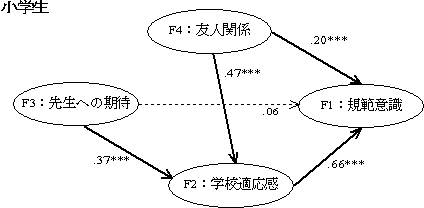 Fig. 9 学校生活と規範意識の因果モデル(小学生)
Fig. 9 学校生活と規範意識の因果モデル(小学生)
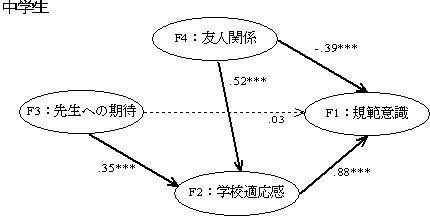 Fig. 10 学校生活と規範意識の因果モデル(中学生)
Fig. 10 学校生活と規範意識の因果モデル(中学生)
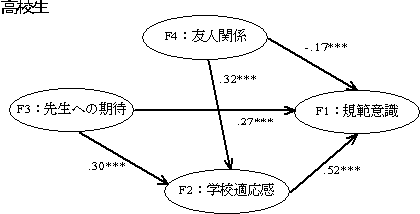 Fig. 11 学校生活と規範意識の因果モデル(高校生)
4-3.将来展望が規範意識に及ぼす影響
自分の将来や社会の将来に見通しを持っていることいることが児童・生徒の規範意識に影響を
及ぼす因果モデルを仮定し、データⅡを用いて多母集団における同時分析を行った(Fig. 12と13)。
想定した潜在変数は、「規範意識」、「将来展望」、「社会活動や勉強への志向性」、「人間関係
の豊かさ」の4変数である。これらの潜在変数を説明するための観測変数は、生活関連意識の成分
得点、及び規範意識における下位尺度得点を用いた。「規範意識」が「将来展望」、「社会活動や
勉強への志向性」、「人間関係の豊かさ」から直接影響を受けると考えられるパスに加え、「将来
展望」から「社会活動や勉強への志向性」を経由して「規範意識」につながるパスと、「人間関係
の豊かさ」を経由して「規範意識」につながるパスを仮定した。その結果、モデルはGFI=.907、
AGFI=.853、RMSEA=.074とやや高い適合度を示した。
中学生・高校生ともに「規範意識」に大きな影響を与えているのは、「社会活動や勉強への志向
性」であった。つまり、社会的な活動や勉強に対して意味を見出している中・高生は、規範意識が
高いということである。
また、「将来展望」が「規範意識」に直接与える影響は、中学生では、弱い負のパスが認められた
(-.17)が、高校生では、パスが認められなかった。しかし、「社会活動や勉強への志向性」を経由
して、「将来展望」から規範意識に与える間接効果には、中・高生ともに正のパスが認められた
(中:.54、高:.40)。つまり、将来に夢や希望を抱いており、なおかつ社会的な活動や勉強に対して
意味を見出していることが、規範意識に大きな影響を与えるということである。中・高生は進学や就職
を考える時期でもあり、自分は将来何をしたいのかということを明確にするだけではなく、勉強が将来
の役に立つことを意識させなくてはならないだろう。
Fig. 11 学校生活と規範意識の因果モデル(高校生)
4-3.将来展望が規範意識に及ぼす影響
自分の将来や社会の将来に見通しを持っていることいることが児童・生徒の規範意識に影響を
及ぼす因果モデルを仮定し、データⅡを用いて多母集団における同時分析を行った(Fig. 12と13)。
想定した潜在変数は、「規範意識」、「将来展望」、「社会活動や勉強への志向性」、「人間関係
の豊かさ」の4変数である。これらの潜在変数を説明するための観測変数は、生活関連意識の成分
得点、及び規範意識における下位尺度得点を用いた。「規範意識」が「将来展望」、「社会活動や
勉強への志向性」、「人間関係の豊かさ」から直接影響を受けると考えられるパスに加え、「将来
展望」から「社会活動や勉強への志向性」を経由して「規範意識」につながるパスと、「人間関係
の豊かさ」を経由して「規範意識」につながるパスを仮定した。その結果、モデルはGFI=.907、
AGFI=.853、RMSEA=.074とやや高い適合度を示した。
中学生・高校生ともに「規範意識」に大きな影響を与えているのは、「社会活動や勉強への志向
性」であった。つまり、社会的な活動や勉強に対して意味を見出している中・高生は、規範意識が
高いということである。
また、「将来展望」が「規範意識」に直接与える影響は、中学生では、弱い負のパスが認められた
(-.17)が、高校生では、パスが認められなかった。しかし、「社会活動や勉強への志向性」を経由
して、「将来展望」から規範意識に与える間接効果には、中・高生ともに正のパスが認められた
(中:.54、高:.40)。つまり、将来に夢や希望を抱いており、なおかつ社会的な活動や勉強に対して
意味を見出していることが、規範意識に大きな影響を与えるということである。中・高生は進学や就職
を考える時期でもあり、自分は将来何をしたいのかということを明確にするだけではなく、勉強が将来
の役に立つことを意識させなくてはならないだろう。
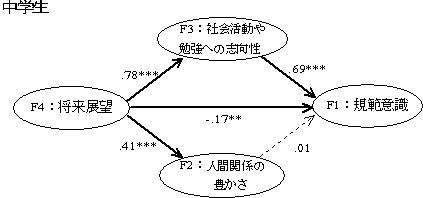 Fig. 12 将来展望と規範意識の因果モデル(中学生)
Fig. 12 将来展望と規範意識の因果モデル(中学生)
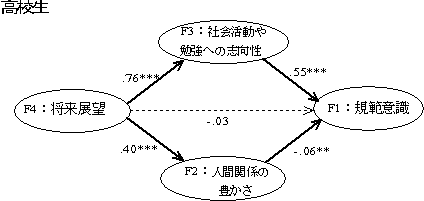 Fig. 13 将来展望と規範意識の因果モデル(高校生)
Fig. 13 将来展望と規範意識の因果モデル(高校生)
 方法へ まとめへ
方法へ まとめへ
トップへ

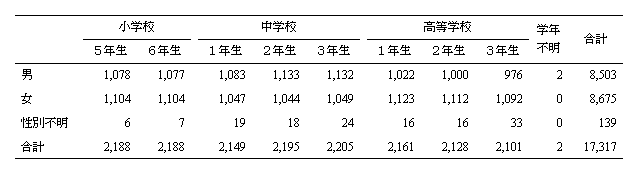
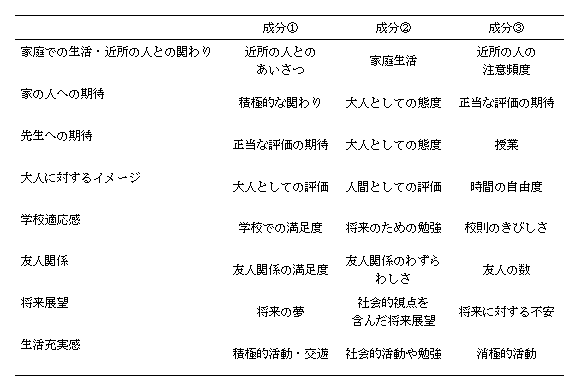
方法へ まとめへ

