![]() �@���ƖړI�@
�@���ƖړI�@![]()
���c���̗V�т̔��W
�� �������@�@ �F�ЂƂ�V�с|���҂Ƃ������C������S�������Ȃ�
�� 2�Δ����� �F�T�ρ@�@�@�|���̎q�ǂ����V��ł���̂��킫���炶���ƌ��Ă���
�� 3����@ �F���s�V�с@�|������������œ����V�т����Ă��邪�ւ�肪�݂��Ȃ�
�� 3,4���� �F�A���V�с@�|�q�ǂ����m���ւ�肠��
�� 5����@ �F�����V�с@�|�c�����ɂ����钇�ԗV�т̊����`
���c�����̗F�����Ƃ̌��т�
�@��̗V�т����邽�߂ɂ�������̂ł���A���̂قƂ�ǂ��V�ѓ���ƕۈ�҂Ȃǂ̑�l��}��Ƃ��Ă�����B���̂��߂��̊W�͂������ĐA���̂Ƃ��̒��q�ɂ���č����͂��̎q�A�����͂��̎q�Ƃ����悤�ɁA�V�ё��肪�ڂ�ς�邱�Ƃ������̂��ӂ��ł���Ƃ����Ă���B
�@�������A�ۈ���H�L�^�̂Ȃ��ɂ́A3�Ύ��N���X�㔼�œ���̗F���������߂āA�܂�Łu�X�g�[�J�[�v�̂悤�ȍs�����Ƃ邱�Ƃ��߂��炵���Ȃ��Ƃ����Ă�����̂�����B�ȉ��ɂ��̎�����Љ��B
����F�`�͂a�����߂��Ƃ��A�G�{��ǂ�ł���a�ׂ̗ɓ��荞��ŁA��������ɓ����G�{�����悤�Ƃ���B�a�͂����Ƃ������Ȃ�A���̊G�{���`�ɓn���āA�����͕ʂ̏ꏊ�ɍs���ĕʂ̊G�{��ǂݎn�߂�B����ƁA�`�͐�قǂ̊G�{�����o���āA�܂��a�ׂ̗ɂ���ė��ē����G�{���̂�������(�_�c,2004)�B
�@�����������F��ł͂��邪�A�V�т̓��e�ł͂Ȃ��F�����Ƃ̊W���̂��̂����߂Ďq�ǂ��������o���Ă��邱�Ƃ��킩��
�@��3�Ύ��͗F�����Ƃ̗V�т��y���������łȂ��A�F�����Ƃ̊W��ϋɓI�ɍ��o�����Ə����������n�߂�p���݂��n�߂鎞���ł���
![]()
�c���������ȊO�̗F��������u����́v��������߂�悤�ɂȂ�̂͂����납��Ȃ̂��낤���H
������̗F���������ߎn�߂鎞���𖾂炩�ɂ���Ӌ`
�c���ɂƂ��ē���̑��肪�ł���Ƃ����̂́A�����ɂƂ����S�n�̂悢�����������邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł���B
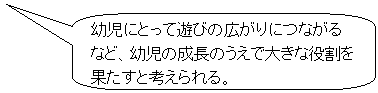
�����̂��߁A�ۈ���H�ɂ����ĕۈ�҂́A�c���ɂƂ��Ă̓��ʂȗF�����̑��݂��ɂ��A�܂��c�������̂悤�ȑ��݂���������悤�ɉ������Ă������Ƃ��]�܂��B
�@���������A���̉����͑�����悢�Ƃ������̂ł͂Ȃ��I�K�Ȏ����ɓK�ȉ������s�����Ƃ��d�v
�˓���̗F���������ߎn�߂鎞���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ́c
�@�ۈ���H�ɂ����鉇�����s�������Ŗ𗧂��_��^���邱�Ƃ��ł��邾�낤
����s�����Ɩ{����
�@�c���̒��ԊW�Ɋւ��邱��܂ł̌����ɂ��A�c�����̒��ԊW�̓����͎���2�ɂ܂Ƃ߂���B
�� 3�Ό㔼�������̑��҂��ӎ�����悤�ɂȂ�
��FHartup(1992)�F3�Ό㔼����4�܂łɁA����̑��҂��\���Ɉӎ����������ł̗F�����W���`������邱�Ƃ�����
�@�@Hinde, Titmus, Easton, & Tamplin(1985)�F3�Ό㔼�ɂ͗V�ё��肪����I�ɂȂ�A���̊W��������x�����I�ł���
�@�@Hartup,
Laursen, Stewart, & Eastenson(1988)�F���ɉ߂������Ԃ����ۂɒ���������A�\�V�I���g���b�N�e�X�g�ɂ������g���ɍD���ȑ����h�Ɠ�����悤�ɂȂ�
�� �V�������͓�����1����������3�����ŗV�ё��肪���܂��Ă���
��F��(1999)�F�V���c�t����(4�Ύ�)�̗F�����W�̌`���̌����ɂ����āA6������7����(������1����������3����)�ɂ����ėV�ё��肪���܂��Ă��邱�Ƃ𖾁@�@
�炩�ɂ��Ă���B����ɁA���̂Ȃ��ł����ɋ������т��������e�F�W�́A10���܂Ŏ�������邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B�����Ē����I�ɂ́A�u�����O�̒m�荇�@
���v�����u�����O�̗F�����W�v�̕�����苭���e�����y�ڂ��Ă��邱�Ƃ������Ă���B
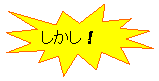
����܂ł̌����̂قƂ�ǂ����R���Ԃɒ������A���̎��Ԓ��̊W�����������Ԃ̑����Ԃɐ�߂銄������A�g���ǂ��̗F�����h����肵�Ă���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����R����������Ă��Ȃ�
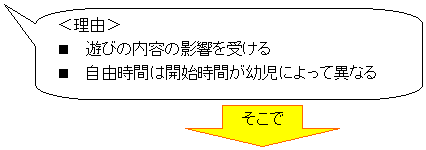
�{�����ł́E�E�E
�@���R������菜����萳�m�ɓ���̗F���������ߎn�߂鎞�����݂邽�߂ɁA
�������ɂ����������Ԃ̋��ڂ̏���ɒ��ڂ���
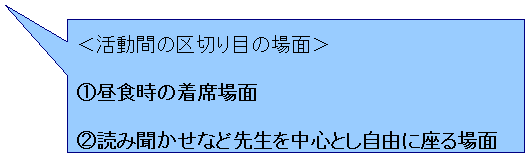
�@�@�@�˂��̂Ƃ��c���͂���܂ł̗V�т��I���A�V���Ɉꏏ�ɍ��肽���q������̈ӎv�ŋ��߂�B
�����̋��߂鑊��c�����u���艻�v����Ă��邱�Ƃ́A���̑��肪���̗c���ɂƂ��āu���ʂȁv���݂ł��邱�Ƃ������Ă���Ƃ�����B
���\�z
�i�P�j�N�����ł́A9�����납�����̗F���������߂�p���݂���悤�ɂȂ�
�@�@�|3���납��F�����Ɗւ�낤�Ƃ���ӎ������X�ɋ����Ȃ��Ă����B������3�ΑO���͂܂��ӎu�a�ʂ͂ł��Ă��炸�A������ӎ�������ł̑������n�܂邱�Ƃ͏��Ȃ��B3�Ό㔼����4����ɂȂ�ƁA�ꏏ�ɓ����悤�Ȋ��������钆�ŁA�F�����Ƃ̊ւ����o�����邱�Ƃ������Ȃ�(�F��,2000)�B9������̓N���X�̑唼��4���}���邱��ł���B�����4���̐V�������ւ̕ω����甼�N���o���A���͂ւ̈ӎ��������Ă��邱��ł���A�F�����Ƃ̊ւ��̌o�����L�x�ɂȂ邱��ł���B
�i�Q�j�N�����ł͔N�����������������������̗F���������߂�p���݂���悤�ɂȂ�
�@�@�|4���납��́A�R�~���j�P�[�V�����\�͂����B���A�F�����̍l���𗝉�������A�����̈ӌ���ɓ`������悤�ɂȂ邽�߁A�ӎv�̓`�B���\���ɂł��Ȃ��������߂ɋN�����Ă������������͏���������悤�ɂȂ�B���̂��߁A�����Ƃ̊ւ����N�����قǎ��Ԃ������邱�ƂȂ��z���Ă�����ƍl�����邽�߂ł���B
�i�R�j�����ւ̓��������͒j�����������ɑ����݂��A����̗F�����������ɋ����݂���
�@�@�|���R��(1984)�́A�F�����̖��O��m���Ă��邩�ǂ����Ƃ����m�������ɂ��3�Ύ��ɂ�����W�c�Q���ւ̉ߒ��̌����ɂ����āA3�Ύ��E4�Ύ��Ƃ��ɔN��ɊW�Ȃ��j�����������̕��������������瑼���̖��O���o���邱�Ƃ������Ă���B
�|�V(1984)�́A�c���̎Љ���B�̌����ɂ����āA�j�����������̎Љ���B���������A�F�����Ƃ̐e�a��(�F�����̍D���������A���b�D���Ȃ�)�ɂ��ėL�Ӎ��������Ă���B
�˂����́A�j����菗���̕����A�����ւ̊S���������Ƃ������Ă���ƍl������B