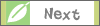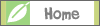要旨
本研究では、気になる子どもとして「ADHD
傾向のある子ども」を取り上げ、以下の2点を明らかにすることを目的とした。
(1) 気になる子どもに対して仲間がどのような態度で接しているかを明らかにし、学年・性別・障害特性(多動性/衝動性・注意欠陥)によって態度に違いがあるか。
(2) ADHDの特性を含む情報を提供することが、気になる子どもに対する仲間の態度に影響を与えるか。
方法は、小学校3〜6 年生42 名を対象に、ADHD
傾向のある気になる子どもが登場する紙芝居を用いたストーリー課題(多動性/衝動性2 種類、注意欠陥2
種類)を呈示し、気になる子どもに対する態度を測定した。
結果は、気になる子どもに対する仲間の態度は、約半数の仲間が否定的であることが明らかとなった。学年については、中学年よりも高学年において否定的な態度を示す仲間が多くみられた。性別については、男児よりも女児において否定的な態度を示す仲間が多くみられた。障害特性については、全体的に否定的であったが、多動性/衝動性の傾向のある気になる子どもに対しては、受容的な態度を示す仲間が多くみられ、注意欠陥の傾向のある気になる子どものほうが否定的にとらえられていることが明らかとなった。
ADHDの特性を含む情報の有無の影響については、情報を提供することにより仲間の否定的な態度をより受容的な態度へと促すことができることが明らかとなった。また、障害特性ごとに情報の有無の影響を検討したところ、多動性/衝動性の特性に対しては情報の提供による効果は得られたが、注意欠陥の特性に対しては情報の提供による効果は得られなかった。よって、ADHD
の特性を含む情報による仲間の態度への影響は、気になる子どものもつ障害特性やその程度によって差が生じることが明らかとなった。
以上のことより、気になる子どもは、通常学級において、仲間から十分に受容されていない可能性が考えられ、現状のままでは意欲の低下や自信欠如、学校不適応等の二次障害を引き起こす危険性も考えられる。よって、気になる子どもへの支援は、個別の対応にとどまるのではなく、周囲の仲間を含めた学級全体を意識した支援が必要であると考えられる。