携帯電話が引き起こす諸々の問題は、社会的迷惑の問題として取り上げられる。社会 的迷惑とは、携帯電話だけに関わらず、「行為者が自己の欲求充足を第一に考えること によって、結果として、他者に不快な感情を生起させること、またはその行為である」 ( 吉田・安藤・元吉・藤田・廣岡・斉藤・森・石田・北折,1999)。
しかし、社会的迷惑という概念には、自分が直接的に迷惑を被るというだけでなく、 社会的な視点から見れば迷惑であるという場合も含む。そこには、迷惑を行っている迷 惑行為者もいれば、直接迷惑を被っている人もいる。さらにそれを見ているという第三 者的な認知者もいる。また、ある行為が誰かにとっては迷惑であるかもしれないし、他 の誰かにとっては迷惑でないと言うこともあるだろう。(Fig.1)
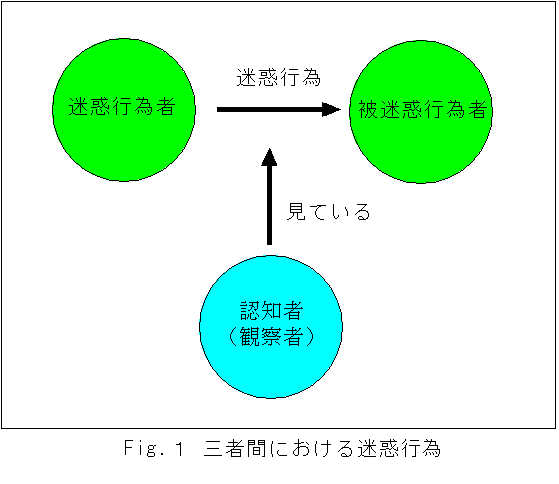
では、迷惑行為を迷惑であると認知するためには、どのような要因が必要だろうか。 人は、自分で自分のことを強く意識したとき、自分の中で適切な行動をとろうと試みる。 この自分が自分に注意を向けることを自己フォーカスという。客体的自覚理論(Duval & Wicklund,1972)によると、自己フォーカスが高まっている状況では、その場で最も 重要な自己の側面について考えようとするため、その人が正しいと思っている規準と現 実自己の姿とを比較する。その両者の間が負の不一致(現実自己が正しいと思っている 規準より劣っている)を起こしていると、人は自分を望ましい姿に近づけようとするた め、不一致を低減するように試みる。すなわち、自己の現実の姿を理想の姿に近づけよ うとするのである。(Fig.2)
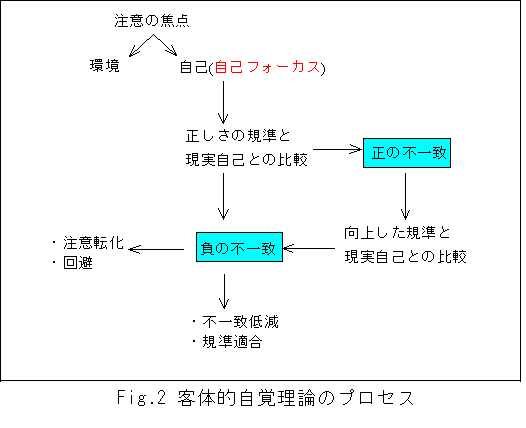
迷惑の感じやすさの個人的要因として、Feningstein, Scheir, & Buss(1975)の自己に 意識を向ける傾向である自己意識特性が考えられる。下位尺度として、第1因子は、自 己の感情や気分など、自己の内的な側面に注意を向ける程度を示すもので、私的自己意 識と名付けた。第2因子は、自己の服装や容姿あるいは他者に対する言動など、自己の 外的な側面に注意を向ける程度を示すものとして公的自己意識と名付けられた。(Fig.3)
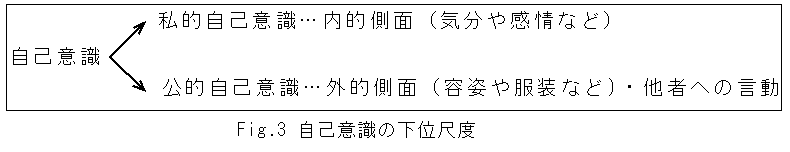 さらに、私的自己意識の高い人は、信念・態度と公的行動との一貫性が高いこと(Scheir,
1980)から、迷惑行為を迷惑であると認知できていれば、自分の行動に対しても迷惑行為
をしないように心がけるのではないかと考えられる。一方、公的自己意識が高い人は、
規範的影響による同調行動が強いこと(Froming, & Carver,1981; 石川・渡辺・押見,
1984)からも、他者の目を気にして、迷惑行為を迷惑であると認知しやすいのではないか
と考えられる。
さらに、私的自己意識の高い人は、信念・態度と公的行動との一貫性が高いこと(Scheir,
1980)から、迷惑行為を迷惑であると認知できていれば、自分の行動に対しても迷惑行為
をしないように心がけるのではないかと考えられる。一方、公的自己意識が高い人は、
規範的影響による同調行動が強いこと(Froming, & Carver,1981; 石川・渡辺・押見,
1984)からも、他者の目を気にして、迷惑行為を迷惑であると認知しやすいのではないか
と考えられる。以上のようなことから、本研究は、社会的迷惑の問題において、迷惑行為を迷惑である と認知することが重要であると考え、被験者が迷惑行為のビデオを見ているときの表情を ビデオカメラで録画することで、被験者の自己フォーカスを高め、その迷惑を認知しやす い状況において、自己意識との関係も考慮に入れながら検討していくことを目的とする。
[仮説1]:自己フォーカスが高まっている状況で迷惑行為を見たとき、そうでないときよ りも現実の自己と正しさの規準とを比較して、自分を正しい規準に近づけようと するため、迷惑行為を迷惑であると認知しやすい。
[仮説2]:自己フォーカスが高まっている状況で迷惑行為を見たとき、自己意識が高い人 の方が低い人よりも迷惑行為を迷惑であると認知しやすいが、自己意識が低い人 にとっても自己フォーカスは効果的である。

 全体要約へ 方法へ
全体要約へ 方法へ 
 タイトルへ
タイトルへ

