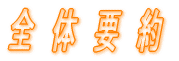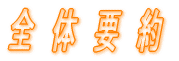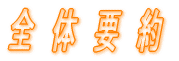


<本研究の目的>
本研究においては、2つの目的を設定して検討を行った。
第1の目的
教師が児童・生徒をどのような認知次元によって認知しているのかを明らかにする。
第2の目的
教師が学校生活において児童・生徒を指導する上で重視していること、つまり教師の指導観を「教師の指導に対する信念」と定義し教師の指導観が教師の児童・生徒認知にどのように影響しているのかを検討する。
<方法>
調査対象:1府4県の小学校、中学校、高等学校、その他の学校(養護学校等)に在職する現職の教師98名(男性39名、女性59名)。
調査方法:質問紙調査
質問紙の構成:①パーソナリティ評定尺度21項目
②教師の指導観尺度32項目
<結果と考察>
①第1の目的について
パーソナリティ評定尺度の因子分析の結果、1)温厚さ、2)活発さ、3)自己表出性、4)落ち着きの4因子で構成されていることが示された。
このことから、教師は児童・生徒を1)温厚さ、2)活発さ、3)自己表出性、4)落ち着きの4つの認知次元によって認知していることが明らかとなった。
このうち「自己表出性」の側面については、児童・生徒の知的な側面と結びついており、集団の中で適切に自己主張をすることや、自己の感情を表出することが知的な側面として認知されていることは、「コミュニケーション能力」が重視されている現在の教育現場におけるニーズを反映するものであると言える。
②第2の目的について
また、指導観尺度の因子分析の結果、1)個性尊重、2)集団協調、3)経験・学習過程重視の3因子で構成されていることが示された。これらの指導観3下位尺度をもとに教師の指導観をクラスター分析により1)自由型、2)集団協調重視型、3)個性尊重重視型、4)全般重視型の4つの指導型に分類できた。
各指導型と各想起児童・生徒を独立変数に、パーソナリティ評定4下位尺度をそれぞれ従属変数とした2要因分散分析を行った結果、「温厚さ」の因子において指導型の主効果がみられ、児童・生徒の個性や主体性、そして集団における協調性、学習の過程など学級生活における全般的な指導を重視している全般指導型の指導観をもつ教師は、全般的にそれらの指導を重視していない教師より「温厚さ」を重視した認知を行っているのではないかと考えられる。このように教師の児童・生徒を認知する上で大きなウエイトを持つと考えられる「温厚さ」の因子において指導型による違いが示されたことは、教師の指導観が児童・生徒の認知に大きな影響を持っていることを示すものであると考えられる。
また、「ウマの合う児童・生徒」のパーソナリティ評定4下位尺度と「理想の児童・生徒」のパーソナリティ評定4下位尺度との間に全般的に正の相関関係がみられた。「理想の児童・生徒」は、教師の持つ指導観が多分に反映されていることを考えると、教師の指導観が教師の児童・生徒に対する好意・非好意に影響を与えていることは十分に指摘できる。教師がこのような児童・生徒に対する認知の方向性を理解し、指導に対する考えを客観的に考える機会を持つことは、児童・生徒の学級適応感や、発達によい影響をもたらすと言える。