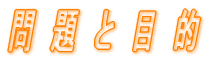
1.はじめに
2.教師の児童・生徒認知について
3.教師の指導観と児童・生徒認知
4.本研究の目的
1.はじめに
教育現場において教師は、毎日多くの子どもと接しながら一人ひとりの発達を見つめ、彼らが社会における自分の生き方を選択し、成長していくための支援をする立場にあると考えられる。現在の教育現場においては学習指導要領に子どもの「生きる力」の育成を掲げていることから推察されるように、単に子どもが学習をする習慣や、基本的な学習指導によって学力を伸長するはたらきかけをしていくだけではなく、コミュニケーション能力や、自ら課題を見出し、自ら考え、自ら判断する問題解決能力など、社会で生きていくための様々な能力を伸ばしていくための支援をしなければならないと考えられる。そのような教育現場の現状をふまえると、教師は一人ひとりの子どもを多様な側面から見つめ、彼らがどのような特性をもっているのかということを適切に見出していく必要があると考えられる。そのために教師自身が、児童・生徒をどのように認知しているのか、そして自己のどのような特性が児童・生徒に対する認知に影響を及ぼしているのかを知る必要があると考えられる。
教師が自分自身の児童・生徒に対する認知を客観的に理解することは、自分の児童・生徒に対する見方を学級経営に活かしたり、職業人としての教師の自己発達をはかっていく上でも重要であると考えられる。また、将来教育現場において生きていこうとしている自分にとっても意義のある研究となると考え、本研究のテーマとした。
2.教師の児童・生徒認知について
※対人認知(person perception)とは?
他者に対する様々な情報から相手の内面的特徴や心理過程を推論するはたらきのこと。人が他者を「どのような人間か」と認知するとき、人はそれぞれが持っているいくつかの基準をもとに評価、判断している。このような基準を認知次元と呼んでいる。飯田(2000)の指摘によると、対人認知における研究においては認知次元の内容が個人によって独自の様相を示すことを仮定する立場と、全ての人が共通の次元を有するが、個人によって各認知次元に重きを置く程度が異なるという大きく2通りの立場があるとしており、後者の立場が支持されることが多い。本研究においても、後者の立場から教師の児童・生徒認知についての検討を進めていくこととする。
2−1.学校現場における児童・生徒認知の重要性
学校現場でも、教師は日常の学校生活において、子どもの学習場面や生活場面で子どものパーソナリティ認知を行い、それに基づいて子どもに対して様々な働きかけをしている。
教師が子どもをどのように認知しているかということは、教師期待効果(teacher expectation effect ; Rosenthal&Jacobson, 1968)の研究から概観すると、子どもに多大な影響を及ぼすことが予測される。教師が児童・生徒をどのような視点に基づいて認知しているのかを検討することは、教師が児童・生徒を理解し、様々な支援をしていく上でも、学級経営や、児童・生徒指導の上においても重要な意味があると言える。
そこで本研究においては、教師が児童・生徒をどのような視点で認知しているのか検討することを第1の目的とする。
2−2.パーソナリティ評定尺度による児童・生徒認知研究
教師の児童・生徒認知研究において蘭(1990a)は、教師の児童・生徒に対する認知次元として1)社会性、2)活動性、3)安定性、4)知的意欲、5)創造性を見出している。また、天根・吉田(1984)は、1)活発さ、2)温厚さ、3)聡明さ、4)落ち着き、5)根気強さの5次元を見出し、3)〜5)の次元は、学業面における望ましさという上位次元を形成していると述べている。近藤(1984)によると、これらの研究から教師は、1)学力、学習意欲、積極性、2)行動の統制、生活態度の2側面を中心とした認知を行っていることを示唆しており、教師の児童・生徒に対する認知は、通常の対人関係における認知とは少し異なり、評価的側面を帯びた視点から行っていることを示している。
2−3.教師用RCRT(role construct reportory test ; RCRT)による児童・生徒認知研究
また、越(2002)は現職教員の大学院生を対象として、近藤(1984)の教師用RCRT(role construct reportory test ; RCRT)を簡略化し、修正を行ったものを用いて、教師自身によって把握された児童・生徒の行動特徴と、それについての教師自身による考察を報告している。教師用RCRT(近藤,1984)とは、教師に類似・非類似と認知された児童・生徒、教師が好意・非好意をもつ児童・生徒などの特徴を記述する際に用いた概念から、その教師特有の児童・生徒認知の視点を抽出するという点で優れているとされる。越(2002)においても、昨年度あるいはそれ以前に担任した学級の児童・生徒を想起させ、その中から自己(教師)との類似・非類似の児童・生徒、ウマの合う・合わない児童・生徒、考えていることが手に取るように分かる・考えていることがまったく分からない児童・生徒をあげさせ、彼らの行動特徴をそれぞれ記述させた。その上で、これらの児童・生徒の行動特徴を対象者自身で複数の認知次元に分類させ、それらの次元上で学級の全員について5段階評定をさせた。また、理想の児童・生徒、現実と理想の自分自身についても同様に評定させ、最後にそれらに基づいて自分の児童・生徒認知を考察させた。
その結果、教師が児童・生徒を認知する側面は、1)能力、2)物事に対する姿勢・意欲、3)行動統制のとりやすさ・とれやすさ、4)人間関係の配慮、5)基本的生活習慣、6)性格・他者への関わり、7)性格・明るさ、8)性格・表出性の8つのカテゴリーに分類された。
2−4.両者の手法による相違点
しかし、蘭(1990a)や天根・吉田(1984)においては、あらかじめ作成された評定尺度に基づくものであり、実験室的な手法である。一方で、越(2002)も近年の研究において認知者個人の特徴を反映しやすく、より具体的で現場の現状に即した認知次元を抽出可能とされる教師用RCRTに注目をしているが、被調査者が29名と少なく、これらが教師が児童・生徒認知に用いる一般的な視点であるのかは疑問が残る。そこで、越(2002)の結果と、天根・吉田(1984)によって抽出された認知次元とを比較、検討した。
越(2002)は、 天根・吉田(1984)の「温厚さ」次元は、人間関係の配慮に関するカテゴリーと性格・他者への関わりに関するカテゴリーに、天根・吉田(1984)の「落ち着き」次元は、行動統制のとりやすさ・とれやすさのカテゴリーに対応すると述べている。さらに、天根・吉田(1984)において使われている各次元の形容詞対と越(2002)において分類されたカテゴリーの内容を比較すると、天根・吉田(1984)における「活発さ」次元は、越(2002)の性格・明るさに関するカテゴリーに、天根・吉田(1984)における「学業面における望ましさ」次元は物事に対する姿勢・意欲のカテゴリーに類似していると考えられた。よって、教師用RCRTによる手法は、パーソナリティ評定尺度によって抽出された認知次元とほぼ同様のカテゴリーが見出されており、教師が児童・生徒を認知するときの共通した認知次元があることが確認されたと考えられる。
しかし、自己主張ができるかどうかに関する性格・表出性のカテゴリーに対応する認知次元が、天根・吉田(1984)の研究にはみられなかった。自己表出は、近年の学校現場において子どもに身につけてほしいと考えられている「コミュニケーション能力」の一つであり、現在の学校現場に即した教師の児童・生徒に対する認知側面であると言える。
これは教師を対象に中学生が欠如している側面を記述させ、中学生に必要とされる心理教育についてを検討した榎本(2004)においても、意見を言う能力や、話し合いをする能力などの「コミュニケーション面」、他者の気持ちを考えて行動するなどの「行動面」が中学生に欠如している能力として挙げられていることからも言える。これらのことから、教師が児童・生徒を認知する側面として自己主張などの「自己表出性」に関する側面にも注目する必要があると考えられる。よって、これらのことを考慮して研究を進めていくこととする。
3.教師の指導観と児童・生徒認知
教師が児童・生徒がどのような子どもかを認知するとき、教師自身が持っている要因によって、認知の仕方が異なってくる。教師の個人的要因を扱った研究については、教職歴、ポジティヴィティ傾向、自己意識、自尊感情などを扱った研究がある。教職歴を扱った研究においては、教職歴が長くなるにつれ、活発さにウエイトをおいて児童を認知することや(吉田・相川,1983)、パーソンポジティヴィティ(人を好意的・肯定的に認知する傾向性)傾向の高い教師の学級では、成績の上昇する児童が多く、児童に対して肯定的な評価を多く行っていることが示されている(蘭,1990b)。このように教師の持つ個人的要因は、児童・生徒の認知に対して影響をもっていることが言える。
本研究においては、教師の個人的要因の中でも教師が児童・生徒を指導するときに大切にしていることや、こう育って欲しいと考えていることなど教師自身が持っている指導観に注目をしたい。
越(2002)は、「ウマの合う児童・生徒」の方が「ウマの合わない児童・生徒」よりも、理想の児童・生徒像や理想自己との類似度が高いことを確認している。理想の児童・生徒像に対しては、教師が「こう育って欲しい」、「このような側面が優れていて欲しい」など教師の指導観を多分に反映するものであると考えられ、越(2002)はこの点についても指摘している。これらは、調査対象者となった教師も、「抽出された認知次元は自分が学級において子どもに投げかけることであり、自身が大切にしていることがそのまま因子として出され、自己の教育観をふり返ることができた」などのコメントがあり、教師の持っている教育に対する信念、指導観が児童・生徒に対する認知に影響を持っていることがうかがわれる。つまり、教師自身が児童・生徒を指導する上で、大切に思っていること、重視したいと思っている側面を中心として児童・生徒認知を行っていると考えられる。つまり、教師が「ウマが合う」と感じている児童・生徒は、教師の指導観に即した認知側面を高く評定されている児童・生徒であるということが考えられる
しかし、「教師の指導観」と一口に言っても、曖昧な概念であるため、本研究においては梶田(1986)の「個人レベルの学習・指導論(Personal Learning And Teaching Theory ; PLATT)に注目をした。「個人レベルの学習・指導論」とは、人間が指導や学習に対して持っているパーソナルな信念・セオリーのことであり、学習に対して持っている個人的な見方・考え方を「個人レベルの学習論(Personal Learning Theory ; PLT)」、指導に対して持っている個人的な見方・考え方を「個人レベルの指導論(Personal Teaching Theory ; PTT)」と呼んでいる(梶田,1986)。
「個人レベルの指導論」は、狭義には、具体的・実際的な指導方法に限定することも可能であるが、梶田・後藤・吉田(1984)においては、PTTを「人の指導に対する信念」として定義している。これは、教師が学校生活の中で児童・生徒を指導する上で重視していることと捉えられる。
よって、梶田(1986)の「個人レベルの指導論」に着目し、教師が児童・生徒を指導する上で大切に思っていることや重視していることなど、教師の指導観を「教師の指導に対する信念」と定義し、教師の指導観が教師の児童・生徒認知にどのように影響しているのかを検討することを第2の目的とする。
4.本研究の目的
本研究における目的を以下に述べる。
第1の目的
教師が児童・生徒をどのような認知次元によって認知しているのかを明らかにする。
第2の目的
教師の指導観を「教師の指導に対する信念」と定義し、教師の指導観が教師の児童・生徒認知にどのように影響しているのかを検討する。