| ■問題と目的■ ※このページ以降の図表の通し番号は、論文の通りになっています。 廣岡ら(印刷中)では、2006年度春クラスの第2回にPAを実施した。ここでは3名の評定者が同一児童の各スキルについてをRubricによって評定しているのだが、スキルによって、この3名の評定値が一致しないものがみられた。 そこで、予備調査として、廣岡ら(印刷中)での評定者3名がそれぞれ集まり、評定値がばらついた原因を検討した。その結果、ばらつきの原因として圧倒的に多かったのが、Rubricの解釈の相違によるものであった(Figure 1-1)。 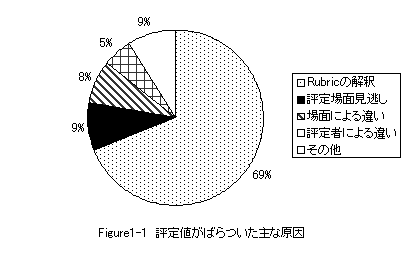 本調査では、予備調査の結果をもとに、モデレーションを行ったうえで、2006年度秋クラスの第5回にPAを実施し、スタッフが評定した。 ■方法■ <モデレーションの手続き> 評定者の協議のメモをもとに、Rubricを改訂した。主に具体例(事例)を増やし、まぎらわしい表現を明確にした。(Table 1-2,Table 1-3) 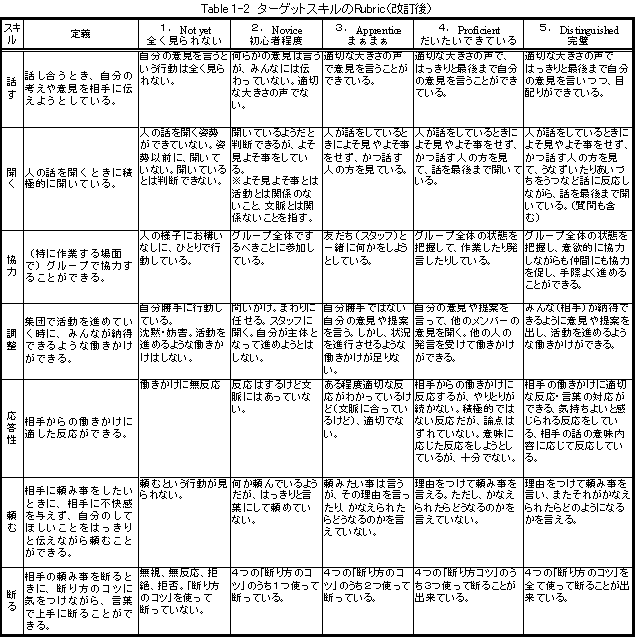 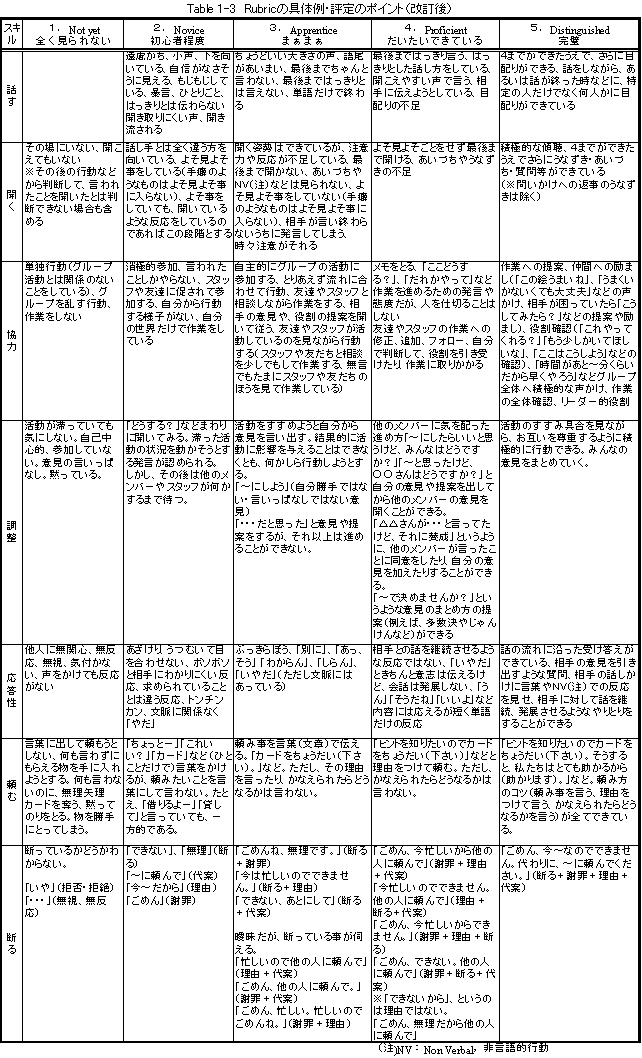 <秋クラス第5回のPA実施手続き> 秋クラス第5回の評定対象児は、4〜5年生の男女11名であった。 グループで協力してすごろくを作るという活動を行う中で、対象のスキルとなる話す、聞く、協力、調整、応答性、頼む、断るの各スキルが評定された。Taskとなったのは、どのようなすごろくを作るのかなどを話し合う場面、作業をする場面、活動を振り返るシェアリングの場面であった。 Rubricに基づく評定は、スタッフ12名が4グループに割り当てられ、各グループ3名ずつの評定者が配置された。評定では、Taskの中で最も多くみられた行動に該当する水準である最頻行動評定と、Taskの中で発揮された最高の行動に該当する水準である最高行動評定が求められた。 ■結果と考察■ 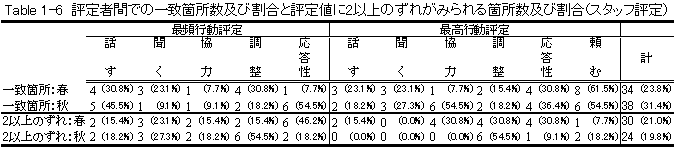 若干ではあるが、3名の評定者間のばらつきが少なくなり、一致している箇所も増えた(Table 1-6)。よって、信頼性はさらに確保されたといってよいだろう。しかし、調整スキルについては、評定者間での評定値のばらつきがみられた。 この原因について、評定者3人が予備調査と同じ要領で、協議した結果、ずれが起きたのは、場面の見逃しや、最頻行動についての数え方の問題などであった。場面の見逃しなどを統制することは難しく、完全な一致は不可能に近いと考えられた。 ★再評定★ ところで、この協議の際、3人で一つの評定値を決めている。以降それを「再評定」値とする。再評定値と、3人の評定の平均値の相関を算出したところ、全てのスキルにおいて強い正の相関関係がみられた(Table 1-7)。 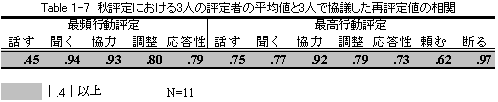 よって再評定値は、場面の見逃しを防ぐことや、信頼性の確保という意味でも利用価値のあるものであることが示唆された。 |