| ■問題と目的■ 研究2では、活動に直接関わらない学生(以下、ゲスト)による評定を実施する。活動に関わりのない人物による評定は客観的である一方で、Rubricを理解しきれず子どもの姿を正確に評定できないという危険性も予測される。よって、ゲストによる評定とスタッフによる評定とを比べることによって、ゲストでもスタッフと同じように評定することができるのかを検討する。 ■方法■ 三重大学人間発達科学課程の学生12名をゲストとした。ゲストにもスタッフと同じようにPAの解説を行った。解説時間は30〜40分であった。スタッフとゲストの評定値の比較には、秋の再評定結果を用いた。 ■結果と考察■ ゲストによる評定も、スタッフと同程度の一致率であった(Table 1-8)。 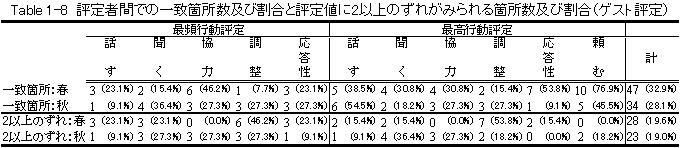 ゲストとスタッフ間の再評定値の相関関係をみると、「話す」「聞く」以外のほぼ全てのスキルにおいて、スタッフと正の相関関係がみられた(Table 1-9)。 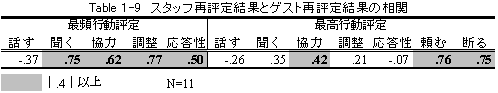 各スキルについて、スタッフとゲストという評定者によって再評定値に違いがあるかどうかを検討するため、独立変数を評定者、従属変数を各スキルの評定値とした1要因分散分析を行った結果、話すスキルの最頻行動評定において有意差がみられた(F(1,10)=6.81,p<.05)。また、聞くスキルの最頻行動評定においても有意差がみられた(F(1,10)=12.00,p<.01)。聞くスキルは最高行動評定においても有意差がみられた(F(1,10)=5.71,p<.05)。以上は、全てゲストによる評定値のほうが低かった(Figure 1-2)。 話すスキルについては、Rubricにおいて、「適切な声の大きさで話す」という段階と「最後まではっきりと話す」という段階がある(Table 1-2)。このため、声の大きさや明瞭さが話すスキルの判断には大きな要因となってくる。このことを考えると、スタッフの評定には、実際にTask実施中に接していた子どもの印象が影響を及ぼしていた可能性が考えられる。一方、ゲストにとって、話し方の声の大きさは、マイクからの音声のみによる判断であったため、聞き取れない声については適切な大きさでないという判断がされた可能性がある。ただし、評定者個人の傾向として、甘く評定する、辛く評定するなど、評定者の要因も考えられるのでこの考察が全てだとは言えない。 また、弱くはあるが負の相関関係がみられたことについても、スタッフには日頃の先入観が働いていたと考えることもできる。例えば、大きな声を出す子どもについて、スタッフが日頃「大きすぎる」と思っている子どもは、スタッフにとっては適切な声の大きさだとは判断されないが、ゲストにとっては「聞き取りやすい声」だと判断される。一方、スタッフが日頃「普通に聞き取れる声の大きさ」だと思っている子どもについて、ゲストは「聞き取りにくい声」だと判断される。このように、逆の評価になったということがこの負の相関関係の原因だとも考えられる。このことから、話すスキルについての「声の大きさ」については、あくまで録画された映像を基準とするということを定めたほうがよいだろう。 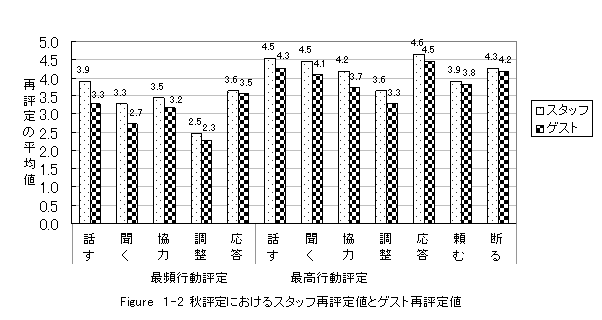 以上のことから、ゲストの評定能力については一定の信頼性が認められたといえよう。解説を充分に行えば、スタッフでない人物による評定は充分可能であることが明らかとなった。 スタッフよりもゲストのほうが有意に得点を低く評価していた箇所がいくつか見られたが、これをゲスト特有の客観性と捉えることもできる。すなわち、スタッフによる評定とゲストによる評定のどちらの値が真値に近いのかは予測できないが、スタッフは日頃の子どもの様子からの主観的な判断が影響してしまうということや、スタッフには秋に評定値が高くなっていてほしいと考える期待効果が働くという危険性を考えると、ゲストによる評定はより客観的な評定結果を表していると言えるだろう。 |