| ■問題と目的■ PAによって評価された子どものコミュニケーションスキルが、活動初期と活動後期とで変化しているかどうかを検討する。 ■方法■ 対象児童は春第2回と秋第5回に参加していた11名であり、それぞれの回のゲストによる再評定結果を比較した。 ■結果と考察■ 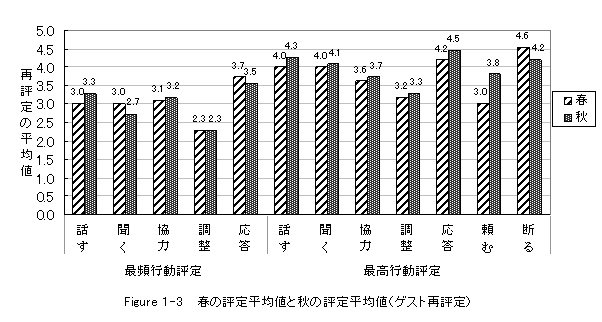 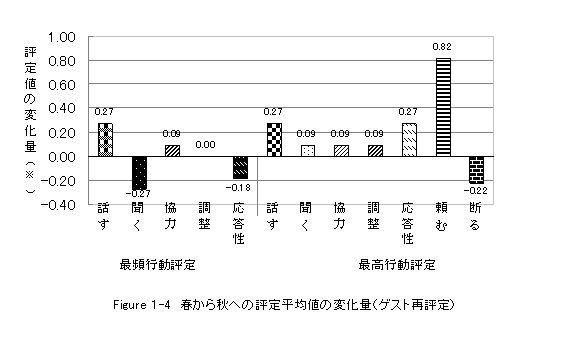 (※Figure 1-4 : 秋の平均値から春の平均値を引いた値) 各スキルについて、春と秋とで得点に差があるかを検討するために、時期を独立変数、ゲストによる再評定の得点を従属変数とした1要因分散分析を行った。その結果、最高行動評定の頼むスキルについては有意差がみられた(F(1,10)=20.25,p<.01)ほか、応答性スキルについても有意傾向(F(1,10)=3.75,p<.10)がみられた。いずれも秋の評定値のほうが高かった。 頼むスキルは他のスキルと違って、春第2回には学習していない内容であり、この変化は、わくわくコミュニケーションクラブでの学習効果を表しているといえよう。 他のスキルでは、有意差はみられなかった。しかし、評定の平均値は秋にかけて高くなっており(Figure 1-4)、最高行動評定は、断るスキル以外は全て増加していることから、子どもたちはわくわくコミュニケーションクラブで適切なコミュニケーションに必要なエッセンスを獲得しており、それを実際行動で表すこともできるようになってはいるものの、それを普段から発揮するということは難しいと考えられる。 しかし、このPAによってターゲットスキルのうち多くのスキルで水準が上がっている子どももみられた。スタッフはこの子どものことについて、PAの評定結果をもとに、わくわくコミュニケーションクラブでのどのような活動がそのスキルの向上に貢献しているのかなどを議論する機会が持てた。以下はその例である。 スタッフ1:<保護者アンケートにおいて>○○ちゃんのお母さんは、「学校の先生から2学期になって自信を持って行動していますけど、何かありましたかと言われました。」と書いています。 わくコミでの活動がちょっとでも関わってたら嬉しいですね。 スタッフ2:(スタッフ1の発言を受けて)さっきPA評定で秋クラス第5回の○○ちゃんを見ていました。 春に比べるとすごく元気になったというのは私も感じました。春は評定する材料を与えてくれないほどおとなしいというイメージだったのに、今回の評定ではたくさん意見も言ってたし、他者との会話も多かったし、すごく活発でした。少し自信があるようにも見えます。まだ全て評定したわけではありませんが、評定値も高いです。 彼女の変化の要因を特定することは難しいですが、わくコミでの活動もその1つの要因として考えてもいいのではないでしょうか? スタッフ3:私も春は○○ちゃんと同じグループではなかったのですが、秋で同じグループになって、秋クラスの中だけでも、どんどん話せるようになってきたと思います。 私から見ていて、同じグループの子からの励ましもかなり効いているなと思います。 △△ちゃんは、○○ちゃんが何か言うと、それをみんなに言ってあげな」と声をかけたりしてくれてる姿を見ました。 【以上、秋クラス第5回のPA実施時期にMoodleにおいて交わされたスタッフの会話】 (※わくコミ:わくわくコミュニケーションクラブの略) このように、PAは現実場面をありのままに測るということで、スタッフにとっても子どもの成長を捉えやすかったといえる。よって、PAを活用することは、豊富な情報を実践者にもたらしてくれるということが明らかとなった。 |