| ■問題と目的■ 教育実践活動に参加する学生スタッフは、活動を実践するに従って子どもへの関わり方や他のスタッフへの配慮や関係が変化し、その考え方や問題意識の持ち方が変化している可能性がある。そして、そのようなスタッフ内での変化は、行動や発言に表れているはずである。 わくわくコミュニケーションクラブでは、活動スタッフが毎回活動終了後に感想を書いており、この感想がスタッフ全員にメール配信され、感想を共有できるようにしている。この感想には書く内容について特に指定はしていないが、2004年度の初回からスタッフたちはこの活動後の感想の交流によって、子どもについての感想を述べたり、自分自身の行動を振り返ったり、他のスタッフへ提案をしたり、活動についての反省や次回への展望を持ったりしてきた。また、わくわくコミュニケーションクラブ全体のあり方についての記述はたびたび感想で問題になることである。つまり、各回の感想は、その時々のスタッフの活動についての考えや問題意識を反映しているものだと考えられる。 そこで研究1では、スタッフの毎回の感想をもとに、わくわくコミュニケーションクラブの3年間の活動でスタッフが獲得したものの変化と活動時期との関連を検討する。 ■方法■ わくわくコミュニケーションクラブにおいて、3年間、学生スタッフとして活動を続けてきたスタッフAの各活動回の感想を取り上げ、分類した。わくわくコミュニケーションクラブで3年間継続して活動を続けた学生スタッフはこのスタッフ1名だけであったので、このスタッフを分析対象とした。 ★分類手続き★ ①分析の対象となった感想: 感想は、e-learningシステムであるMoodleやメーリングリストに投稿されたものである。各活動回についての感想は、毎回活動終了後から2日以内に書かれていた。また、スタッフは、各クラスが終わった後にも感想を書いていた。例えば、春クラスが終わった時には「春クラス全体感想」というように、そのクラス全体について振り返る感想も書いていた。つまり、各クラスについて、活動回数分の感想と、そのクラスについての全体感想があるということになる。 対象となった感想は、2004年度春クラスの第1回感想から2006年度の秋クラスの全体感想までである。 ②感想の単位 スタッフAの記述の1段落を1個の記述と数えたところ、2004年度春から2006年度秋までの感想は、全327個の記述となった。スタッフAの感想は、活動1回につき約1500字前後であり、内容は意味内容ごとに段落分けされていた。 ③カテゴリー 藤田(2004)を参考にしつつ、わくわくコミュニケーションクラブで毎回スタッフが感想に書く主な項目を考え、著者が設定し、カテゴリー表を作成した(Table 2-2)。 ④分類の手続き 全327の記述を、スタッフAとは別の活動スタッフである学部生と大学院生2名がカテゴリーに分類した。この2名には、カテゴリー表(Table 2-1)を見て協議をしながら、あてはまるカテゴリーにチェックをするよう求めた。 また、1個の記述に対して複数箇所のカテゴリーにチェックを入れてもよいこととした。 ★分析方法★ 2004年度春クラスについての感想、2004年度秋クラスについての感想、2004年度冬クラスについての感想、2005年度春クラスのについての感想、2006年度の春クラスについての感想、2006年度秋クラスについての感想、というように、活動時期を8時期に分けた。それぞれのカテゴリーのそれぞれの時期においてチェックされた総数を、活動回数で割り、「各時期の1回あたりの記述量」とした。 例えば、あるクラスについて、活動が全6回で、6回とも出席し感想を書いており、全体感想を書いているという場合、そのクラスにおいてチェックされた総数を7で割った数が、「各時期の1回あたりの記述量」となった。 以降の分析では、この「各時期の1回あたりの記述量」の変化を見ていく。  ■結果と考察■ 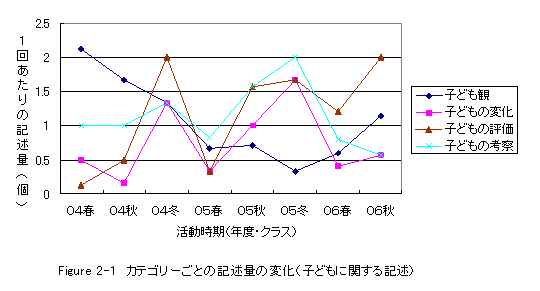 子どもについてのスタッフの発見や子どもに関する感想を表す「子ども観」について、スタッフの記述量の変化を確認するために、独立変数を時期、従属変数を各時期の1回あたりの記述量とした1要因分散分析を行った結果、有意な差がみられた(F(7,37)=3.12,p<.05)。そこで、活動時期間の差を確認するため、多重比較を行ったところ、2004年度春と2005年度秋との間に5%水準で有意差がみられた。 また、?子どもの様子についてできていることやできていないことを評価している「子どもの評価」について、スタッフの記述量の変化を確認するために、独立変数を時期、従属変数を各時期の1回あたりのの記述量とした1要因分散分析を行った結果、有意な差がみられた(F(7,37)=4.09,p<.01)。そこで、活動時期間の差を確認するため、多重比較を行ったところ、2004年度春と2006年度秋との間に1%水準で、さらに2005年度春と2006年度秋との間に5%で水準で有意差がみられた。 →単なる「子ども観」よりも「子どもの評価」のように、心理学的な理論を持って子どもを見るような視点が身に付いていくということが明らかとなった。これは、活動が長期間であることや、心理学的な背景を持っていることの影響であると考えられる。 →「子どもの評価」について目を向けられるようになることが明らかとなった。これは、05春から05秋にかけてのPAの導入を起因としていると考えられる。 ?
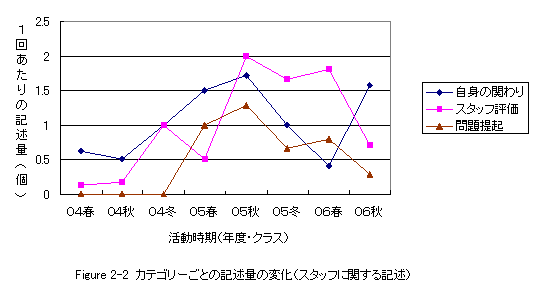 他のスタッフの行動についての評価を表す「スタッフ評価」について、スタッフの記述量の変化を確認するために、独立変数を時期、従属変数を各時期の1回あたりの記述量とした1要因分散分析を行った結果、有意な差がみられた(F(7,37)=2.70,p<.05)。そこで、活動時期間の差を確認するため、多重比較を行ったところ、2004年度春と2005年度秋との間に5%水準の有意差がみられた。 →2年目の、スタッフ内コミュニケーションの増加がみられた。これは、本活動のようにメンバー交代のあるスタッフ集団における葛藤が、その集団の発展を促したという可能性が考えられる。
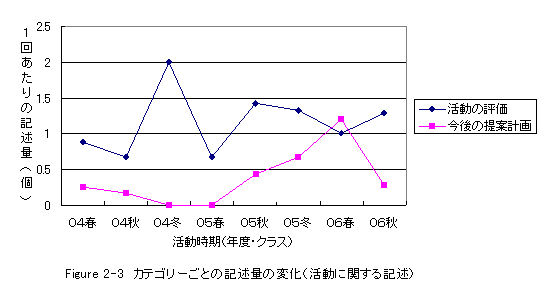 次回以降のことについての提案や計画を表す「今後の提案・計画」について、スタッフの記述量の変化を確認するために、独立変数を時期、従属変数を各時期の1回あたりの記述量とした1要因分散分析を行った結果、有意傾向がみられた(F(7,37)=2.19,p<.10)。そこで、活動時期間の差を確認するため、多重比較を行ったところ、2005年度春と2006年度春との間に5%水準の有意差がみられた。これは、PA導入により子どもの評価をしたことで、今後さらに子どもの力をのばすための活動を考えるようになったことなどが考えられる。また、2005年度春から2006年度春には記述量はコンスタントに増加しており、PA導入開発による効果は一時的でなく、そのブラッシュアップの過程で、今後の展開についてさらによく考えるために効果をもたらしていると考えることができる。 ★各カテゴリー同士の相関係数 「子どもの評価」と「子どもの変化」の記述量の変化の傾向が類似していたことから、カテゴリー間の関連を確認するため、カテゴリー間の相関関係を検討した(Table 2-2)。その結果、「子どもの評価」と「子どもの変化」については、1%水準で有意な正の相関関係が認められた。このことから、子どもの変化を見る視点と子どもを評価する視点は相互に影響し合っていることが言える。すなわち、変化を見ようとする発想が評価という観点を生み、またその評価によって子どもの変化を判断しようとするという流れが存在していることが言えるだろう。もしくは、「子どもの評価」と「子どもの変化」は、同カテゴリーである可能性もある。他にも様々なカテゴリーについて相関関係がみられた。 「子ども観」は、「子どもの評価」、「スタッフ評価」、「問題提起」などと有意な負の相関関係を示しており、「1.子どもに関する記述」での分析結果からわかるように、「子ども観」カテゴリーは、活動初期の記述量が多いのに対し、「子どもの評価」、「スタッフ評価」、「問題提起」は、活動初期は記述量が少なく活動回が進むにつれてその量が多くなっていった。すなわち、先にも述べたように、子ども観に目をむけることよりも、年度の後期になると子どもの評価やスタッフの評価、問題提起などに目をむけることがわかる。このことから、初めは子どもに対する理解や観点が単純なものに注目しているが、次第にスタッフが子どもを評価する視点が育ってくるということが言える。 さらに、「問題提起」と「スタッフ評価」が、1%水準で有意な強い正の相関関係を示している。これは、上でも述べた通り、スタッフの評価をすることで問題提起をするということや、問題意識からスタッフの行動をさらに意識させるという流れが考えられる。 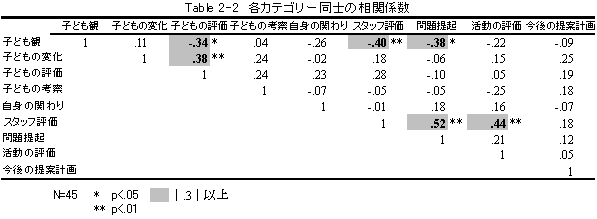 |