![]() �@���ʁ@
�@���ʁ@![]()
�������Ώێ��̊ώ@��
���c�t���N���N���X�ł͏�ʇA�S�̊����������̒��Ȃ̑̌n�̂܂ܒ��H���Ɉڍs���邱�Ƃ������������߁A��ʇ@���H���͕��͑Ώۂ��珜�����B
���ۈ牀��7������8�����܂ł͏c����ۈ炾�������߁A���͂��珜�����B
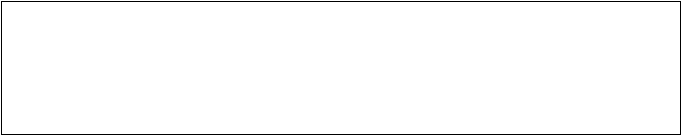
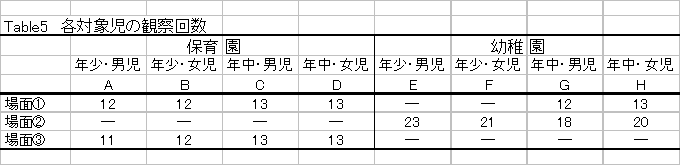
�@�ώ@��ʂɂ�葊��c����������Ƃ������Ƃ͍l���ɂ������߁A�f�[�^�͊ώ@�����Ƃɂ܂Ƃ߂��B
������̗F�����̒�`
�@�{�����ł͘A������4��̊ώ@�̂���3���������݂�ꂽ�ꍇ���A�u����̑���v�Ƃ����B����͊�1��ɓ����������݂��Ȃ��Ă��A����͋��R�ł���ƍl�����邽�߂ł���B�A�������ώ@�̊Ԃ͏��Ȃ��Ƃ�1�T�ԋ����߁A�A������4��͏��Ȃ��Ƃ�1�����ɂ킽��B1�����Ԃ̊ώ@�Ŗ����c���ɓ����������݂���̂́A���̑��肪�u���ʂȑ��݁v������ł���ƍl������B����ɉ����A�ώ@�҂��ώ@�𑱂��钆�œK�x�ȉł���Ǝv��ꂽ���߁A�{�����ł͘A������4��̊ώ@�̂���3���������݂�ꂽ�ꍇ���u����̑���v�Ƃ����B�������A�c�t���ł͉Ċ��x�����̑O���1�����ȏ�̊Ԃ��Ă��邽�߁A���̑O��̊ώ@����A�ԂɂȂ��Ă��邪�A�A�������ώ@�Ƃ݂͂Ȃ��Ȃ��B
�܂��A�Ώێ����u����̑���v�����ߎn�߂鎞���͂����B
�ώ@��1���̂�����1��ʂł������������݂�ꂽ�ꍇ���g1�h�A���������������Ȃ������ꍇ���g0�h�Ƃ��ăf�[�^���܂Ƃ߂��B�@
����̑���������납�狁�߂�悤�ɂȂ�̂����������邽�߁A�������������̔����p�x�ɊW�Ȃ��A���������̗L���̘A�����ɒ��ڂ���B����́A����c���̔����ɂ���ē������������̔����p�x�͈قȂ��Ă��邽�߁A�������������̔����p�x���K���������̑���c�������߂�C�����̋����Ɣ�Ⴗ��Ƃ͂����Ȃ��ƍl�����邽�߂ł���B
���e�Ώێ��̌���
�� �`�i�ۈ牀�E�N���E�j���j
�@�ώ@�S�̂�ʂ��ē��������͂��܂�݂��Ȃ������B��̓I�ɂ́AK(�j��)�ɑ���9������2��A11������1��AM(�j��)�ɑ���10������1��݂�ꂽ�����ł������B
�@���`�́A�ώ@���}�C�y�[�X�ȗl�q�������݂�ꂽ�B�����ւ̈ӎ��������Ă��Ȃ��ƁA��������̓��������ɂ��������݂��Ȃ�X�����������B
�� �a(�ۈ牀�E�N���E����)�@
�c����ۈ�I�����9�����߂����C(����)�ցA����ɂ��킦��10���ɂ�Y(����)�֘A�����ē������������Ă���A���҂����̑���Ƃ�����B��̓I�ɂ́AC�ւ̓���������9�����߂���11���̊ώ@�I�����܂ŘA�����Ă݂�ꂽ�BY�ւ̓���������6���ώ@�J�n������2���Ă��炵�炭�݂��Ȃ��������A10�����߂���p���I�ɂ݂�ꂽ�BC�AY�ȊO�ɂ��AD(�j��)�ɑ���2��AN(����)�ɑ���3��AI(����)�AB(����)�ɑ���1��̓����������݂�ꂽ�B
�@���a�́A���R���Ԓ��ɂ͑����Ƃ̊ւ������A1�l�œD�c�q���ɔM�����Ă���p���悭�݂�ꂽ���A�ώ@��ʂł͈ꏏ�ɍ��肽�������̖��O���ĂсA����ɐȂ��m�ۂ��Ă����Ƃ����ϋɓI�Ȏp���悭�݂�ꂽ�B
�� �b(�ۈ牀�E�N���E�j��)
�@10�����ɘA������3��O(�j��)�ւ̓����������݂��邪���̌�݂͂��Ȃ������B���̑��̗c���ɂ��܂�ɓ��������݂͂��邪�A����̑���݂͂��Ȃ��B��̓I�ɂ�O�ɑ���6����2��A10����3��AQ(�j��)�ɑ���10���E11����1�AB(�j��)�ɑ���9����1��A11����2��A���̑�4���ɑ���1�����������݂�ꂽ�B
�@���b�́A�����̉e�����₷���X�����������B���ȏ�ʂł��������瑼���ɓ�������������A�����ɂ��Ă�������A���łɍ����Ă��鑼���̂������낤�낵�A������������̂�҂��Ă���p���悭�݂�ꂽ�B
�� �c(�ۈ牀�E�N���E����)
�@10�����߂���H(����)��L(����)�֘A�����ē������������Ă���A���҂����̑���Ƃ�����BH�ւ�10�����̘A���������������ȍ~11���ɓ����Ă���͓��������݂͂��Ȃ������B����AL�ւ�10���̓��������ȍ~�ώ@�I�����܂œ����������݂�ꂽ�B��̓I�ɂ́AH�ɑ���6����3��A10����3��AL�ɑ���10������11���̊ώ@�I�����܂ŘA�����Ă݂�ꂽ�ق��A5���ɑ���1�`3��̓����������݂�ꂽ�B
�@���c�́A�ώ@�����S�ɗ��Ƃ��Ƃ���p�������݂�ꂽ�B���ȏ�ʂł́A�����ɍ���Ȃ��w������ȂǁA�ꏏ�ɍ��肽������ɐϋɓI�ɓ��������Ă����p���悭�݂�ꂽ�B
�� �d(�c�t���E�N���E�j��)
�@10�����߂���J(�j��)�֘A�����ē������������Ă���A����̑���Ƃ�����B��̓I�ɂ�J�ɑ���6���I����1��A10���E11���ɂ͊ώ@�I�����܂Ŗ����������݂�ꂽ�B�܂��AM(����)�AA(����)�ɑ���2��A��3���ɑ���1�����������݂�ꂽ�B
�@���d���A���Ȏ咣�͂��܂�݂��Ȃ����A�������ӎ����Ă���p�������݂�ꂽ�B�ϋɓI�ɑ����ɓ��������Ă��������A�ꏏ�Ɉړ�������A�����ɂ��Ă����p���悭�݂�ꂽ�B
�� �e(�c�t���E�N���E����)
�@11���ɓ����Ă���C(����)�֘A�����ē������������Ă���A����̑���Ƃ�����B��̓I�ɂ́AC�ɑ���7����1��A11���Ɋώ@�I�����܂ŘA�����ē����������݂�ꂽ�ق��AB(����)�ɑ���10����2��AM(����)�ɑ���11����1��̓����������݂�ꂽ�B
���e����́A�T�^�I��3�Ύ��炵���������������Ƃ��ł����B�����̊����f���ɕ\�����A�����Ăł���]�ʂ�ɂ������Ƃ����p�������݂�ꂽ�B
�� �f(�c�t���E�N���E�j��)
�@6�������ɂ�J(�j��)�����H(�j��)�֘A���������������������A���̎����ɂ͂���2��������̑���ł������Ƃ�����B�������A���̌�10���ȍ~��ؓ��������݂͂��Ȃ������B��̓I�ɂ́AJ�AH�ɑ���6������3�AL(�j��)�ɑ���6������2��̓����������݂�ꂽ�B
���f�́A�Ƃ��Ɏ��͂̏ɉe������邱�Ƃ����������A�����ւ̓��������͏��Ȃ��A�����ƈ�_�����߂Ă���p���悭�݂�ꂽ�B
�� �g(�c�t���E�N���E����)
�@10�����߂���I(����)�֘A�����ē������������Ă���A����̑���Ƃ�����B��̓I�ɂ́AI�ɑ���10�����߂���11���̊ώ@�I�����܂ŘA�����ē����������݂�ꂽ�ق��AF(����)�ɑ���6����2��A���̑�4���ɑ���1�����������݂�ꂽ�B
��I�́A�}�C�y�[�X�ȗl�q�������݂�ꂽ�B�������A�������C�ɂ���l�q�͌����A���肽�������ɂ��Ă����Ƃ��������������݂�ꂽ�B
�@�ȏ�A�ۈ牀�̒j��2���ɂ͓���̗F�����͌����Ȃ��������A��6���̑Ώێ��ɂ͓���̑��肪10�����납��݂�ꂽ�B
|
Table�R �e�Ώێ��̌��� |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
���ۈ牀�� |
|
|
|
|
|
|
�N���j�� |
�N������ |
�N���j�� |
�N������ |
|
�Ώێ� |
�` |
�a |
�b |
�c |
|
����̑���̗L�� |
�Ȃ� |
2�l |
�Ȃ� |
2�l |
|
�݂��n�߂����� |
�\ |
9���E10�� |
�\ |
10�� |
|
���c�t���� |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
|
|
�N�j�� |
�N������ |
�N���j�� |
�N������ |
|
�Ώێ� |
�d |
�e |
�f |
H |
|
����̑���̗L�� |
1�l |
1�l |
2�l |
1�l |
|
�݂��n�߂����� |
10�� |
11�� |
6�� |
10�� |
|
Table�S �@�����ւ̓��������̕��ρi�N��j |
|||
|
�@ |
6�E7���̓��������̕��ρi��j |
10�E11���̓��������̕��ρi��j |
�����������l���i�l�j |
|
�N�� |
2.5 |
7.5 |
4 |
|
�N�� |
5.25 |
7 |
5.75 |
�@�ۈ牀�̒j��2���������ẮA�S���ɓ���̑��肪�݂�ꂽ�B����̑��肪�݂���悤�ɂȂ鎞���́A�N�����̕������x�����̂́A���ɔN�����E�N�����ō��͌���ꂸ�A���҂Ƃ�10������ł������B���̌�̌o�߂ɂ��ẮA�N�����ł�3���̑Ώێ��ɂ݂�ꂽ5���̓���̑���c���̂����A3���ւ̓����������݂��Ȃ��Ȃ������A�N�����ł͑S�����ώ@�I�����܂œ�����c���ւ̓����������݂�ꂽ�B�܂��A�ۈ牀�ł͏c����ۈ���Ԃɓ���O�A�c�t���ł͉Ċ��x���ɓ���O��6���E7���ł́A�N�����ł͑��c���ւ̓��������̕��ς�5.25��A�N�����ł͕��ς�2.5��ƂȂ��Ă���A�N�����ł�6���̊ώ@�J�n�������瑼���ւ̓����������悭�݂�ꂽ�B�������N�����ł�3��̓����������݂�ꂽ�Ώێ���7�E8��̓����������݂�ꂽ�Ώێ�������A���̉ɂ͌l�����݂�ꂽ�B
�������̔�r
|
Table�T�@�����ւ̓��������̕��ρi���ʁj |
|||
|
�@ |
6�E7���̓��������̕��ρi��j |
10�E11���̓��������̕��ρi��j |
�����������l���i�l�j |
|
�j�� |
4.25 |
4.75 |
4.5 |
|
���� |
3.5 |
9.75 |
5.25 |
�@�j���ł́A�ۈ牀��2���̑Ώێ��ɂ͓���̑��肪�����Ȃ��������A�c�t���̑Ώێ��ɂ͓���̑��肪�݂�ꂽ�B�������A����̑��肪�݂��n�߂鎞����6����10���ł���A���̌�̌o�߂��A�c�t���̔N���j���ł͓����������݂��Ȃ��Ȃ����̂ɑ��āA�c�t���̔N���j���ł͊ώ@�I�����܂œ����������݂�ꂽ�B�ȏ�̂悤�ɒj���͑Ώێ��ɂ���Čl�����݂�ꂽ�B�����ł́A4���̑Ώێ��S���ɓ���̑��肪�݂�ꂽ�B����̑��肪�݂��n�߂鎞����9������11���Ɍł܂��Ă���A�N�����Ɋւ��Ă�2���Ƃ�10���������̑���ւ̓����������݂�ꂽ�B���̌�̌o�߂��ۈ牀�N��������2���̓���̑���̂���1���ւ̓��������͌����Ȃ��Ȃ������̂́A�c���1������сA����3���̑Ώێ��̓���̑���ւ̓��������͊ώ@�I�����܂ł݂��Ă����B
���p���铭�����������Ƃ��̎g�p�p�x
�@���ɑΏێ����ǂ̂悤�ȓ�������������p���đ��c���ւ̓��������������Ȃ����̂��͂����B
Table�U�͑Ώێ����Ƃɗp���������̎g�p�p�x�����������̂ł���B�e�ώ@��ʒ��ɂ݂�ꂽ�������������̉�30���Ԃ̔����p�x�Ɋ��Z���A�e�Ώێ��̑S���������ɐ�߂銄�����o�������̂ł���B
�ۈ牀�N���j���E��������єN�������́A����̖��O���Ăԁu��.�Ăԁv�������A�c�t���N���j���E�����́A�ꏏ�ɍ��肽������ƈꏏ�Ɉړ�����u��.��āv�������A�ۈ牀�N���j������їc�t���N���j���E�����́A��������ꏏ�ɍ��肽������̋ߗׂɈړ�����u��.�ړ��v�������ł������p�x�ŗp���Ă����B
���N��̔�r
�@�N�����ł́A�u��.�Ăԁv�A�u��.��āv�������悭�p�����Ă����B�N�����͕ۈ牀�N�������������āu��.�ړ��v�������悭�p�����Ă����B�܂��N�����ɔ�הN�����ł�1�̕�����50���ȏ���߂Ă���A�p����������قڌ��܂��Ă����B
�������̔�r
�@�j���ɂ��āA�c�t���N���j���������j���Ώێ�3���͗p����������u��.�Ăԁv�u��.��āv�u��.�ړ��v�����Ɍ����Ă����B�����ɂ��āA�ۈ牀�N���E�N�������́u��.�Ăԁv�����A�c�t���N�������́u��.��āv�����A�c�t���N�������́u��.�ړ��v�����Ƃ����悤�ɁA�悭�p��������͂قڌ��܂��Ă�����̂̒j�����������̕�����p���Ă����B�������S�̓I�ɒj�����͓��ɂ݂��Ȃ������B
�j���ɂ��āA�c�t���N���j���������j���Ώێ�3���͗p����������u��.�Ăԁv�u��.��āv�u��.�ړ��v�����Ɍ����Ă����B�����ɂ��āA�ۈ牀�N���E�N�������́u��.�Ăԁv�����A�c�t���N�������́u��.��āv�����A�c�t���N�������́u��.�ړ��v�����Ƃ����悤�ɁA�悭�p��������͂قڌ��܂��Ă�����̂̒j�����������̕�����p���Ă����B�������S�̓I�ɒj�����͓��ɂ݂��Ȃ������B
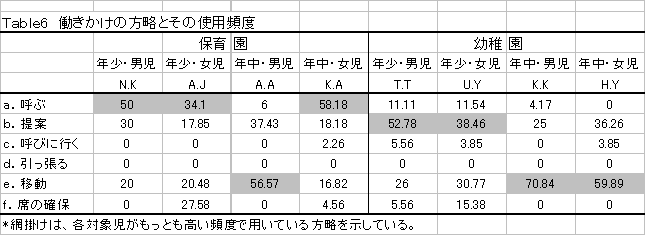
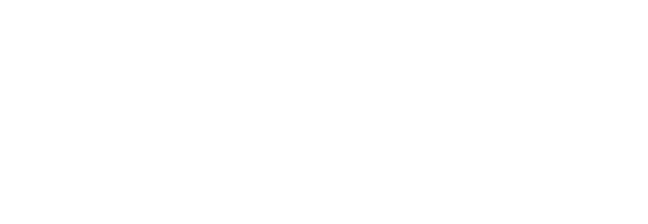
![]() �g�b�v�֖߂��@�@�@�@
�g�b�v�֖߂��@�@�@�@![]() ���@�֖߂��@�@�@�@
���@�֖߂��@�@�@�@![]() �l�@��
�l�@��