![]() �@�l�@�@
�@�l�@�@![]()
���{�����̖ړI�ƌ���
�� �ړI
�ۈ�̋���ʂɂ����钅�ȍs����ʂ��āA�c�����u����̗F�����v�����ߎn�߂鎞�����������邱��
�� ����
�E�l���͂�����̂�8����6���̑Ώێ��ɓ���̗F�������`������邱�Ƃ����������ꂽ�B
�@�@�@�E�����⓭�����������ɂ����Ă͂킸���ł͂��邪�N��E�������݂�ꂽ
�@�@���N���
�@�@�@�E����̗F�����̌`�������ɔN��͓��ɂ݂��Ȃ��������A���̌�N�����͊ώ@�I�����܂Ŏ������Ă���̂ɑ��āA�N�����͎������Ȃ����̂�������
�@�@�@�E6���E7���̑����ւ̓��������͔N�����͔N�����ɔ���Ȃ��������A10���E11���ɂȂ�Ƒ傫�ȍ��݂͂��Ȃ��Ȃ����B
��������
�@�E�j���͏����ɔ�l�����傫������
�@�E6���E7���̑����ւ̓��������͏����ƒj���ɑ傫�ȍ��݂͂��Ȃ��������A10���E11���ɂȂ�Ə����͒j���ɔ�ד����������悭�݂���悤�ɂȂ���
������̗F���������ߎn�߂鎞���Ƃ��̓���
���N��̔�r��
�@�l���݂͂�����̂̓���̗F�������`������Ă���͔̂N�����E�N�����Ƃ���10������ł������B
�� �N����
10������ɂ͔N������3�Δ�����4�ɂȂ��Ă���B
��3�Ό㔼����4�܂łɁA����̑��҂��ӎ�������ŗF�����W���`������邱�Ƃ�����Ƃ�����s����(Hartup,1992)�̌��ʂɗގ����Ă���
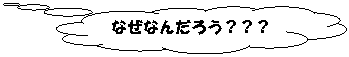
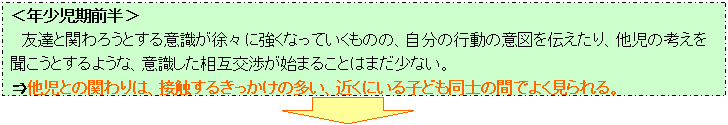
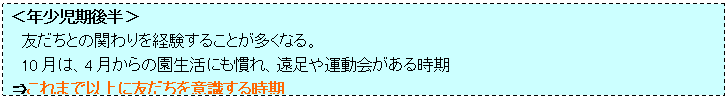
�� �N����
�@�N�����ɂ��Ă�����̗F�������`������Ă���̂�10������
��6������7���ɂ����ėV�ԑ��肪���܂��Ă���Ƃ�����s����(��,1999)�ƈ�v���Ă��Ȃ�
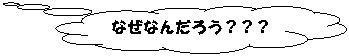
���R�@�F�Ώێ��̓����̉e��
�@�{�����̑Ώێ��͈�ʓI�ȗc����I�o���Ă�����̂́A���ȏ�ʂɂ����鑼���ւ̓��������Ɋւ��ẮA�����ɔ�ׂ�⓭�����������Ȃ��Ɗ�������c���������B���̂��߁A�{�����ł͑Ώێ��̓��������ʂɑ傫���e�����Ă���ƍl������B�����ЂƂ͌������@����ѕ��͕��@�̈Ⴂ�ł���B
���R�A�F���ڏ�ʁE���͕��@���̈Ⴂ
�@��(1999)�́A���R���Ԓ��̑����ɒ��ڂ��Ă���@�@�́@�{�����ł͊����Ԃ̋��ڂ̒��ȏ�ʂɂ����铭�������̗L���ɒ���
�˖{�����ł͐ڐG�̗L���ł͂Ȃ��A���肳�ꂽ�������������̔����ɒ��ڂ��Ă���Ƃ����_�Ŏ�(1999)�ƈقȂ��Ă���B
��(1999)�͑����Ԃɐ�߂鑊���̎��Ԃ��璇�ǂ��̗F�����f�@�́@�{�����ł́A���������̘A�����������̗F�����f
![]()
�����̂��Ƃɂ��A��(1999)�Ɩ{�����̌��ʂɍ��ق��݂�ꂽ�ƍl������B
�� �N�����ƔN�����̓���̗F���������߂鎿�I�ȈႢ
�i�P�j����̗F�����̎���
�@�N�����F����̗F�����ւ̓��������͊ώ@�I�����܂ł݂�ꂽ
�N�����F��x����̗F�����Ɣ��f����Ă��A���̌セ�̑����ւ̓����������݂��Ȃ��Ȃ�c��������
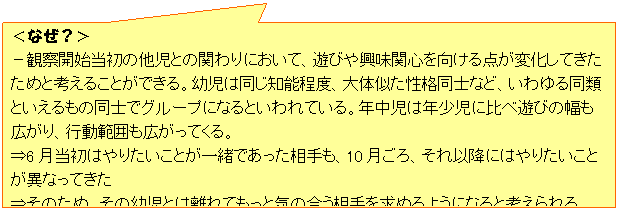
�i�Q�j6���E7���̑����ւ̓��������̗l�q�̈Ⴂ
�|6���E7���ɂ����鑼���ւ̓��������̕��ς́A�N������2.5�����̂ɑ��āA�N������5.25��ƁA�N�����̕��������݂����B������10���E11���ɂȂ�ƁA�N������7.5��A�N������7��ƂȂ�A�N�����E�N�����Ƃ��ɓ��������̕��ω͑������Ă��邪�A�N�����E�N�����̊Ԃɍ��݂͂��Ȃ��Ȃ����B
���N�����͊ώ@�J�n�������瑼���֊S���������Ă���A�����10���E11���ɂ͂��̊S�͑����Ă��邪�A�N�����̕������̕ω���������
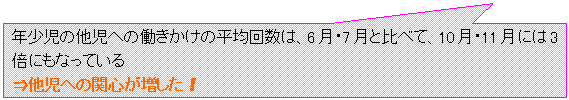
�N�������ɂ�����6���E7������͗V�т����W���Ă��炸�A�܂������Ƃ̊ւ������܂茩���Ȃ��B����ɑ��A�N�������ɂ̓R�~���j�P�[�V�����\�͂����B���A�F�����̍l���𗝉�������A�����̈ӌ���ɓ`������悤�ɂȂ�B���̂��ߔN��������6���E7������͂��łɑ��҂ւ̊S�������Ă��邽�ߓ����������N������葽���݂���ƍl������B
�������̔�r��
6���E7���̓��������̕��ώA�j��4.25��A����3.5��ƒj���ɍ��݂͂��Ȃ������B�������A10���E11���ɂȂ�Ə�����9.75��ƂȂ�j��(4.75��)��2�{�ɂ��Ȃ����B�܂��A���������������l���̕��ς͒j��4.5�l�A����5.25�l�ł���A�j���ɑ傫�ȍ��͂Ȃ��B
�������E�E�E
�@�ۈ牀�̒j��2���͓���̗F����������ꂸ�A�c�t���̒j���͓���̗F�����݂͂�ꂽ���A���̌`������n�߂���������т��̌�̌o�߂͗��҂ɗގ�����_�͌����Ȃ������悤�ɁA�j���͌l�����傫���B����A�����͑S����9������11���̂����ɓ���̗F�������݂��n�߂��B
�˒j���ɔ�����̕������҂ւ̊S�������A����ɂ���͍L���͈͂ɂ킽��̂ł͂Ȃ��A���������鑊��͂�����x���肳��Ă���ƍl������B
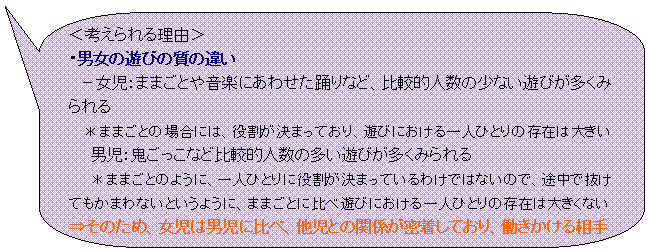
![]() �\�z�Ƃ̔�r���@�@�@�@�@
�\�z�Ƃ̔�r���@�@�@�@�@