<年齢差の比較>
■ 全体的には「a.呼ぶ」「b.提案」「e.移動」方略がよく用いられていた。
→これらは他の方略に比べるとシンプルで一般的なものとも言える。
■ 年少児は「a.呼ぶ」「b.提案」が、年中児では「e.移動」がよく用いられている。
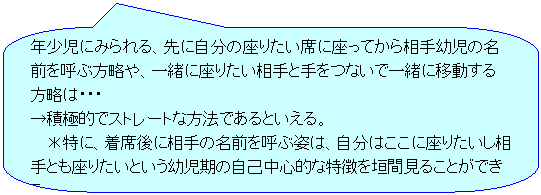
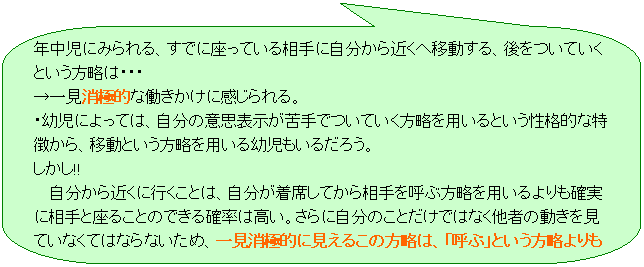
○直前の相互やり取りが観察場面の働きかけに与える影響
■ 全体的には、15.39%となり直前の相互やり取りがその後の働きかけに強く影響しているとはいえない。
■ しかし年少児は4名の平均が8.26%だったのに対して、年中児は4名の平均が22.52%と、年中児の方が直前の相互やり取りがその後の働きかけに影響を与えていることがわかる。
→その中でも保育園年中女児は、観察期間中直前にやり取りがみられた他児と隣同士に座る姿が最も多くみられた。
○観察時間中のポジティブな双方的なやり取りがその後の働きかけに与える影響
■ 全体的には13.38%となり、ポジティブな双方的やり取りがその後の働きかけに強く影響しているとはいえない。
■ しかし年少児は4名の平均が8.85%だったのに対して、年中児は4名の平均が17.79%と、年中児の方がポジティブな双方的やり取りがその後の働きかけに影響を与えていることがわかる。
→特に保育園年中児に比較的多くみられた。そのなかでも保育園年中男児は39.15%と8名の対象児の中でも最も影響が強かった。着席行動中に他児との会話が弾むとその他児についていくという働きかけがみられることがしばしばみられた。
■ 年少児では、年中児に比べ次の場面への準備をする際にその場と関係のないおしゃべりがみられることはほとんどなく、それぞれが自分のペースで動いているという印象を受けた。そのため、年少児にはほとんど観察時間中のポジティブな双方的やり取りは見られなかった。これは年中児に比べ年少児では「〜シナガラ〜スル」という力が未発達であるためと考えられる。また年少児前半はひとつのことをこなすのにかかる時間にまだ個人差が大きい。そのため、手を洗うときなどにもペースが違うため、他児と同じテンポで物事をこなしていくことはあまり見られない。
■ 年中児では、しゃべりながら手を洗い、他児とほぼ同じテンポで準備を進めていくことができるようになっている。これは片付けの際にも同じことが言える。年中児ではおしゃべりをしながら片付けるということもみられるが、年少児では片付けのときには、とにかく床に転がっているブロックをたくさん拾うことに夢中になるなど、片付けというその行為のみに注意が集中しがちである。
→→→これらのことから、年少児は年中児に比べて、直前の相互やり取り、観察時間中のポジティブな双方的やり取りの頻度が少なく、その影響も弱いと考えられる。
■ 年少女児2名については、他の対象児に比べて一人の他児を強く求める様子が観察中にみられた。
→他児への特に強い思いは、他の対象児にはみられなかったものである。これより、年少女児の他児への関心の強さがうかがえる。
■ 同じ年少児でも男児には女児のように強く他児を求める姿はみられなかった。観察中も年少児・年中児関わらず、男児に比べて女児に他児を求める姿がよくみられた。