①尺度作成と因子構成の確認
日本において学業的満足遅延研究が少ないため、以後の分析に用いるための指標が必要である。そこで、まずはADOG-Sの日本語版の作成を行う。そして、確認的因子分析を用いて因子構造の検討を行い、学業との多面的な関連の検討を通して尺度の構成概念妥当性を検討することを一つ目の目的とする。先行研究に基づき、本研究では自己調整学習方略の側面から学業的満足遅延と努力調整、メタ認知傾向との関連を検討する。さらに、学習の行動パターンの側面からは学習の持続性をとりあげる。課題や目標への認知の側面からは、課題価値をとりあげる。 ②学業的満足遅延と課題価値の因果モデル検討
さらに、具体的な目的のひとつとして、学業的満足遅延を予測しうる要因について構造方程式モデリングを用いて検討する。本研究では、大学生の学習に対する課題価値に着目する。先に述べてきたとおり、学業において取り組む課題が個人に及ぼす影響は大きい。よって大学生が現在取り組んでいる課題、つまり大学での学習への興味や実用性、コストは、学業的満足遅延の実証研究の中で扱う価値があると思われる。なお、解釈の複雑化を避けるため、自己調整学習方略に関しては尺度の妥当性検討にのみ用いることとし、今回のモデルには含めない。 仮説モデルの構成 Bembenutty(2008; 2010)やEccles & Wigfield(1995)の意見を踏まえると、学業的満足遅延は個人の課題価値のあり方に影響を受けているというモデルが仮説として考えられる。さらに、Zhang, Karabenick & et al.(2011)に基づき、学業的満足遅延は学習の持続性に影響を与えていることが予測される。モデルとしては課題の価値が直接的に学習の持続性に影響を及ぼしている場合も成り立つ可能性はある。しかし、学業的満足遅延の役割(Figure 1)を踏まえると、両者の関係は満足遅延という過程を経て持続性が成り立っているということが想定されると思われる。 すなわち個人にとって大学の学習が面白かったり、将来の役に立つと感じられるものであれば、結果として学業の達成にも意欲的になるため、学習を阻害するような欲求に意欲が向くことなく、学習に対し一貫した取り組みの姿勢が保たれるということである。逆に、個人が大学の学習にそうした価値を感じていなかったり、心理的な負担感が大きければ、先の達成目標への意識を維持できないため、学習場面において満足遅延をすることなく娯楽や学業以外の活動に傾倒するだろう。そうなると、結果として学習は持続的に行われないことが考えられる。 以上を本研究における仮説とし、構造方程式モデリングによってそれらを検討することを二つ目の目的とする。 Bembenutty(1999, 2008)では学業的満足遅延傾向は、非学業的な選択をすることと学業を選択することのそれぞれの価値を比較することが影響することまでは言われている。しかし、課題価値のうち興味や実用性、コストの側面がそれぞれどの程度影響するかまでは検討されていない。よって、本研究でその点についても検討することとし、課題価値の複数の側面を区別した重回帰のモデリングを行う(Figure 2)。
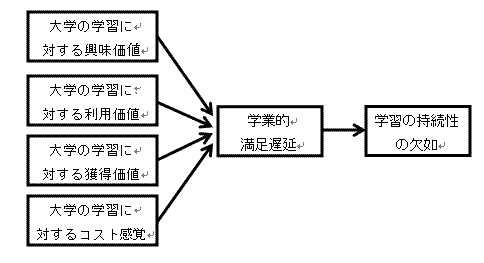
Figure 2 本研究における仮説モデル
③性差の検討
三つ目の目的は、性差の検討である。概念の一般化可能性を示す上で、作成した尺度の性差を検討しなくてはならない(小橋・井田, 2012)。先行研究より、また、性別によって学業的満足遅延とその関連概念との関係の差を調べることも必要である。そこで、目的1で作成した尺度の性差を検討することと、目的2において作成したモデルの在り方を男女で比較を行う。これらを通して、性別による学業的満足遅延の特徴を知ることを目的とする。性別によって学業的満足遅延の平均値やモデル構造に差が現れない場合、今回作成した尺度で学業的満足遅延が男女で共通の測定が行われているということが支持される。また、差が現れた場合も、男女で異なる側面を持つ概念としての新たな知見を得ることができるだろう。それらを検討するため、本研究でモデルの構造の違いだけでなく、男女の課題価値の側面が学業的満足遅延に及ぼす影響力の違いについても注目しておきたい。 以上が本研究における3つの目的である。これまで述べたとおり、学業的満足遅延は自己調整学習方略の使用、持続性などの学習行動のパターン、動機づけなどそれぞれにおいて説明力を持つ重要な概念である。尺度を作成してこれを測定し、他の要因にどう影響を受けるのか、または影響を及ぼすのかというプロセスや性差の違いについて検討を行うことは、今後の研究において、学業的満足遅延の役割的な位置づけや概念の一般性に有効な示唆を与えることになるだろう。
TOP