尺度の作成と因子構成について
Bembenutty & Karabenick(1998)では、学業的満足遅延の尺度が作成されている。これまでの満足遅延の研究において、その測定は実験による一時的なものであった。学業的満足遅延では、個人の長期的な学業目標が遅延報酬にあたるため、仮想的な実験課題では捉え難い部分があるとされた。そのため彼らは回答者の実生活に沿った質問によって学業的満足遅延の測定をする必要があるとして、尺度による測定が必要であるとした。質問項目は大学生の多様な学業的経験を基に作成された。学業的経験とは、試験前の行動や勉強に関わる対人関係、図書館の利用などである。このような複数の場面を項目ごとに定め、それぞれの場面に対し、満足遅延を選択する行動(A)と、満足非遅延を選択する行動(B)の2種類の文を対比させて提示した。そして、回答者にどちらの行動を選択するかを「確実にAを選ぶ(“Definitely choose A”)」、「恐らくAを選ぶ(“Probably choose A”)」、「恐らくBを選ぶ(“Probably choose B”)」、「確実にBを選ぶ(“Definitely choose B”)」の4段階で評価させ得点化した。これにより、得点が高い程学業場面での満足遅延傾向が高く、低い程満足非遅延傾向が高いということで測定を行った。 因子分析の結果から、学業的満足遅延が2因子からなる概念であることが確認された。1つ目の因子は満足非遅延を選択する行動に「試験が近付くまで勉強はせずに、直前に猛勉強をする」などの社会的要素を含まないものであった。2つ目の因子は、「テストで悪い成績を取るかもしれないが、友達の集まりに行く」など、満足非遅延に社会的要素を含むものであった。このことから、学業的満足遅延尺度は多面的な測定ができていることが確認された。なお、Bembenutty & Karabenick(1998)は分析の段階で、下位因子ごとの分析は信頼性が落ちることを示しており、彼らを含む研究者たちは、それ以降の分析や考察は2つの因子をまとめて扱っている(Bembenutty, 2010; Mehdi, et al. 2012; Zhang, et al. 2011)。潜在因子についてはさらなる検討が望まれている。
学業的満足遅延と関連する概念について
Bembenutty & Karabenick(1998)の研究において作成された学業的満足遅延尺度に対し、構成概念の信頼性が確認された。以後もいくつかの研究において尺度の信頼性が検討されている。(Bembenutty, 1999,2007a, 2007b, 2008, 2010; Bembenutty & Karabenick, 2004; Zhang, Karabenick, Maruno & Lauermann, 2011)では、その妥当性に関して、どのような心理学的概念と学業的満足遅延が関係するのだろうか。以下より、学業的満足遅延に関連する概念とその実証研究について述べていく。
自己調整学習方略との関連
学業的満足遅延はその性質から、自己調整学習方略との関連が強く示唆されている。実際、学業的な達成を得るためには様々な方略の使用が重要であると言われている。Zimmerman(1989)は、自己調整学習方略を、学習に関わるメタ認知や動機づけ、行動などの側面において自己調整を行いながら積極的に取り組む学習のあり方としている(伊藤,2007による)。具体的には、学習者がまず予見の段階において自分の興味や効力感の程度を把握したりしながら、目標設定や計画立てを行う。次に遂行コントロール段階においてうまく遂行がなされるように、自己教示をしたりモニタリングを行いながら学習課題に取り組む。最後に自己省察の段階において、学習の自己評価や結果の原因帰属を行うことでまた予見の段階に進む。こうした循環プロセスによって学習が効率的で動機づけの高いものになり、結果継続的な学習にも繋がっている。学業的満足遅延をおこなうことは、学業達成に向けて適切なセルフ・コントロールをすることに値するため、自己調整学習方略とは根強い関連がうかがえる。 Bembenutty & Karabenick(1998)はこうした知見にもとづき、Pintrich & Garcia(1992)のMSLQ(Motivated strategies for learning questionnaire)と学業的満足遅延の関連を検討している。MSLQとは、自己調整学習方略の使用や、学習への自己効力感、テスト不安等の学習の動機づけに関わる要因を多面的に測定する尺度である。方略に関しては、難しいことにも辛抱づよく取り組もうとする「努力調整」、効率良く効果的に学習を進めようとする「認知的方略」、自己の理解度を把握したり学習計画をたてることに関する「メタ認知的方略」、うまく時間をやりくりしようとする「時間のマネジメント」や、与えられた資源を学習に活かそうとする「学習資源の活用」があり、学業的満足遅延傾向と全ての学習方略の間で正の関連が見られている。 その後の研究においても統計的に同様の結果が得られており(Bembenutty & Karabenick, 2004; Bembenutty, 2007a)、学業的満足遅延と自己調整学習は互いに重要な関係にあるとして解釈されている。
学習の行動パターンとの関連
学業的満足遅延は実際の学習行動を反映することも明らかになっている。実証研究で測定される学業的満足遅延は質問紙による自己申告で測定されるものであるため、個人の認知的な傾向が明らかになるのみである。よって、実際の学習場面でどのような行動をとるかまでを把握することは研究の課題とされている。その点について、Zhang, Karabenick, Maruno & Lauermann(2011)は、小学生の試験前の数週間の学習時間を調査し、併せて測定した学業的満足遅延傾向の高さによって生徒の学習時間の推移の違いを比較している。その結果、学業的満足遅延傾向の高い生徒は数週間前から継続的に学習を行っていたことに対し、低い生徒は試験前まで勉強をあまりせず、試験が迫ってから急激に学習時間が増えるということが明らかになっている。 また、取り組んだ教科についても両群に差が見られている。学業的満足遅延傾向の高い生徒は教科の好き嫌いによって学習内容に偏りが出ることなくまんべんなく取り組んでいたのに対し、低い生徒は急激に学習時間が増えたとしても好きな科目を集中的に勉強する傾向にあった。これにより、学業的満足遅延が高い生徒は、学習行動において日頃からの継続的な勉強の必要性を理解し、ある程度の欲求を我慢しながら学習に取り組んでいるということが示唆されている。さらに、苦手な科目に取り組みたくないという回避的な欲求に対しても、学業達成という目標をもって欲求をコントロールし勉強していることも明らかになったといえる。こうした結果から、学業的満足遅延が学習行動を予測するということが示唆されている。
動機づけ的要因との関連
課題価値との関連
動機づけ理論を基に、学業的満足遅延が学習者が取り組む課題への認知から影響を受けるということも示唆されている。Atkinsonの期待×価値理論(expectancy-value theory, 1964)は、学習者の課題に対する期待と価値の関数によって行動の達成動機づけが決まるというものである。Eccles & Wigfield(1995)は、課題によって得られる報酬、つまり課題の価値が直接的に課題への取り組み活動を引き起こしたり、望ましい結果を得る上での間接的な役割として取り組み活動を起こさせると述べている。彼女らは、そうした課題の価値を具体的に「獲得価値」、「内発的価値・興味」、「実用性」、「コスト」に分類している。獲得価値とは課題の達成そのものに人間的な価値としての重要性を感じていることである。内発的価値・興味とは、課題の内容や取り組みそのものに面白みや楽しさを感じていることである。実用性とは、課題を達成することで、先々の目標に役に立つと考えることである。最後に、コストとは、先の3つとは対照的に課題への取り組みによってこれから自分は何かを失うか、諦めなくてはならないか、もしくはどれぐらい苦しむかなどの課題に対する個人的な負担感を指す。これらの主観的な課題価値は、課題に対する関与の程度や、動機づけによる学習行動の選択を予測することとしてEccles(1983, 2005)によってモデル化されており、多くの実証的研究でも明らかにされている(Meece, Glinke & Burg, 2006; et al.)。 Bembenutty(2008; 2010)によって、大学生の中で学業的満足遅延傾向の高い者は、学業に対して高い期待を持っていたことが明らかにされている。また彼らは満足遅延傾向の低い者に比べ、勉強に対し興味を持ち、その実用性を感じていたことも明らかにしている。これらの結果によって学業的満足遅延を行うか否かの動機づけにおいて課題への期待と価値が影響を及ぼしている可能性が示唆されている。実際我々はものごとの必要性を感じなかったり成功の予測が立ちにくければ、実行に移すことは難しいだろう。課題への取り組みが自分にとって価値あるものであることを理解していれば、即時的または衝動的な非学業的欲求の前にも、望んだ学業達成に向けて課題を優先させていくことが考えられる。
達成目標との関連
動機づけ理論において、学業的満足遅延は目標理論の観点からも重要視されることにも触れておく(Bembenutty, 1999)。これは学業的満足遅延の遅延報酬にあたるものが学業の達成目標であるからである。ここでの目標理論とはElliot(1999)が唱えた動機づけ理論である。Elliot & Church(1997)やRawthome & Elliot(1999)は様々な達成目標の研究を概観し、学習者が課題の達成に向けて抱く目標は3つの視点から捉える事が出来ると述べている。1つ目が「面白いから取り組みたい」や「自分のためになる」といった熟達目標である。2つ目は「他者に認められたい」といった、積極的に結果や評価を求める遂行接近目標である。3つ目は「失敗を他者に笑われたくない」という、遂行回避目標である。 Bembenutty(1999)がこれら3つの達成目標志向性によって学業的満足遅延がどう異なるかについて大学生を対象に比較検討を行っている。結果から、熟達目標志向が最も高い学生は学業的満足遅延が高かったが、熟達目標と並んで遂行接近目標が高い学生も同様の傾向であったとされている。一方で、遂行回避目標志向的な学生の学業的満足遅延は先に述べた目標志向の学生より低かったことが明らかになっている。Bembenuttyは同研究において、個人の達成目標の在り方によって学業的満足遅延が予測されうると結論づけている。
以上より、さまざまな動機づけ理論においても学業的満足遅延が重要な意味を持つものであることが示唆されている。現段階では課題や目標への認知が学業的満足遅延を予測しうるものと考えられている。課題価値と達成目標はConley(2012)の統合的な視点によって両者が強い関連を持つことが述べられており、学業的満足遅延研究においてのそれぞれの結果も独立したものではないと考えられる。そのため、動機づけの視点から学業的満足遅延の一定の知見を得るために、より多くの実証研究を重ねることが必要である。
その前段階として、Zhang & Maruno(2009)は学業的満足遅延の研究を動機づけの観点から概観している。彼らは同研究において、長期的な目標を定めた学習課題への取り組みのプロセスにおける学業的満足遅延の役割を、以下のモデルによって示されると述べている(Figure 1)。
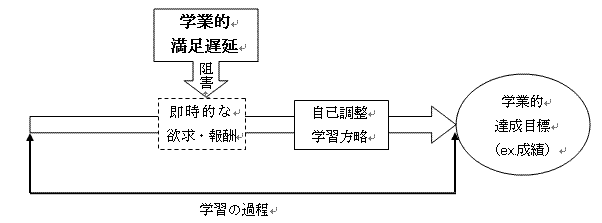
Figure 1 長期的な学習過程における学業的満足遅延の役割モデル
(Zhang & Maruno (2009)のモデルを一部修正したもの)
このような考察は現段階ではあくまで理論上のものである。なぜなら、縦断的な調査による因果関係の検討は未だ行われていないからである。学業的満足遅延傾向が、自己調整学習方略の使用を促しているのか、自己調整学習方略の使用が結果として学業的満足遅延として即時的な報酬に向かう行動を抑えているのかは定かではない。
また、目標や上記のモデルに含まれていないが課題の価値についても同様である。学習目標があることや学習課題への価値を感じていることで学業的満足遅延傾向が高められているのか、それとも、もともと学業的満足遅延傾向が高いことから、学習目標を重視するようになったり学習課題への価値を感じるようになっていくのだろうか。先行研究では、理論的に学業的満足遅延と関連する要因とその因果関係が示唆されているものの、実証的な面では曖昧である。Zhang & Maruno (2009)は学業的満足遅延との因果的関係が予測される要因についての更なる研究の必要性を指摘している。
文化・性差について
学習への取り組みに影響を及ぼす要因は、方略や目標の在り方だけではない。それらは個人の生得的な要因や環境など様々である。学業的満足遅延研究において、文化差や性差についての検討もされている。このような個人の特徴を考慮することは、概念の妥当性や他の要因との関連を説明するにあたって重要な点である。Bembenutty(2007a)やZhang & Maruno(2009)は、学業的満足遅延の研究を概観したうえで、一般化可能性について言及している。本研究において国内での調査を行うにあたり、諸外国での尺度作成研究と学業的満足遅延の性差について詳しく述べておきたい。
4-3.1学業的満足遅延の多文化圏における尺度
Bembenutty(2007b)では、一般化可能性に向けた異文化での幅広い検討を目的として、韓国の大学生を対象にBembenutty & Karabenick(1998)と同様の調査を行っている。その結果においてアメリカと同様に、韓国の大学生についても学業的満足遅延と自己調整学習方略の間には正の関連がみられている。また、学業的満足遅延は調査時の学生の期末成績とも正の関連を示しており、結果から学業的満足遅延が自己調整学習における重要システムとして信頼性を持つものであると述べている。Zhang & et al(2011)は小学生対象ではあるが、アメリカと中国圏において同尺度を翻訳・応用し、十分な信頼性を確認している。Mehdi , Parvin, Ali & Javad(2012)も大学生を対象に学業的満足遅延のペルシア語版尺度を作成し、その結果学業的満足遅延尺度が異なる文化圏においても信頼に値する指標であることを示した。
学業的満足遅延の性差
まず、セルフ・コントロール研究において、日常の一般的な満足遅延の性差は青年期・成人期においてみられないとされている(小橋・井田, 2012)。これはしばしば性差が取り上げられる幼児・児童期とは異なり、個人の自己制御が充分に機能する、つまり自律的な段階にあることによる。このことは、自律的な学習という点で学業的満足遅延にも当てはまる。
Mehdi & et al.(2012)では作成した尺度の確認的因子分析を男女別に行い、男女で因子分析の結果に違いが現れなかったことを報告している。彼らはこのことから、学業的満足遅延が男女共通の概念であることを示唆している。さらに、共通概念であることが示されたメリットとして、自己調整学習方略研究における、方略使用の性差に対する根拠となりうることを述べている。男性と女性で自己調整学習方略の使用が異なるのは、学業的満足遅延の機能が性別によって異なるからであるという説明が可能になると示唆している。
Bembenutty(2007a)では、自己調整学習方略と学業的満足遅延、学業成績の関係の個人差について、性別要因と民族要因(Caucasian or minority)が及ぼす影響が検討されている。彼は調査対象者を、性別と、出身がコーカサス民族かそれ以外の少数民族かについて2×2の4群に分類した。そして、群同士で各変数の平均値の差や関連の有無について検討している。その結果、学業的満足遅延と認知的学習方略の間には全ての群において有意な関連がみられたのに対し、学習のメタ認知傾向との関連が、少数民族の男性においてのみ有意ではないという結果を示している。また、コーカサス民族の男性と少数民族の女性の間にのみ、前者が後者より学業的満足遅延が有意に低いという差がみられたことも報告している。しかしながら、学業成績に関してはコーカサス民族の男性の方が少数民族の女性よりも高かったという結果となっている。民族によっては性別が学業的満足遅延と学習方略の双方において興味深い違いを生み出していることが分かる。
これらより、学業的満足遅延の性差による違いを、文化を超えて検討することは概念自体の信頼性を測るだけでなく、学習方略に焦点を置いた教育的アプローチへの汎用性の点で有効であることがうかがえる。
これまでアメリカ、中国、韓国、ペルシアの諸地域において学業的満足遅延の概念と尺度の信頼性が確認されている。日本国内では、先に述べたとおり学業場面でその必要性が望まれているにも関わらず(宮崎ら, 2002)、学業的文脈に沿った満足遅延を尺度測定によって扱った研究はほとんどみられない。そのため、日本の学業的満足遅延を測定する指標は存在していない。これまで述べてきた研究者たちは、学業的満足遅延の定義を述べるにあたり、高い学業成績をもたらすものであることを強調している。日本においても学業達成の背景要因のひとつとしてこれを知る尺度は必要であると思われる。
TOP