
丂偦傟偧傟偺巋寖偺摿挜偵偮偄偰偼埲壓偺傛偆偱偁偭偨丅
倎丏慺嵽偑戝偒偔丄悈傪擖傟偨巋寖偺偆偪偱嵟傕抁帪娫偱梕婍撪傪棊壓偡傞丅岝傪斀幩偡傞丅
倐丏慺嵽偑戝偒偔丄悈傪擖傟偨巋寖偺偆偪偱倎偺師偵棊壓帪娫偑抁偄丅們偲傎傏摨偠帪娫傪梫偡傞丅
岝傪斀幩偟側偄丅
們丏慺嵽偑彫偝偔丄悈傪擖傟偨巋寖偺偆偪偱倐偲摨條丄倎偺師偵棊壓帪娫偑抁偄丅岝傪斀幩偡傞丅
倓丏慺嵽偑彫偝偔丄悈傪擖傟偨巋寖偺偆偪偱嵟傕棊壓帪娫偑挿偄丅岝傪斀幩偟側偄丅
倕丏慺嵽偑戝偒偔丄岝傪斀幩偡傞丅悈拞偺傕偺傛傝傕棊壓帪娫偼抁偄丅
倖丏慺嵽偑戝偒偔丄岝傪斀幩偟側偄丅悈拞偺傕偺傛傝傕棊壓帪娫偼抁偄丅

嘥丏拲帇峴摦偺慡懱揑側孹岦偵偮偄偰
幚尡偼丄採帵偟偨偲偒丄旐尡帣偑巋寖偵婥偯偔傛偆偵峴偭偨丅慺嵽偑棊壓偡傞偲偙傠偐傜寁應傪奐巒
偟偰偄傞偑丄偙偺偲偒偵拲帇偑巒傑偭偰偄傞傕偺偑傎偲傫偳偱偁偭偨丅
丂偙偙偱丄巋寖倕丄倖偵偮偄偰峫偊偰傒傞丅偙偺俀偮偺巋寖偼悈偑擖偭偰偄側偄傕偺偱偁傞丅偲傕偵丄
尒偐偗忋丄拲帇棪偑崅偔側偭偨偑丄偙傟偼丄抁帪娫偵棊壓偡傞懳徾偑堷偒婲偙偡拲帇偺寢壥偲峫偊傜傟
傞丅悈偺擖偭偨懠偺巋寖偵斾傋丄慺嵽偺棊壓帪娫偑抁偔丄傛偭偰採帵帪娫傕抁偔側傝丄巋寖偵廤拞偟傗
偡偐偭偨偙偲偑嫇偘傜傟傞丅偙偺偙偲偼丄拲帇夞悢偑彮側偔丄侾夞拲帇帪娫偑抁偄偙偲偐傜傕柧傜偐偱
偁傞乮Fig.侾,俀,俁乯丅
傑偨丄倕丄倖偼悈偺擖偭偨巋寖傛傝傕懍偔丄傑偲傑偭偰棊壓偡傞偨傔丄慺嵽偺堦偮傂偲偮傪嬫暿偡傞偙
偲偼偱偒側偄偑丄梕婍撪傪妸傝棊偪偰偄偔慺嵽偺摦偒傪慡懱揑偵擣抦偟傗偡偄丅偙偺偙偲偐傜丄愒偪傖
傫偺岲傓帇妎巋寖偺丄摦偔傕偺丄偲偄偆梫慺偑丄拲帇傪堷偒婲偙偟偨偲傕峫偊傜傟傞丅
偟偐偟丄偙偺俀巋寖偺拲帇棪丄拲帇夞悢丄1夞拲帇帪娫偵嵎偑尒傜傟側偄偙偲偐傜丄旐尡帣偼岝傪斀幩偡
傞偐丄斀幩偟側偄偐偲偄偆揰偱慺嵽傪嬫暿偟偰偄側偐偭偨偲偄偊傞丅棊壓懍搙偑懍偄偙偲丄棊壓帪娫偑
抁偄偙偲偱丄巋寖傪偠偭偔傝尒暘偗傞偙偲偑偱偒側偐偭偨傕偺偲巚傢傟傞丅偦偺偨傔丄巋寖偺擣抦偼丄
悈拞偱偺慺嵽偺備偭偔傝偲偟偨摦偒偵懳偡傞斀墳偐傜傒偰偄偒偨偄偲峫偊丄埲壓偱偼丄悈偺擖偭偨巋寖
偵拲栚偟偰偝傜偵暘愅傪壛偊偨丅
Fig 1 巋寖暿暯嬒拲帇棪
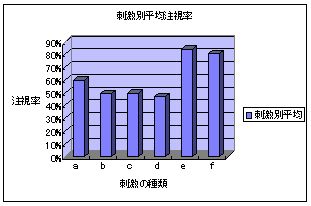 Table 3丂暘嶶暘愅
Table 3丂暘嶶暘愅
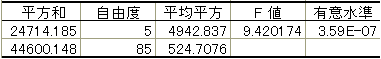
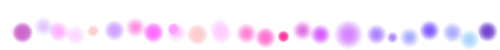 Fig 2 巋寖暿暯嬒拲帇夞悢
Fig 2 巋寖暿暯嬒拲帇夞悢
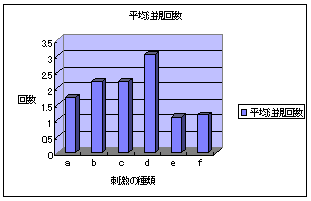 Table 4丂暘嶶暘愅
Table 4丂暘嶶暘愅
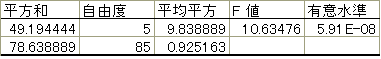
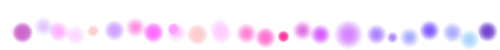 Fig 3 巋寖暿暯嬒拲帇棪
Fig 3 巋寖暿暯嬒拲帇棪
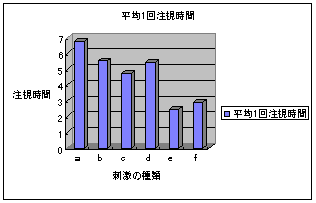 Table 5丂暘嶶暘愅
Table 5丂暘嶶暘愅
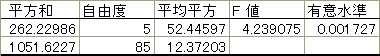

嘦丏悈拞偱偺慺嵽偺摦偒偵懳偡傞斀墳偵偮偄偰
丂悈偺擖偭偨巋寖倎丄倐丄們丄倓偺拲帇棪丄拲帇夞悢丄1夞拲帇帪娫偺暯嬒偺斾妑偐傜丄拲帇夞悢偵偍偄
偰巋寖倎偲倓偺娫偱桳堄側嵎偑傒傜傟偨寢壥偵偮偄偰偱偁傞偑丄傑偢偙偺俀巋寖偺摿挜偲偟偰丄巋寖倎偼
戝偒偔丄岝傪斀幩偡傞慺嵽偱丄暯嬒棊壓帪娫偼侾係丏俈昩偲丄嵟傕棊壓懍搙偑懍偐偭偨丅偦偟偰丄巋寖倓
偼彫偝偔丄岝傪斀幩偟側偄慺嵽偱丄暯嬒棊壓帪娫偼俀係昩偲嵟傕挿偔丄棊壓懍搙偑抶偐偭偨丅棊壓帪娫丄
偮傑傝採帵帪娫偑挿偄偲偄偆偙偲偼拲堄偑巋寖偐傜偦傟傗偡偄偲偄偆偙偲偱偁傝丄偦偺偨傔拲帇夞悢偑懡
偔側偭偨偲傕峫偊傜傟傞丅偟偐偟丄巋寖a偲倓偱偼岝偺斀幩丄戝偒偝偺俀揰偱堎側傞摿挜傪帩偭偰偄傞偙偲
偐傜丄埲壓偱偼偙傟傜偺摿挜偵暘偗偰丄峫偊偰偄偒偨偄丅偨偩偟丄拲帇夞悢偵偍偗傞巋寖倎偲倓偺娫偵偟
偐桳堄側嵎偑尒傜傟側偐偭偨偨傔丄峫嶡偼暯嬒乮暯嬒傪帵偟偨僌儔僼乯傪嶲徠偡傞丅
乮侾乯岝傪斀幩偡傞偲偄偆忦審偵偮偄偰
僌儔僼偐傜偼丄倎偑嵟傕崅偄拲帇棪傪帵偟偰偄傞偙偲偑暘偐傞丅戝偒偝偑摨偠偱偁傞丄a偲倐丄們偲倓傪
偦傟偧傟偱傒偰傒傞偲丄偲傕偵岝傪斀幩偡傞慺嵽偺暯嬒拲帇棪偑崅偄孹岦偑偁傝(Fig.1)丄偙傟傛傝岝傪斀
幩偡傞偲偄偆摿挜偑拲帇傪懀偡偙偲偑峫偊傜傟傞丅傑偨丄拲帇夞悢偵偍偄偰傕岝傪斀幩偡傞慺嵽偱偼夞悢偑
彮側偄偲偄偆孹岦偑尒傜傟(Fig.2)丄偙偺偙偲偼岝傪斀幩偡傞慺嵽偑拲堄傪傂偒偮偗傞偙偲傪帵偟偰偄傞偲
巚傢傟傞丅偮傑傝丄愒偪傖傫偺岲傓偲偝傟傞帇妎巋寖偺丄岝傞傕偺丄偲偄偆梫慺偑丄傛傝拲帇傪堷偒婲偙偟
偨傕偺偲峫偊傞偺偱偁傞丅
乮俀乯戝偒偝偲偄偆忦審偵偮偄偰
丂師偵戝偒偝偵傛傞堘偄傪専摙偡傞丅岝傪斀幩偡傞偐偟側偄偐丄偲偄偆愭偺峫嶡偲摨條偵丄暯嬒拲帇棪偲暯
嬒拲帇夞悢傪尒偰傒傞偲丄拲帇棪偱偼丄c偵懳偟a偑丄d偵懳偟倐偑崅偔側偭偨丅悈偺擖偭偨巋寖偱偼丄棊壓傪
巒傔偰偟偽傜偔偡傞偲丄慺嵽偑傑偲傑偭偨慡懱揑側摦偒偱偼側偔丄堦偮傂偲偮偵暘偐傟偰棊壓偡傞丅傛偭偰
慺嵽偑彫偝偔側傞偲丄擣抦偟偵偔偔偔側傞偙偲偑峫偊傜傟傞丅偮傑傝丄3倣倣妏偺彫偝偄慺嵽偺傕偺偼丄
俈倣倣妏偺戝偒偄慺嵽偺傕偺偵斾傋丄廤拞偟偨拲帇傪堷偒婲偙偟偵偔偄偲尵偊偦偆偱偁傞丅
丂
乮俁乯悈拞巋寖慡懱傪傒偰
丂偙偙偱彮偟丄巋寖偺棊壓帪娫偵偮偄偰傆傟偰傒傞丅巋寖a偲倓偺暯嬒拲帇夞悢偵偮偄偰偺峫嶡偱丄採帵帪娫
偑挿偄偨傔偵拲帇夞悢偑懡偔側傞偲偄偆壜擻惈傪弎傋偨偑丄倐偼們偵斾傋俆昩嬤偔懡偄帪娫偑偐偐偭偰偄傞
偵傕偐偐傢傜偢拲帇夞悢偵偼嵎偑側偐偭偨丅偙偺偙偲偐傜丄採帵帪娫偺挿偝偺傒偑拲帇夞悢偵塭嬁偡傞偺偱
偼側偄偲巚傢傟傞丅偦偟偰丄暯嬒拲帇棪偺僌儔僼偐傜傕摨偠傛偆偵峫偊傜傟丄愒偪傖傫偑丄巋寖偺戝偒偝傗丄
岝傪斀幩偡傞偐偟側偄偐丄傑偨丄偦偺懍搙側偳偲偄偭偨帇妎揑側摿挜傪嬫暿偟偰偄傞偙偲傪帵偡寢壥偲尵偊
傛偆丅暯嬒1夞拲帇帪娫偐傜偼丄岝偺梫慺偲戝偒偝偺梫慺偵暘偗偰斀墳偺堘偄偵偮偄偰峫嶡偡傞偙偲偼擄偟偄
偑眰眰艂鄠鈧蛡鑾h寖倎偺1夞拲帇帪娫偑嵟傕挿偔側偭偰偍傝丄偦傟偩偗廤拞偟偨拲帇偱偁傞偙偲偑暘偐傞
(Fig.3)丅
丂埲忋偺揰傪傆傑偊丄悈拞偺慺嵽偺摦偒傊偺斀墳傪傑偲傔傞偲丄岝傪斀幩偟側偄慺嵽傛傝傕岝傪斀幩偡傞慺
嵽偑丄彫偝偄慺嵽傛傝傕戝偒偄慺嵽偑傛傝愒偪傖傫偺拲帇傪懀偟丄傛偭偰丄拲帇偵桳岠側偙傟傜偺梫慺傪暪
偣帩偮巋寖a偵偍偄偰丄嵟傕廤拞偟偨拲帇偑娤嶡偝傟偨偲巚傢傟傞偺偱偁傞丅
丂偝傜偵岝傪斀幩偟側偄偙偲丄彫偝偄偙偲偵壛偊丄巋寖倓偼丄悈偺擖偭偨慺嵽偺拞偱傕摿偵慺嵽偺棊壓帪娫
偑挿偔丄偦傟偩偗慺嵽偑偲偰傕備偭偔傝棊壓偟偰偍傝丄摦偒偲偟偰擣抦偟偵偔偄偲峫偊傜傟傞丅偮傑傝丄巋
寖倓偼懠偺巋寖偵斾傋拲帇傪堷偒婲偙偟偵偔偄傕偺偱偁偭偨偲偄偆偙偲偱偼側偄偐丅
丂偦偟偰丄岝傗戝偒偝丄懍搙偲偄偭偨忦審偑憡屳偵嶌梡偟偰丄愒偪傖傫偵偲偭偰揔搙側丄偄偄巋寖偲側傞偙
偲偑峫偊傜傟傞丅

嘨丏壛楊偵敽偆曄壔偵偮偄偰
怴惗帣偺帇椡偑侾儢寧偺娫偵戝恖偵嬤偯偔傛偆偵丄愒偪傖傫偺敪払偼傔偞傑偟偄丅愒偪傖傫偺敪払偲巋寖拲
帇偲偺娭學傪傒傞偨傔丄偙偙偱偼丄悈偺擖偭偨巋寖偵偮偄偰丄俆儢寧楊偛偲偵嬫愗偭偰斾妑偟偨丅
丂俉亅侾俀儢寧帣偲侾俁亅侾俈儢寧帣偺娫偱偺傒憤巋寖偺暯嬒拲帇棪偵桳堄側嵎偑傒傜傟偨偑丄慡懱傪傒傞偲丄
俁亅俈儢寧帣偵斾傋俉亅侾俀儢寧帣偺拲帇棪偑掅偔丄侾俁亅侾俈儢寧帣偱偼嵟傕崅偄丅侾俉亅俀俀儢寧帣偱偼
俁亅俈儢寧帣傛傝傕彮偟崅偄抣傪帵偟偨丅
丂愒偪傖傫偺敪払偐傜傒傞偲丄俉亅12儢寧帣偼恖尒抦傝丒応強尒抦傝偑嫮偄偲偝傟傞帪婜偱偁傞丅 6儢寧偛傠
偐傜侾嵨慜屻傑偱偺娫偼丄傎偲傫偳偺愒偪傖傫偑壗傜偐偺宍偱恖尒抦傝傪偡傞偲尵傢傟丄俈乣俉儢寧偛傠偑僺
乕僋偱偁傞丅俋儢寧偛傠偵側偭偰傕恖尒抦傝丄応強尒抦傝偼嫮偄偑丄偍曣偝傫偵書偐傟偰偟偽傜偔偡傞偲丄埨
怱偟偰廃埻偺傕偺偵暔偵嫽枴傪帵偟巒傔傞偲偄偆曄壔傕婲偙偭偰偔傞丅偙偙偱偼姷傟側偄幚尡忬嫷偐傜惗偠傞
偱偁傠偆晄埨偑丄拲帇棪偺掅偝偵塭嬁偟偨偲峫偊傜傟傞丅
丂傑偨丄寧楊暿偵巋寖拲帇棪傪斾妑偟偨寢壥偐傜丄俁亅俈儢寧帣偱岝傪斀幩偡傞戝偒偄慺嵽傪梡偄偨巋寖倎偲
彫偝偄慺嵽傪梡偄偨巋寖們丄倓偺娫偵桳堄嵎丄桳堄孹岦偑傒傜傟偨偑丄戝偒偄慺嵽偵斾傋丄彫偝偄慺嵽偵懳偡
傞拲帇偑婲偙傝偵偔偐偭偨偙偲偑傢偐傞丅惗屻俁乣係儢寧偱偼丄栚偺摦偒偼偐側傝傛偔側傞丅偍曣偝傫偺巔傗丄
摦偔偍傕偪傖側偳傪挿偄娫捛帇偱偒傞傛偆偵側傝丄婡寵偺傛偄偲偒偵偼丄拲帇偟偨傝廃埻傪尒夞偟偨傝丄惡丄
暔壒偺偡傞曽傪尒偨傝偡傞丅杮幚尡偵偍偄偰傕丄俁儢寧帣偺拲帇傪娤嶡偡傞偙偲偑偱偒偨丅偟偐偟傑偩帇椡偼
枹弉偱偁傞丅偦偺偨傔巋寖們偲倓偵懳偡傞拲帇棪偑掅偔側偭偨傕偺偲巚傢傟傞丅
丂偛偔彫偝側暔傪尒偮偗傜傟傞傛偆偵側傞偺偼惗屻俁乣俇儢寧偱偁傞偑丄摿偵嵶偐偄暔偵嫽枴傪帵偟丄娭怱傪
帩懕偝偣尒偮傔傞傛偆偵側傞偺偼惗屻俇乣侾侽儢寧崰偱偁傞丅偦偟偰丄巋寖倎偵偍偄偰偼岝傪斀幩偡傞偲偄偆
摿挜偑拲帇傪懀偟偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅偮傑傝丄3亅7儢寧帣偱偼丄慺嵽偑戝偒偄偙偲傗丄岝傪斀幩偡傞偲偄
偆丄枹弉側帇椡偱傕擣抦偟傗偡偄摿挜傪傕偮巋寖偵懳偟偰拲帇棪偑崅偔側偭偨偲尵偊傞丅俉亅侾俀儢寧帣偱巋
寖們丄倓偵偍偗傞拲帇棪偑倎丄倐偺偦傟偲傎偲傫偳嵎偑側偐偭偨偺偼丄偙偺嵶偐偄傕偺傪偠偭偲尒偮傔傞偲偄
偆擻椡傪恎偵偮偗偰偄偔抜奒偵偁傝丄摿偵彫偝偄傕偺偵懳偡傞斀墳偑晀姶偵側偭偰偄傞偙偲偑峫偊傜傟傞丅偦
偺擻椡偑掕拝偟偨侾俉亅俀俀儢寧帣偵偍偄偰偼丄嵞傃擣抦偑梕堈側戝偒偄傕偺丄岝傪斀幩偡傞傕偺偵懳偡傞拲
帇棪偑崅偔側偭偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅
Fig 4 巋寖暿暯嬒拲帇棪
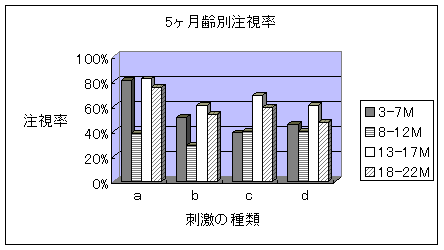 Table 6丂暘嶶暘愅
Table 6丂暘嶶暘愅
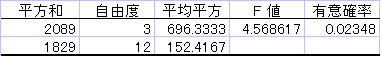

嘩丏慡懱揑側摙榑
丂幚尡偵偍偄偰拲帇埲奜偵傕娤嶡偝傟偨峴摦偑偁傞偺偱丄堦恖傂偲傝偺婰榐偐傜偦傟傜傪嫇偘偰傒傞丅偙偙偱
偼丄暘愅偺僒儞僾儖偲偟偰寢壥傪梡偄傞偙偲偑偱偒側偐偭偨旐尡帣偺峴摦偵偮偄偰傕婰弎偡傞丅僇僢僐撪偼偦
偺旐尡帣偺寧楊偱偁傞丅
傑偢幚尡拞偵媰偔旐尡帣偑係恖偁偭偨乮8.7,9.0,11.5,17.20乯丅偙傟偼丄幚尡幰偵懳偡傞恖尒抦傝丄僇儊儔
偑愝抲偝傟偰偄傞丄惷偐偱偁傞偲偄偆晛抜偲偼堘偆娐嫬丄暤埻婥偱偺応強尒抦傝側偳偵傛傞晄埨偐傜媰偄偨偲
巚傢傟傞丅壛楊偵敽偆曄壔偺峫嶡偱傕弎傋偨丄恖尒抦傝偺嫮偄帪婜乮俉亅侾俀儢寧乯偵偁偰偼傑傞旐尡帣偑懡
偄丅傑偨丄幚尡傪峴偭偨偺偑恎懱専嵏側偳傪峴偆堛柋幒偱偁偭偨偺偩偑丄曐堢巑偵傛傞偲丄17.20帣偼恎懱専
嵏偺偲偒偵傛偔媰偄偰偄傞偲偺偙偲偩偭偨丅8.7帣偼丄巋寖偺採帵偲採帵偺娫偵媰偒婄傪尒偣偨偑丄採帵傪奐
巒偟巋寖偺棊壓偵婥偯偔偲媰偒傗傓偙偲偑偁偭偨丅姷傟側偄幚尡忬嫷偲偄偆晄埨偺梫場偐傜巋寖乮慺嵽偺摦偒乯
偵拲堄偑偆偮偭偨丄偮傑傝愒偪傖傫偺拲堄傪晄埨側忬嫷偐傜偦傜偡偙偲偺偱偒傞傕偺偱偁傞偙偲偑暘偐傞丅傑
偨丄晄埨偘側婄偱採帵偝傟偨巋寖傪尒偨屻丄書偄偰偄傞曐堢巑偺婄傪妋擣偡傞傛偆偵怳傝曉傞偲偄偆旐尡帣
乮9.24乯偺峴摦偺孞傝曉偟傕丄晛抜偲堘偆忬嫷偺拞偱偺晄埨偐傜婲偙偭偨傕偺偱偁傝丄曐堢巑偺婄傪尒傞偙偲
偵傛傝埨怱偟偰偄偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞丅
巋寖偵懳偡傞峴摦偱偼丄巋寖傪採帵偡傞偲庤傪怢偽偟偮偐傕偆偲偡傞峴摦偑尒傜傟偨乮5.8,7.20,10.3乯丅惗
屻5儢寧偵側傞偲丄栚偺慜偺傕偺傪偮偐傕偆偲偡傞傛偆偵側傞丅幚尡偱偼丄5.8帣偼巋寖傪栚偺慜偵採帵偝傟丄
斀幩揑偵庤傪怢偽偟偰偮偐傕偆偲偡傞偑丄梕婍撪偺慺嵽偺摦偒偵婥偯偔偲偦傟傪尒傞偙偲偵廤拞偟庤偺摦偒偼
偲傑偭偨丅偦偟偰採帵偑廔椆偟幚尡幰偑巋寖傪夋梡巻偺屻傠偵栠偡偲丄偦偺摦偒傪偒偭偐偗偵偟偰巋寖傪捛偆
傛偆偵傑偨庤傪怢偽偟偮偐傕偆偲偡傞丄偲偄偆孞傝曉偟偑偁偭偨丅偙傟偼丄庤傪怢偽偡峴摦偑斀幩揑側傕偺偱
偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞偲巚傢傟傞丅7.20帣偲10.3帣偱偼巋寖偺棊壓偵婥偯偄偰傕丄拲帇偟側偑傜庤傪怢偽偟偰
偄傞偙偲偑懡偐偭偨丅
拲帇偵偍偄偰偼恎傪忔傝弌偟偰墶偐傜梕婍撪傪偺偧偒偙傓條巕偑偁偭偨乮20.22乯丅
旕忢偵報徾揑偩偭偨偺偼丄悈拞傪備偭偔傝棊偪傞慺嵽傪拲帇丄傑偨偼捛帇偟側偑傜徫偆乮5.8,7.20,10.3,20.22乯
條巕偱偁傞丅偳偺旐尡帣傕惡偼偨偰側偐偭偨偑丄1昩掱搙偺傕偺偐傜丄侾侽昩嬤偄徫偄偑尒傜傟偨丅拲帇偟偰偄
傞娫傆傢乕偭偲慺嵽偑晳偆偺偵崌傢偣傞傛偆偵岥傪戝偒偔奐偗偰徫偄丄慺嵽偺摦偒傪妝偟傫偱偄傞傛偆側旐尡
帣傕偁偭偨丅偙偺斀墳偼悈偺擖偭偰偄側偄傕偺偱偼婲偙傝偵偔偐偭偨偑丄偙偙偱傕備偭偔傝偲偟偨摦偒丄偠偭
偔傝尒偰妝偟傓梋桾偺偁傞摦偒偑塭嬁偟偨傕偺偲巚傢傟傞丅
暘愅偺曽朄偱弎傋偨丄幚尡幰偲偺傗傝庢傝傪妝偟傫偱偄傞偲巚傢傟偨16.2帣偱傕徫偄偑傒傜傟偨丅偙偺旐尡帣偼
丄幚尡幰偑巋寖傪採帵偡傞偲丄徫偄側偑傜書偐傟偰偄傞曐堢巑偺傂偞偺忋偱棫偪偁偑傞傛偆偵偟偰恎傪傛偠傜偣
偨丅傑偨丄幚尡幰偺婄偺丄夋梡巻偱塀傟偰偄側偄栚偺晹暘傪帇慄偑崌偆傑偱尒偮傔丄帇慄偑崌偆偲摨偠傛偆偵徫
偄側偑傜懱傪摦偐偟偨丅偙傟偼丄巋寖偺摦偒偵懳偡傞徫偄偲偄偆傛傝傕巋寖傪採帵偟偨幚尡幰偲偺娭學偵偍偄偰
偺徫偄偱偁傞丅娭楢偟偰丄巋寖拲帇偺帪娫傪寁應偟偨偺偩偑丄帇慄偑巋寖偐傜偼偢傟傞偲偒丄巋寖傪採帵偟偰偄
傞幚尡幰傗丄價僨僆僇儊儔乮傑偨偼嶣塭傪峴偭偰偄傞幚尡幰乯傪尒傞條巕偼慡偰偺旐尡帣偵娤嶡偝傟偨丅擔忢惗
妶偱壗偐暔傪尒偣傜傟傞偲偄偆偙偲偼丄愒偪傖傫偵偲偭偰偼偁傗偟偰傕傜偆丄堦弿偵梀傇偲偄偭偨懠幰偲偺僐儈
儏僯働乕僔儑儞応柺偵婲偙傞偙偲偱偁傞偨傔丄幚尡拞偵巋寖傪採帵偡傞幚尡幰傪尒偨偺偱偼側偄偐丅
偙偺偙偲偼巆偝傟偨壽戣偱傕弎傋傞偑丄旐尡帣偲幚尡幰偑岦偒崌偭偰偄傞偲偄偆幚尡偺宍懺傪専摙偡傞傋偒偱偁
傞丅偟偐偟丄偙傟傜偺峴摦偼愒偪傖傫偲偍傕偪傖偺帇揰偐傜峫偊傞偲丄偍傕偪傖偑偦傟偺傒偱愒偪傖傫偺堄梸丒
娭怱傪怢偽偟偨傝丄恎懱婡擻偺敪払傪懀偡巋寖偲側傞偩偗偱側偔丄偦傟傪捠偟偰戝恖偲偺偐偐傢傝傪妝偟傔傞傕
偺偱偁傝丄戝恖偲偍傕偪傖傪梡偄偰梀傇偲偄偆宱尡偺孞傝曉偟偑懠幰偲偺僐儈儏僯働乕僔儑儞婡擻偺敪払傪懀偡
傕偺偱偁傞偲偄偆偍傕偪傖偺婡擻傪帵嵈偡傞傕偺偲巚傢傟傞丅摨帪偵丄戝恖偑偍傕偪傖傪條乆側曽朄偱採帵偟偨
傝丄偦偺嵺偵愒偪傖傫傪尒偮傔丄榖偟偐偗偨傝偡傞偙偲偑丄愒偪傖傫偺傕偺偵懳偡傞嫽枴傪偄偭偦偆嫮偔偟丄帺
傜摥偒偐偗偰偄偔偙偲傪妎偊傞傛偆偵傕側傞偺偱偁傞丅
偝傜偵丄巋寖偺採帵捈屻傗丄採帵拞偵婘偺壓傪尒傞偲偄偆峴摦偑尒傜傟偨乮9丄13.12丄14.12丄16.13乯丅惗屻
8乣俋儢寧偵側傞偲丄 暔偺棫懱姶丄墦嬤姶傪偮偐傔傞傛偆偵側傝丄棊偪偰偄偔傕偺傪栚偱捛偭偰偦偺峴偒愭傪妋
擣偡傞側偳丄暔帠偺場壥娭學偵嫽枴傪妎偊傞丅幚尡偱偼丄棊壓偟偨慺嵽偼幚尡幰偺庤偺晹暘偱尒偊側偔側傞偺偩
偑丄幚尡幰偺庤偲婘偲偺姶妎偼俆乣侾侽們倣掱搙偱偁傞偺偱丄棊壓偺嵟廔抧揰偑暘偐傝偵偔偄丅梕婍撪傪棊壓偡
傞慺嵽傪丄幚尡幰偑埇偭偰偄傞儁僢僩儃僩儖偺傆偨偺晹暘傑偱捛帇偟偨屻丄慺嵽偑偝傜偵壓傑偱棊偪偰偄傞偺偱
偼側偄偐偲偄偆偙偲傪妋偐傔傞峴摦偩傠偆丅
丂愭偵傕弎傋偨傛偆偵丄悈拞偱備偭偔傝偲棊壓偡傞巋寖傪愒偪傖傫偑嬫暿偟偰偄傞偙偲偑暘偐偭偨丅偟偐偟丄慺
嵽偺摿挜偵傛傞棊壓懍搙偺堘偄偲拲帇棪偺曄壔偐傜丄備偭偔傝偱偁傞傎偳愒偪傖傫偑巋寖傪拲帇偡傞偺偱偼側偄
偲偄偆偙偲傕暘偐偭偨丅巋寖偺拲帇偵偼丄偦偺慺嵽偺戝偒偝丄幙乮杮幚尡偵偍偄偰偼岝傪斀幩偡傞偐偟側偄偐乯
偩偗偱側偔丄揔搙側懍偝偑塭嬁偡傞偙偲偑峫偊傜傟傞丅偦傟偼丄愒偪傖傫偑摦偒偲偟偰擣抦偱偒傞懍搙丄偦偺摦
偒傪尒偰妝偟傓偙偲偺偱偒傞懍搙偱偁傞丅偝傜偵戝偒偝偺堘偄偲寧楊偛偲偺斾妑偱弎傋偨傛偆偵丄崱夞偺幚尡偵
偍偄偰丄敪払抜奒偵傛偭偰岲傓巋寖偑堎側傞孹岦偑尒傜傟丄偍傕偪傖偑愒偪傖傫偺僷乕僩僫乕偲偟偰丄偦偺敪払
偵恊枾偵偐偐傢傞偙偲偑偆偐偑傢傟傞傕偺偱偁偭偨偲尵偊傛偆丅
丂幚尡偱梡偄偨巋寖偺偆偪丄悈偺擖偭偨巋寖偼愒偪傖傫偺拲帇傪懀偡慺嵽偱偁傝軅絺粋虙崕媯蛠A廤拞傪敽偆傕
偺偱偁傞偙偲偑暘偐偭偨丅偦偟偰帪偵偼徫傒傪傂偒偍偙偡偙偲傕暘偐偭偨丅偙偺傛偆側摿挜傪庢傝擖傟偨偍傕偪
傖偑彮側偄偙偲偵壛偊丄偙偺悈拞偱偺娚傗偐側摦偒偲偄偆偺偼擔忢応柺偱偼宱尡偟偵偔偄傕偺偲巚傢傟傞丅傛偭偰
愒偪傖傫偑條乆側姶妎傪宱尡偡傞偨傔偺丄帇妎巋寖偺傂偲偮偵側傞偲尵偊傞偺偱偼側偄偐丅
丂
 僩僢僾儁乕僕
僩僢僾儁乕僕
 亂寢壥偲峫嶡亃
亂寢壥偲峫嶡亃

Table 3丂暘嶶暘愅
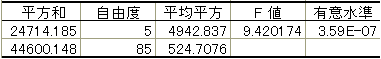
Fig 2 巋寖暿暯嬒拲帇夞悢
Table 4丂暘嶶暘愅
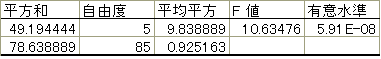
Fig 3 巋寖暿暯嬒拲帇棪
Table 5丂暘嶶暘愅
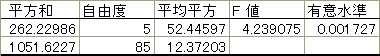


Table 6丂暘嶶暘愅
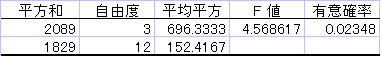

 僩僢僾儁乕僕
僩僢僾儁乕僕