援助要請について
印象評価について
仮説
方法
結果と考察
引用文献
|
調査対象 三重県内の大学生184名に質問紙調査を行い,有効解答数は184名(男性95名,女性89名)。平均年齢は19.70歳,標準偏差は1.12であった。 調査時期および方法 2015年7月下旬〜10月初旬 大学の講義時間に配布し,調査者が注意事項を説明し,回答者にはフェイスシートを読んでからから回答させた。説明を了解し同意が得られた場合に回答するよう依頼した。回答後,調査票はその場で回収した。回答の所有時間は約20分であった。 質問紙の構成 場面想定法を用いた。想定内容としては,ある場面(ストーリー)においてその中心人物が別の人物に援助要請を行うものである。質問紙は,それぞれの場面において,そのなかで援助要請を行う者に対する印象を第3者の立場で評価するものである。 質問紙の構成として,印象評価尺度と4つの質問すなわち,想定場面のなかの援助要請者主人公に対する好感度,その要請にあなたなら応えるか,その場面の援助要請に正当性があるか,あなたがもし要請者の立場なら要請をするかどうかの可能性(それぞれ5段階評定),その他に,被援助志向性,援助要請スタイル,対人志向性の3つの尺度によって構成された。 想定場面は,野崎・石井(2004)の援助要請行動の抑制要因に基づく援助要請行動の分類から,Aお金を借りる場面,B勉強を教えてもらう場面,C仕事の手伝いを頼む場面,D就活についての相談場面の4つを選択し,それぞれの場面において,援助要請の妥当性が高いパターンと妥当性が低いパターンをオリジナルで作成した。援助要請の場面は,基本的に,最初は一人でがんばってみるが,途中で行き詰まり,他者に援助を要請しようと決断して,具体的に他者に援助を要請するところまでを,想定上の話として設定した。その要請の仕方,あるいは要請の経緯が,要請者として一般的に妥当であり理解され得るものの場合は「妥当性高」とし,要請者のわがまま独断によるもので一般的には理解され得ない場合は「妥当性低」として設定した。質問紙は,A妥当性高・B妥当性低・C妥当性高・D妥当性低の組み合わせと,A妥当性低・B妥当性高・C妥当性低・D妥当性高の組み合わせで2パターンの質問紙を作成した。調査実施時においては,これをランダムに配布した。 また,フェイスシートにおいて,学年,年齢,性別を尋ねた。 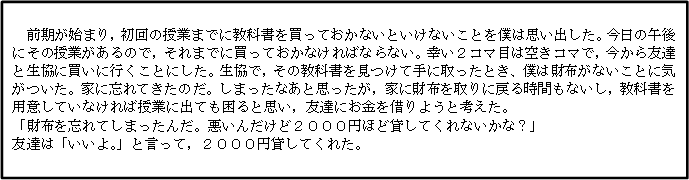 場面A・妥当性無 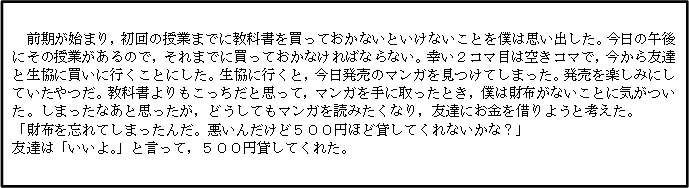 場面B・妥当性有 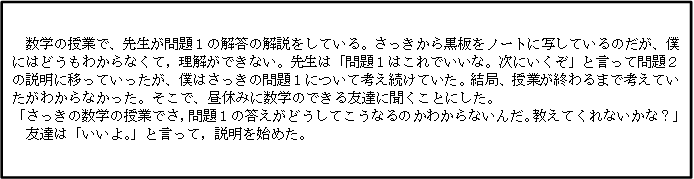 場面B・妥当性無 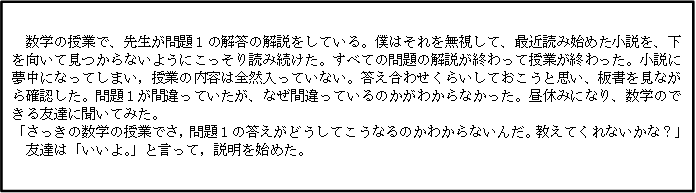 場面C・妥当性有 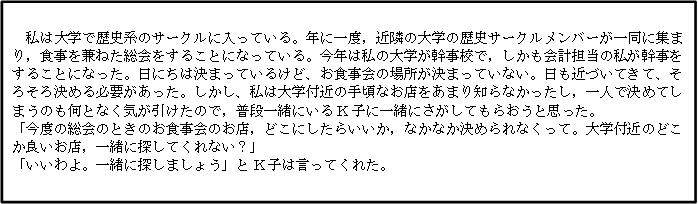 場面C・妥当性無 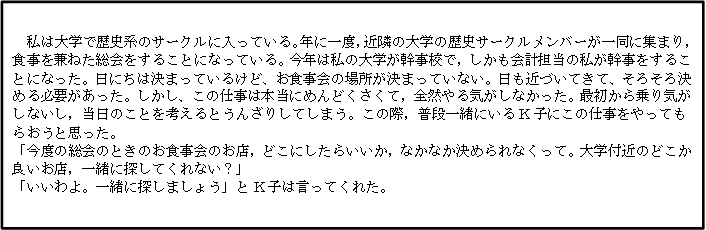 場面D・妥当性有 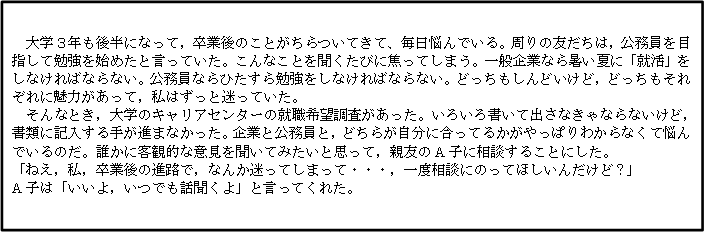 場面D・妥当性無 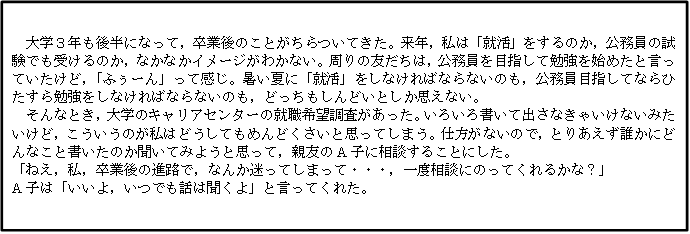 印象評価尺度(16項目) 大橋・三輪・平林・長戸(1973)によって作成された印象評価尺度(形容詞対からなるもの)から,見た目からしか判断できないような印象評価項目や対象者の気分を推測して尋ねる項目を削除し,文章から読みとれると思われる項目を使用した。その結果,「個人的親しみやすさ」因子6項目,「社会的望ましさ」因子4項目,「活動性」因子5項目,どれにも当てはまらない1項目の計16項目を選び印象評価尺度とした。両極形容詞の5点尺度で測定した。この尺度上で,提示された場面での援助要請者についてどんな印象を持ったかを尋ねた。 被援助志向性尺度(11項目) 回答者自身の被援助志向性を尋ねるために,田村・石隈(2001)によって作成された被援助志向性尺度を使用した。「援助の欲求と態度」因子7項目,「援助関係に対する抵抗感の低さ」因子4項目の計11項目からなり,「あてはまらない」から「あてはまる」までの5件法で測定した。 援助要請スタイル尺度(12項目) 回答者自身の援助要請スタイルを尋ねるために,永井(2013)によって作成された援助要請スタイル尺度を使用した。「援助要請過剰型」因子4項目,「援助要請回避型」因子4項目,「援助要請自立型」因子4項目の計12項目からなり,「あてはまらない」から「あてはまる」の5件法で尋ねた。いくつかの項目においてすべてが「悩み」という単語を使用して尋ねていたため,「悩み」と「困りごと」が同数になるように文章を変更した。 対人志向性(18項目) 回答者自身の対人志向性を測定するために,斎藤・中村(1987)によって作成された対人志向性尺度を使用した。「人間関係志向性」因子9項目,「対人的関心・反応性」因子5項目,「個人主義傾向」因子4項目の計18項目からなり,「全くそう思わない」から「そう思う」の5件法で尋ねた。 |
援助要請について
印象評価について
仮説
方法
結果と考察
引用文献