1.実験デザイン
2者間の相互作用について、対人距離(近距離、遠距離)の要因を操作した実験デザインである。なお、対人距離は被験者間要因とした。
また、性の組み合わせと2者の関係性を統制するため、被験者は初対面の同性ペアとした。これは、これまでの研究から、性の組み合わせや2者の関係性が非言語的行動に影響を与える(和田, 1990;市河ら, 1989)ことが報告されていることに基づく。
さらに、2者の会話の盛り上がりが、ペアを構成する個人の特性によって異なることが考えられる。よって、被験者の言動や話の盛り上がりによって不安が喚起されるという要因を統制するため、会話をする2者のうち一方は、実験者が実験内容を理解させた上で選定した実験協力者(以下、協力者)とした。これにより、各組は、同性の協力者と被験者の2人で構成された。
協力者は、男子大学生1名(21歳)と、女子大学生1名(22歳)であった。協力者は、被験者と初対面かつ同性であり、また、被験者に対して自らが協力者であることを告げず、終始同じ被験者として振る舞わせた。
ペアの数は、同性同士の34組(男性同士18組、女性同士16組)とした。
各組について、近距離条件と遠距離条件のうちどちらかをランダムに行った。対人距離とは、一方の椅子の前脚から他方の椅子の前脚の間の距離とした。対人距離の水準は、近距離条件(76.2cm)と遠距離条件(213.4cm)であった。この距離は、先に述べたホールの分類のうち、個人距離の近接相(45.7〜76.2cm)と遠方相(76.2〜121.9cm)の境界である76.2cmより、これを近距離とした。同様にして、社会的距離の近接相(121.9〜213.4cm)と遠方相(213.4〜365.8cm)の境界である213.4cmより、これを遠距離とした。
両条件において、入室し実験者と協力者及び被験者の自己紹介の後に、会話前の質問紙に記入を求め、話す内容を考え実際に会話をした後に会話後の質問紙に記入を求めた。
実験は、平成18年1月初旬に行われた。
2.被験者
M大学学生34名(男性18名、女性16名、平均年齢は21.8歳)を対象とした。全ての被験者は協力者と初対面であった。この点は、前もって各被験者について既知かどうか協力者に確認した。
3.質問項目
会話実施前と会話実施後それぞれで以下のような質問紙構成とした。
1.会話実施前
STATE-TRAIT ANXIETY INVENTORY(STAI)日本語版(大学生用)
会話実施前の状態不安を測定するために、STAI日本語版(大学生用)のうちA-Stateの20項目(清水・今栄, 1981)を用いた。会話実施前は、いま現在どのような感じをもっているかを「全くそうである」から「全くそうでない」の4段階評定で回答を求めた。
2.会話実施後
STATE-TRAIT ANXIETY INVENTORY(STAI)日本語版(大学生用)
会話実施後の状態不安を測定するために、会話実施前と同一項目を用いた。会話実施後は、会話実施前と同じ項目を用いて会話をしている間にどのような感じをもったかについて「全くそうである」から「全くそうでない」の4段階評定で回答を求めた。
ACT(affective communication test)
被験者のノンバーバル行動の表出について測定するためにACT(affective communication test;Friedman et al., 1980 ; 日本版, 大坊, 1991b)を参考に10項目を用い、「よくあてはまる」から「まったくあてはまらない」の5段階評定で回答を求めた。
ノンバーバルスキル尺度改訂版
被験者に気分を非言語的行動に反映することを避けるスキルがどの程度あるか、相手の非言語的行動を正しく解釈する感受性スキルがどの程度あるかを検討するために、ノンバーバルスキル尺度改訂版(和田, 1992)を参考に15項目を用い、被験者自身がどの程度あてはまるか、「よくあてはまる」から「あまりあてはまらない」の5段階評定で回答を求めた。
4.手続き
所定の場所で被験者と協力者を待ち合わせ、協力者と被験者が揃ってから実験室に同時に導入した。そして、あらかじめ距離を設定し向かい合わせた椅子に、椅子を動かさず座るように促した。このとき、協力者をFigure1の「協」の位置に、また被験者をFigure1の「被」の位置にそれぞれ着席させた。
実験室環境について
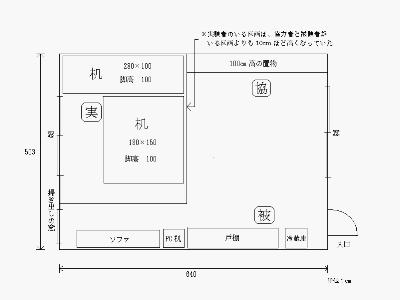
Figure1 実験室の様子
(上図の協力者と被験者の距離は遠距離条件)
照明 40形36ワット蛍光灯(MITSUBISHI/OSRAMネオルミスーパー ラピッドスタート FLR40SW/M/36)4本
室温 エアコン(MITSUBISHI霧ヶ峰SFX MSZ-SFX32FS-W '99年製)の温度調節により、25℃に保った。
実験者はこの後、実験者の自己紹介(所属と名前)をした上で、実験の目的について「会話がどのような仕組みで成り立っているかについて調べる」と説明し、「まず最初にアンケートに答えてもらい、その後お2人に、大学生活を送る上でどんなアルバイトをしているか、またはしていたか、そしてどんなアルバイトをしてみたいかということ、大学生活におけるアルバイトの意義ということについて5分ほど考えていただいた後で、約5分程度話し合ってもらいたい。いくつかのテーマで、今回行うものと同じようなかたちで会話をしてもらっている。また、最後にアンケートに回答してもらいたい」と告げた。
初めに、被験者同士簡単な自己紹介をさせた。
その後、まず、会話実施前の質問紙(状態不安についての尺度)について回答を求めた。
そして、5分間考えさせ、会話をさせた。なお、会話時、協力者には、話題展開の統制リストにより、話題展開をさせた。本実験において「アルバイト」の話題を選んだのは、市河ら(1989)によると、アルバイトについての話題は、「比較的興味があり、話しやすい話題」とあったため、本研究でもこの話題を用いることにした。
実験者は、協力者および被験者に実験の進行に関わる説明をする際以外は、直接の影響を与えないようFigure1の「実」の位置に被験者に背を向けて座り、協力者および被験者の両者と視線が交錯することがないようにした。
相互作用終了後、会話実施後の質問紙(会話前と同じ状態不安を測る尺度、ノンバーバルスキルを測る尺度)に回答させた。また、協力者にも被験者と全く同一の質問紙について同様に回答させた。このとき、被験者の特性が会話に影響する要因を考慮し、協力者は、被験者が対人不安についてどのような特性を持っていると判断したかを、質問紙末の枠内に書いた。協力者は、被験者からは自分と同じように質問紙に回答していると見えるようにした。
実際の実験目的を告げ、お礼を述べて終わった。また、被験者が会話をした人物が協力者であったことは、本研究における実験終了を持って全ての被験者に連絡した。
本研究における実験の所要時間は、全体を通して、約15分であった。
なお、協力者には、会話時の行動について、視線や表情、体の動きなどについて過度に大きな行動をとらず、普段初対面の人と接するときのように接するという教示を与え行動させた。また、協力者の服装が被験者に与える影響を少なくするため協力者の服装は黒っぽい服を着用するようにさせ、協力者同士で異ならないようにした。さらに、会話内容を統制し実施回ごとの会話内容や話の盛り上がりが異なることのないよう、協力者自身がどのような会話を展開させるか話題の統制をした。