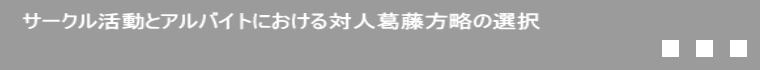1.大学生の課外活動
部活動やサークル活動などの課外活動,あるいはアルバイトは,大学生にとって学業以外の重要な関心事である.これらの活動は,大学生のどのような成長を導くのであろうか.
新井・松井(2003)・・・部活動・サークル集団は,これらの集団の本来の目的である,興味を満たし,技術を向上させる機能だけでなく,集団に所属することで得られる友人関係や先輩後輩関係によって対人関係的な機能も果たしている.
小平・西田(2004)・・・大学生のアルバイトに関する調査研究.調査対象となった学生の9割が,自らのアルバイト経験に対して何らかの意味づけをしている.そして,その意味づけの内容として「人間関係における成長」や「仕事に対する意識の高まり」などを多くの学生が挙げている.
このように,大学生の課外活動は,大学生活の充実感や大学生の成長に対し,時として学業以上に大きな役割を果たしていると考えられる.
以下,本研究では,大学生の課外活動集団の「部」「サークル」という名称を区別することなく「サークル集団」という表記に統一し,この「サークル集団」が行う活動を「サークル活動」と表記する.さらに,この「サークル集団」には,いわゆる委員会などの集団も含むこととする.また,アルバイト先の職場(大きい組織の場合には同じ部署)の集団について,「アルバイト集団」と表記する.
2.青年期の所属集団における対人関係の機能
松井(1990)・・・青年期の友人関係が青年の社会化において果たす機能として,「安定化の機能」「社会的スキルの学習機能」「モデル機能」の3つがある.これら3つの機能は,友人という,年齢や社会的立場は対等でありながら,家族にはない異質性をもつ存在から得られるものである.
大学生にとって,家族以外に日常的に関わる他者や親しいつきあいを持つ他者は,対等な立場である友人だけではない.例えば,大学の教員,サークル集団の先輩や後輩,アルバイト先の上司などが挙げられる.このような他者との関係においても,松井(1990)のいう3つの機能が果たされるだろう.特に「社会的スキルの学習機能」や「モデル機能」は,例えばサークル集団の同輩の関係よりも,集団における所属期間や人生経験の豊富な,先輩に対する関係において,より強いと考えられる(新井,2004 ).
宮下(1995)・・・集団活動における先輩後輩関係の3つの意義
◇ある目標をみんなで共有し,リーダーの下に協力してそれを育んでいく点.同年齢での集団よりも,職場集団などの社会の実態に近いかたちで意見の交換や課題を解決するといった経験をすることで,青年の信念や価値観も徐々に明確になっていく.
◇リーダーや先輩への礼儀と尊敬の態度や,上下関係の中でうまく自分の役割を遂行する能力などを主とした社会性の獲得.
◇集団内での役割を上手く果たすことを学ぶという点.先輩と後輩とが,それぞれの果たす役割の違いにも意識を向けながら,各自が自分の役割の重要性を認識し,集団の中でその役割を遂行していくことが,集団活動を維持する上でどうしても求められる.
3.対人葛藤
所属する集団における他者との関わり,特に先輩後輩関係は,青年期にある大学生にとって大きな意味をもつと考えられる.しかしながら,サークル集団やアルバイト集団で,先輩や後輩,あるいは上司と上手く関わることが難しいと感じている大学生も少なくないだろう.これらの悩みは,集団の中で上手くやっていくことや,集団全体として活動を維持していくことの妨げになると考えられる.
高井(2008)・・・大学生において悩みが生じる人間関係の種類として,友人関係の他に先輩後輩関係やアルバイト先の人間関係などが挙がっている.悩みの内容としては,「対人スキル不足・コミュニケーションスキル不足」「合わない相手との関係」「考え方の異なる他者との共存」などがあった.
他者との意見の食い違いや対立,他者から妨害や邪魔をされるなどの不愉快な状態のことを,対人葛藤という.
大坊・奥田(1996)によると,Kelley(1987)は対人葛藤を「ある人の行動,感情,思考の過程が,他の人によって妨害される状態」と定義している.対人葛藤のような状態は,誰もが避けたいと考えるものであるが,社会的接触において,関係者が抱く認知や意見が自然に一致することの方がむしろ稀であり,避けられない面もあることは確かである.
4.葛藤解決方略
葛藤は人々の営みに悪影響を及ぼすばかりではない.組織心理学などの研究分野においては,葛藤を経験してそれをうまく乗り越えることは,組織の構造や運営の見直しのきっかけになるなど,むしろ組織の成長にとって必要なことであるという見解が主流となっている(大渕,1997).葛藤解決を通して互いの気持ちが理解でき,その後のつきあいがスムーズになることや,腹を割って話し合うことによって以前よりも親しくなることもある(大渕,2003).
葛藤を解決しようとして人々が試みる行動は「葛藤解決方略(conflict resolution strategies)」と呼ばれ,家族,友人,職場など様々な領域で研究が行われており(福島・大渕,1997),藤森(1989)やOhbuchi & Kitanaka(1991)などの諸研究によって葛藤解決方略の分類が試みられてきた.
大渕(2005)によると,葛藤解決方略分類の研究において最も一般的に使用されてきたものはThomas
& Kilmann(1975)の二重関心モデルであると述べられている.この二重関心モデルとは,「自己志向性」と「他者志向性」の2次元によって葛藤方略を分類するものである.「自己志向性」とは,方略行使者が自分の願望充足を重視する程度,すなわち自己利益への関心の強さを表し,一方の「他者志向性」は反対に,葛藤相手の願望充足を重視する程度,すなわち他者利益への関心の強さを表すものである.これら2次元の高低の組み合わせによって,「主張」「協力」「妥協」「回避」「譲歩」の5タイプの方略が位置づけられている.
加藤(2003)も,多くの研究者と同様に,この「自己志向性」と「他者志向性」の2次元からなる葛藤方略スタイルモデルをRahim&Banama(1979)を参考に作成し使用している(Figure1).
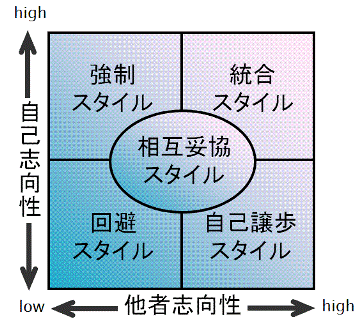
Figure1 加藤(2003)の2次元5スタイルモデル
加藤(2003)は,この 2次元5スタイルの葛藤方略モデルに基づき,対人葛藤方略スタイル尺度(Handling Interpersonal Conflict Inventory:以下HICI)の作成を行った.そして,大学生の友人関係において生じる対人葛藤への解決方略スタイルとして,「統合スタイル」「回避スタイル」「強制スタイル」「自己譲歩スタイル」「相互妥協スタイル」の5スタイルが存在することを明らかにした.
統 合スタイル:方略行使者と葛藤相手の両者が受け入れられるように交渉し,問題を解決しようとする方略群
回 避スタイル:直接的な葛藤を避けようとする方略群
強 制スタイル:葛藤相手の利益を犠牲にしてでも,方略行使者の要求や意見を通そうとする方略群
自己譲歩スタイル:葛藤相手の要求や意見に服従する方略群
相互妥協スタイル:方略行使者と葛藤相手の両者が相互に要求や意見を譲歩し合い,お互いに受け入れられる結果を得ようとする方略群